春になると、暖かくなり自然が息を吹き返す季節。本来なら活力に満ち溢れるはずなのに、なぜか体がだるく、疲れやすくなったと感じることはありませんか?
実はこれ、あなただけではなく多くの人が経験することなのです。冬から春への移り変わりは、私たちの体にとって大きな環境変化であり、体内のエネルギーの流れも大きく変わる時期なのです。
今回は、東洋医学の視点から春の疲れの原因を探り、効果的な対策法をご紹介します。正しい知識と養生法で、この季節を元気に乗り切りましょう。
YouTubeでも解説しています。
春になると疲れやすくなるのはなぜですか?
東洋医学では、春の3ヶ月間を「発陳(はつちん)」と呼んでいます。「発」は何かが外に現れること、「陳」は古いものを意味します。つまり、冬の間に体内に蓄積していた古いエネルギーが外に出てくる季節なのです。
これは自然界の現象と同じです。植物が芽吹き、動物たちが冬眠から覚めて活動を始めるように、私たち人間の体内でも同様の変化が起きています。冬の間は体の内側を守るために「気(エネルギー)」が内側に集中していましたが、春になるとこれが外側へ向かって流れ始めるのです。
しかし、このエネルギーの方向転換は、いわばエンジンがかかり始めたばかりの状態。冬のモードから急に活動モードに切り替わるため、体がその変化についていけないことがあります。
特に「肝気(かんき)」という、体中にエネルギーを巡らせる働きが春には活発になりますが、ストレスや無理な活動でこれが乱れると、疲れやすさや精神的な不調として表れてしまうのです。
春の疲れを解消する漢方薬にはどのようなものがありますか?
春特有の疲れや不調に効果的な漢方薬として、以下のようなものがあります:
- 四逆散(しぎゃくさん):肝気の流れを整え、ストレスによる不調を改善します
- 抑肝散加陳皮半夏(よくかんさんかちんぴはんげ):肝気の昂ぶりを抑え、気血や水分を身体全体に巡らせることで、イライラや不眠を和らげます
- 加味逍遥散(かみしょうようさん):気の巡りを改善し、身体の上部の熱を冷ましながら引き降ろしてきます
- 香蘇散(こうそさん):穏やかに気の巡りを良くし、春特有の憂うつ感や食欲不振を改善します。香りの良い蘇葉(そよう)を含み、ストレスからくる胸のつかえ感も和らげます
- 大柴胡湯(だいさいことう):肝気の鬱滞(うったい)が強く、胸脇部の張りや便秘、イライラが強い方に適しています。肝の熱を冷まして気の流れを改善します
- 柴胡疏肝湯(さいこそかんとう):肝気を調整し、気の巡りを良くするとともに血の流れも促進します。イライラや頭痛、めまいなどの症状を和らげるのに効果的です
これらの漢方薬は、東洋医学での「肝」の機能を整え、気の流れをスムーズにすることで、春に起こりやすい体の不調を和らげる効果があります。
春の疲れを予防・改善するための生活習慣はありますか?
春の疲れを予防・改善するためには、生活習慣の見直しが大切です。以下のポイントを意識してみましょう:
1. 早寝早起きのリズムを整える
春は自然のリズムに合わせた生活が特に重要です。早めに就寝し、朝日を浴びながら軽い散歩をすることで、体内時計を整え、エネルギーの流れをスムーズにすることができます。
2. 適度な運動を取り入れる
激しすぎない適度な運動が効果的です。ウォーキングやヨガ、太極拳などの穏やかな運動は、ストレスを解消し、気の巡りを促進します。特に朝の時間帯に行うと、一日を通してエネルギーレベルを維持しやすくなります。
3. 春の食材を積極的に取り入れる
季節の食材を食べることは、東洋医学では非常に重要視されています。春の若葉や芽ものは、体内の気の流れを助けてくれます:
- 春キャベツ
- レタス
- 菜の花
- タケノコ
- アスパラガス
特に苦味のある食材は、体内の余分な熱を冷まし、停滞したものを追い出す効果があります。ただし、体を冷やしすぎないように、温かい性質の食材と組み合わせるのがコツです。
4. ストレス管理を意識する
春は特に肝の機能が高まる時期です。肝は東洋医学でストレスと密接に関わる臓器とされています。深呼吸やマインドフルネス、アロマテラピーなどでリラックスする時間を意識的に取り入れることで、肝気の流れを整え、春の疲れを軽減できます。
春におすすめの食材や料理法はありますか?
春におすすめの食材には、以下のような特徴があります:
おすすめの春の食材
- 緑の野菜:春キャベツ、菜の花、レタスなど
- 苦味のある食材:菜の花、タケノコ、アスパラガス(体内の余分な熱を冷まし、デトックス効果があります)
- 発酵食品:味噌、醤油、漬物(腸内環境を整え、免疫力を高めます)
春におすすめの調理法
- さっと茹でる:春野菜の持つ生命力を活かす調理法です
- 蒸す:食材の栄養を逃がさず、消化にも優しい調理法です
- 軽く炒める:春は消化機能もまだ完全に活発ではないため、消化しやすい調理法が適しています
特におすすめなのは、春野菜と発酵食品を組み合わせた温かいサラダや、軽く炒めた春野菜の和え物です。これらは、春の「気」の流れを促進し、体の巡りを良くする効果が期待できます。
まとめ:春の養生で元気に過ごそう
春の疲れは、冬から春への移行期に体内エネルギーの流れが変化し、特に「肝気」の流れが影響を受けることで起こります。
この春特有の不調を乗り切るためには:
- 早寝早起きで自然のリズムに合わせる
- 適度な運動で気の巡りを促進する
- 春の食材を積極的に取り入れる
- ストレス管理を意識する
- 必要に応じて漢方薬を活用する
これらの養生法を実践することで、春の疲れを予防・改善し、この季節の持つ生命力あふれるエネルギーを存分に享受することができるでしょう。
体質は人それぞれ異なりますので、より詳しいアドバイスが必要な方は、東洋医学の専門家による体質チェックを受けてみることをおすすめします。あなたに合った漢方や養生法を見つけ、健やかな春をお過ごしください。
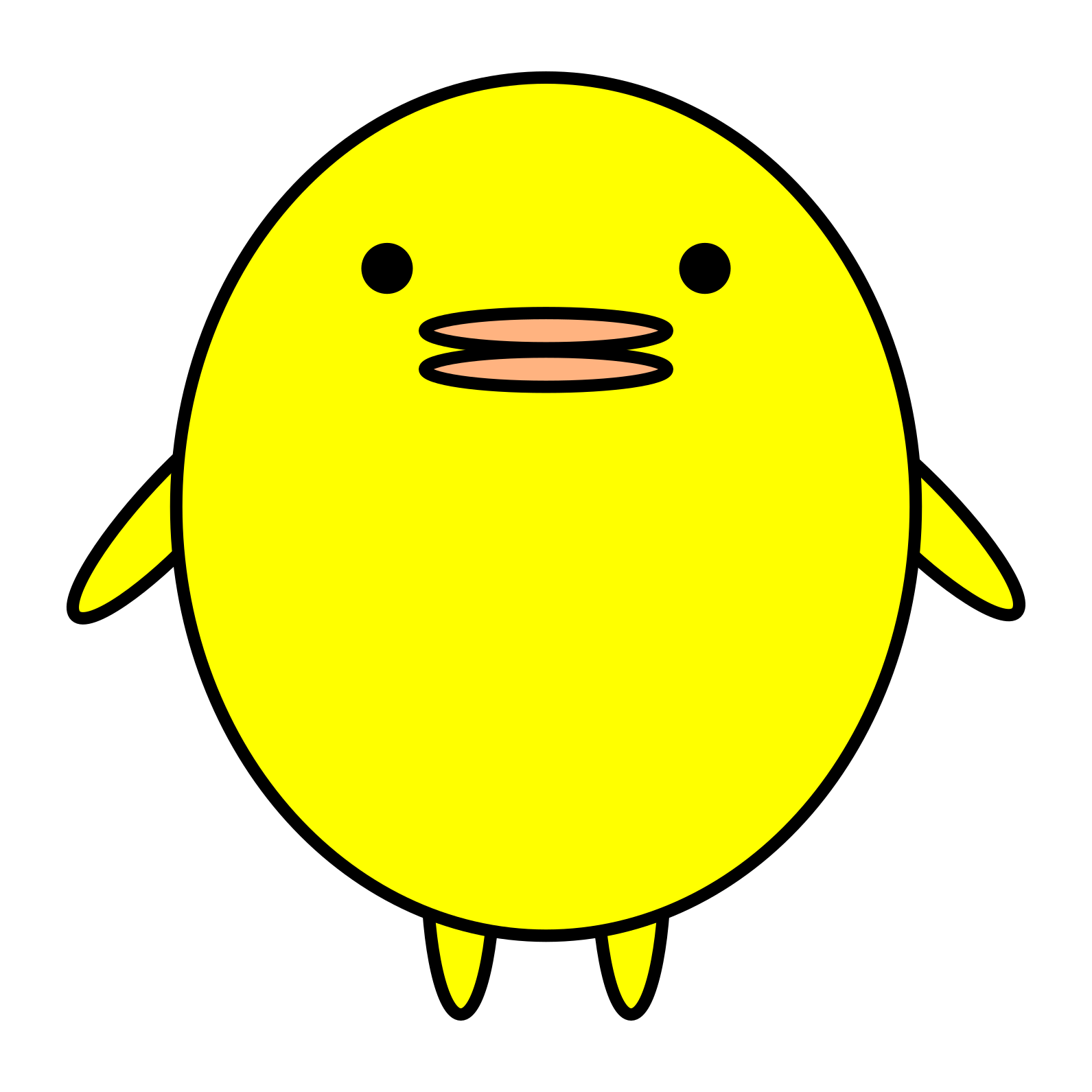
ご自分の体質にあった
漢方薬を試してみたい方は
ピヨの漢方の漢方相談を
ご利用ください。






