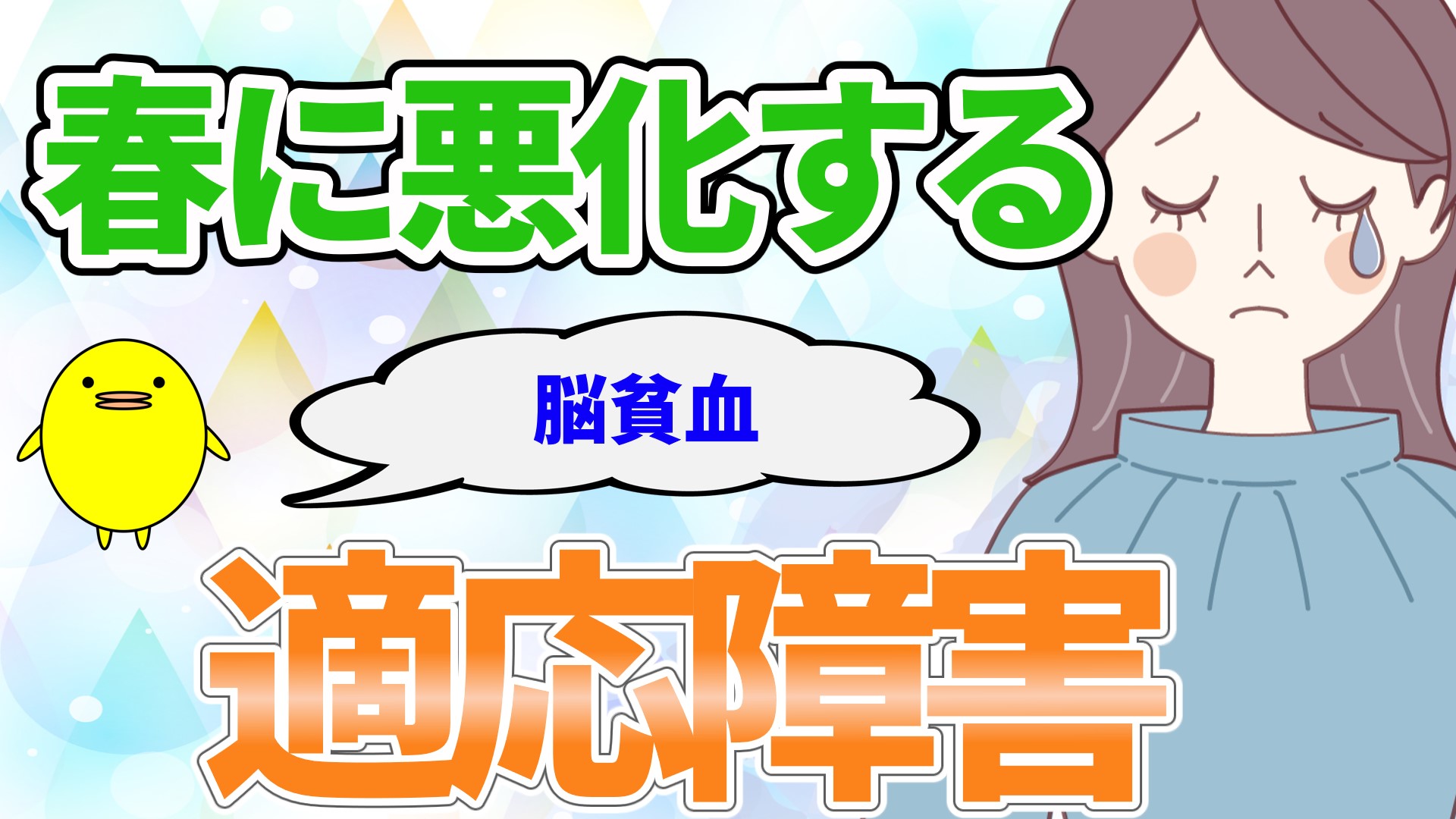こんにちは
どうなさいましたか?

適応障害にお悩みの方から
質問をいただきましたよ。
季節の変わり目、特に春になると体調を崩しやすくなる方が多くいらっしゃいます。特に適応障害や自律神経の乱れを抱える方にとって、春は症状が悪化しやすい季節です。
東洋医学では、冬から春への移行期に「気」の流れが内側から外側へと大きく変化すると考えます。この変化についていけないと、様々な不調が表れるのです。
今回は、適応障害や脳貧血、あかぎれなどの症状が春に悪化するという38歳女性の方の事例を通して、乾燥体質の特徴と効果的な自然療法についてご紹介します。体質を正しく理解して、適切なケアを始めてみませんか?
外見的な特徴とお悩みの症状
まずは相談者の方の基本情報と症状をご紹介します。
- 年齢・性別: 38歳・女性
- 身長: 162cm
- 体重: 47kg
- BMI: 17.91(やせ型)
外見的特徴:
- 皮膚や髪の毛が乾燥している
- 顔色が白っぽい
- 舌の赤みが強い
- 舌の形が厚い
- 舌苔の上の水分が水っぽい
お悩みの症状:
- 適応障害(精神疾患)
- 脳貧血
- あかぎれ
- 不眠
- 春になるとひどくなる症状
現在はレディース鍼灸院で診てもらっているとのことです。
適応障害とはどのような症状ですか?
適応障害とは、生活環境の変化などストレスの原因となる出来事や状況に対する適応がうまくいかず、情緒的または行動的な症状が現れる状態です。
よく見られる症状には:
- 抑うつ気分
- 不安や過度の心配
- 怒りや焦り
- 対人関係のトラブル
- その他行動の変化
こうした症状は、ストレス因子がなくなれば通常は改善しますが、継続的なストレスにさらされると長引くこともあります。
なぜ春になると症状が悪化するのですか?
東洋医学的に見ると、冬の間は内側主体に巡っていた「気」が、春になると外側へと強い勢いで巡り始めます。この巡りの主体が変わるタイミングで、もともと気の滞りがある方は様々な症状が表れやすくなります。
特に、この方のように潤いの不足がある状態で気が滞っていると、春の勢いの強い状態で気の動きが盛んに煽られるため、熱や乾きの症状が悪化しやすくなるのです。
これが春になると適応障害の症状やその他の不調が強まる理由の一つと考えられます。
この方の体質の特徴は?
BMIの数値から痩せ型であることがわかります。また、以下のような特徴から、全体的に乾燥体質だと考えられます:
- 皮膚や髪の毛の乾燥
- 目が疲れやすく乾きやすい
- 不眠になりやすい
体の上部には乾きの症状が目立ち、以下のような気の滞りを示す症状も見られます:
- 胸が張って苦しい
- ゲップやガスが出ると楽になる
- 吐き気を感じる
また、顔色が白っぽく、BMIや皮膚の状態から全体的に乾燥していることがうかがえます。月経周期と月経血の量が正常であるため、かえって血や潤いが不足していく可能性があります。
さらに、以下の症状から「動きの悪い水分が停滞している」状態も見受けられます:
- 口が粘る
- 頭が重く感じられることが多い
- 舌の形が厚い
- 舌苔の上の水分が水っぽい
- 自然に汗が出る
手足の冷えや立ちくらみからは、気血を巡らせる力の不足も推測されます。これにより:
- 気血が上に持ち上げられないことで脳貧血になりやすい
- 末端部まで気血が広がらないためにあかぎれが生じる
また、気の滞り、持ち上げる力の不足、血や潤いの不足によって、熱だけが上昇してしまうため舌の赤みが強くなり、脳が穏やかになれないために不眠や不安感などの症状が現れているのでしょう。
ではこの方に、おススメの自然療法を教えて下さい
この方の体質の特徴を踏まえると、気血を巡らせる力の不足が背景にあり、気の滞りや血・潤いの不足も見られます。そのため、以下の自然療法がおすすめです:
1. 適度な運動
食欲がなく多く食べられないとのことで、お腹の働きも少し弱っているように感じられます。「作る働き」を応援するためにも、運動不足かもしれないと心当たりがある場合は、近所を散歩するなど軽く汗ばむくらいの運動を取り入れてみましょう。
無理せず、気が向いたときに行うことが大切です。適度な運動は気血の巡りを良くし、代謝を上げる効果が期待できます。
2. 潤いを補う食生活
乾燥体質の改善には、適切な水分補給と潤いのある食材を取り入れることが効果的です:
- 根菜類や季節の野菜をたっぷり使ったスープ
- 良質なタンパク質(魚、豆類など)
- ナッツ類(アーモンド、クルミなど)
3. 乾燥対策
外的な乾燥から身を守ることも重要です:
- 保湿クリームやオイルでスキンケア
- 室内の適切な湿度管理(加湿器の活用)
- 入浴後すぐの保湿習慣
乾燥体質に効果が期待できる漢方薬
以下の漢方薬は、乾燥体質の改善に効果が期待できるものです。ただし、これらは特定の乾燥体質の改善に効果が期待できる一般的な漢方薬の紹介であり、この方に特定して合う漢方薬ではないことをご了承ください。
- 当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん): 血虚(けっきょ:血の不足)による冷え、むくみ、乾燥に効果的な漢方薬です。
- 六味地黄丸(ろくみじおうがん): 腎陰虚(じんいんきょ:腎の潤いの不足)による乾燥、のぼせ、不眠などに用いられます。
- 滋陰降火湯(じいんこうかとう): 潤いを補う事で不足による不安感、イライラ、のぼせなどに効果があります。
症状が複雑な場合には、単独の漢方薬では効果が見られないこともあります。当店では漢方相談も行っておりますので、お気軽にご相談ください。
まとめ
適応障害や春の不調に悩む乾燥体質の方には、気血を巡らせ、潤いを補う対策が効果的です。適度な運動や潤いのある食生活、適切な乾燥対策を取り入れることで、体質改善につながります。
体質は一朝一夕には変わりませんが、毎日の小さな積み重ねが大きな変化を生み出します。自分の体質を理解し、季節の変化に合わせたケアを心がけましょう。
YouTubeでも解説しています。

ご自分の体質にあった
漢方薬を試してみたい方は
ピヨの漢方の漢方相談を
ご利用ください。