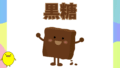こんにちは
どうなさいましたか?

不眠症にお悩みの方から
質問をいただきましたよ
睡眠の問題は現代人の多くが抱える悩みのひとつです。特に「寝つきが悪い」「夜中に何度も目が覚めてしまう」という症状に悩まされている方は少なくありません。
このような不眠の悩みは、単に眠れないというだけでなく、日中のパフォーマンス低下やストレス増加など、生活全体に大きな影響を与えます。西洋医学では薬に頼ることが多いですが、東洋医学には体質から原因を探り、自然な方法で改善していくアプローチがあります。
今回は、不眠でお悩みの56歳女性の体験談をもとに、東洋医学的な視点から不眠の原因と自然療法による対策をご紹介します。ご自身の症状と照らし合わせながら、ぜひ参考にしてみてください。
不眠に悩む患者さんの外見的な特徴とお悩みの症状
まずは患者さんの基本情報と外見的な特徴をご紹介します:
- 年齢:56歳
- 性別:女性
- 身長:159cm
- 体重:89kg
- BMI:35.2
外見的な特徴:
- 赤ら顔
- 皮膚の乾燥が目立つ
- 髪の毛は乾燥して細い
- 舌は厚ぼったく、色は白で部分的に紫色
- 舌には歯の跡があり、苔は剥れている部分がある
- 苔の上の水分は水っぽい
主な症状:
- 不眠症(特に寝つきが悪く、夜中に何度も目が覚める)
- 全身の倦怠感や無力感
- 身体のあちらこちらに痛み
- 肩こりがある
- 手足が冷えるが、のぼせることが多い
- 腹部の不快感や鈍痛
- 頭が重く感じることが多い
- 月経前に胸が張る
- 湿疹ができやすく、膿みやすい
- 耳鳴りがある
- 目が充血しやすい
なぜ不眠は起こるのか?東洋医学からの視点
睡眠に入るためには、身体の潤いによって興奮した脳が穏やかな状態に落ち着くことが必要です。
例えば、遠足前日の子どものように、明日大事なイベントがある場合、体も心も興奮して熱が盛んになると、脳の興奮が鎮まらず寝付けなくなります。このような場合は、体や心の緊張をほぐす必要があります。
また、お腹の働きが弱っていると、脳を穏やかにする潤い(血液)を作り出せなくなります。さらに、血液を運ぶ働き自体も緩んで低下するため、脳のある身体上部まで潤いを運び上げられなくなり、不眠につながります。
その他にも、脳へと潤いを届ける働きを何かが邪魔することで不眠が起こる場合もあります。例えば:
- お腹の働きが弱く、食べ物を上手く吸収・運搬できないと、お腹には余分な水分が停滞します
- ストレスなどで気の巡りが悪くなった状態でやけ食いすると、お腹の中でドロドロしたものが生じます
- これらが脳へ潤いを届けるのを邪魔すると、脳は穏やかになれず不眠となります
この患者さんの体質分析
身体上部の血の不足
この方の体質を分析すると、まず身体の上部に血の不足が見られます。以下の症状がその証拠です:
- 皮膚や髪の毛の乾燥
- 口唇の乾燥
- 不眠
- 夢を多く見る
- 不安感が強い
- 爪が脆い
- 目の疲れや乾燥
舌の色が白っぽいことも血の不足を示しています。
体内の余分な水分
一方で、以下の症状から体内には余分な水分が充満していることがわかります:
- BMI数値の高さ(35.2)
- 舌の苔の水分が水っぽい
- 舌に歯の跡がある
- ふくらはぎの浮腫み
- 動くと汗が出やすい
- 頭の重さ
気の滞りと巡りの悪さ
また、気血の巡りに滞りがあることも見て取れます:
- 舌の色に部分的な紫色
- 息切れしやすい
- 湿疹ができやすい・膿みやすい
- しびれを感じることが多い
- 身体のあちらこちらの痛み
- 月経前の胸の張り
- かゆみを感じることが多い
気の上向き過剰な流れ
さらに、気が上に向かって過剰に流れる傾向があります:
- 肩こり
- 手足が冷えるのにのぼせる
- 目の充血
- 耳鳴り
- 難聴
- 腰や膝の疲れや脱力感
- 腰痛
この方の不眠の原因まとめ
以上の分析から、この患者さんの不眠の原因は以下のようにまとめられます:
- 体内の余分な水分が充満している
- 気の滞りにより拡がりが悪くなっている
- 気が一方的に上昇する流れができている
- これにより熱や水分が巻き込まれ、のぼせや頭重感、湿疹などの症状が出ている
- 末端部の血液不足により、皮膚乾燥や髪の細さなどの症状が出ている
- 体の潤い不足により、体は熱を帯びやすくなり、気の巡りがさらに滞りやすくなっている
- これらの結果、脳と体の芯部にある潤いや熱源との相互の行き来が悪化し、寝つきが悪く、夜中に何度も目が覚める不眠症状につながっている
ではこの方に、おススメの自然療法を教えて下さい
1. 食事療法
体内の余分なものが充満している状態では、脳と体の芯部の相互の行き来が阻害されます。そこで、食事の量や内容を見直すことが重要です:
- 昔ながらの和食中心の食事を心がける
- 1口30回以上噛む習慣をつける
- 食事は腹八分目にとどめる
- 辛いもの・脂っこいもの・アルコールは控えめにする
特にアルコールは「お神酒」と呼ばれるように、東洋医学では「心は神を蔵す」といわれ、精神・意識活動を活発にして上方に昇らせる熱を強めます。もともと体に熱がこもりがちな方や乾燥しがちな方にとって、アルコールは不眠を悪化させることがあります。
2. 水分摂取の工夫
喉の渇きを感じてから水分を摂ると、必要以上に飲みすぎてしまう傾向があります。
- 一気に飲まず少量ずつこまめに飲む
- 少し飲んでから時間をおき、まだ喉が渇いていたら追加で飲む
3. 適度な運動
体に無理をかけない程度に体を動かすことで、滞りがちな気血の巡りを促進できます:
- 軽く汗ばむ程度の散歩
- ヨガや気功などの体操
- 家事や掃除など日常生活の中での活動
適度な疲労感は心の活動を穏やかにして、眠りにつきやすい状態へと導いてくれます。
4. 就寝前の習慣
- 寝る1時間前から部屋を暗くする
- スマホやテレビなど脳を興奮させるものを避ける
- ゆったりとした時間を過ごす
5. 眠れない時の対処法
どうしても眠れない場合:
- 布団の中で目を閉じる
- 吐く息を長めにした呼吸法を行う
- **足の裏の湧泉(ゆうせん)**に意識を向ける
これらの方法で脳の興奮が落ち着いてくることが期待できます。
この体質にお勧めの漢方薬
特定の体質改善に効果が期待できる漢方薬をいくつかご紹介します:
- 柴胡加竜骨牡蛎湯(さいこかりゅうこつぼれいとう):気の上昇を抑え、体の熱を鎮める効果が期待できます
- 酸棗仁湯(さんそうにんとう):不眠症に用いられる代表的な漢方薬で、心と肝の熱を冷まし、気の巡りを整えます
- 加味逍遙散(かみしょうようさん):気の巡りを整え、余分な熱を取り除き、血の不足を補う効果があります
ただし、これらは一般的な体質改善のための漢方薬であり、症状が複雑な場合には単独では効果がない場合もあります。ピヨの漢方では、個々の体質や症状に合わせた漢方相談も行っていますので、ぜひご相談ください。
まとめ:不眠症状の自然療法と体質改善
不眠症状、特に寝つきが悪く夜中に何度も目が覚めるタイプの不眠は、東洋医学的には体内の気・血・水のバランスの乱れに起因しています。
この方の場合は、体内の余分な水分、気の滞り、上方への熱の偏り、そして血液不足が複雑に絡み合って不眠を引き起こしていると考えられます。
自然療法としては、食事内容の見直し、適切な水分摂取、適度な運動、就寝前の過ごし方の工夫などが効果的です。特に、辛いものや脂っこいもの、アルコールなどの摂り過ぎに注意し、和食中心の腹八分目の食事を心がけることが重要です。
毎日の小さな習慣の積み重ねが、体質改善と質の高い睡眠につながります。焦らず、自分のペースで取り組んでみてくださいね。
YouTubeでも解説しています。

ご自分の体質にあった
漢方薬を試してみたい方は
ピヨの漢方の漢方相談を
ご利用ください。