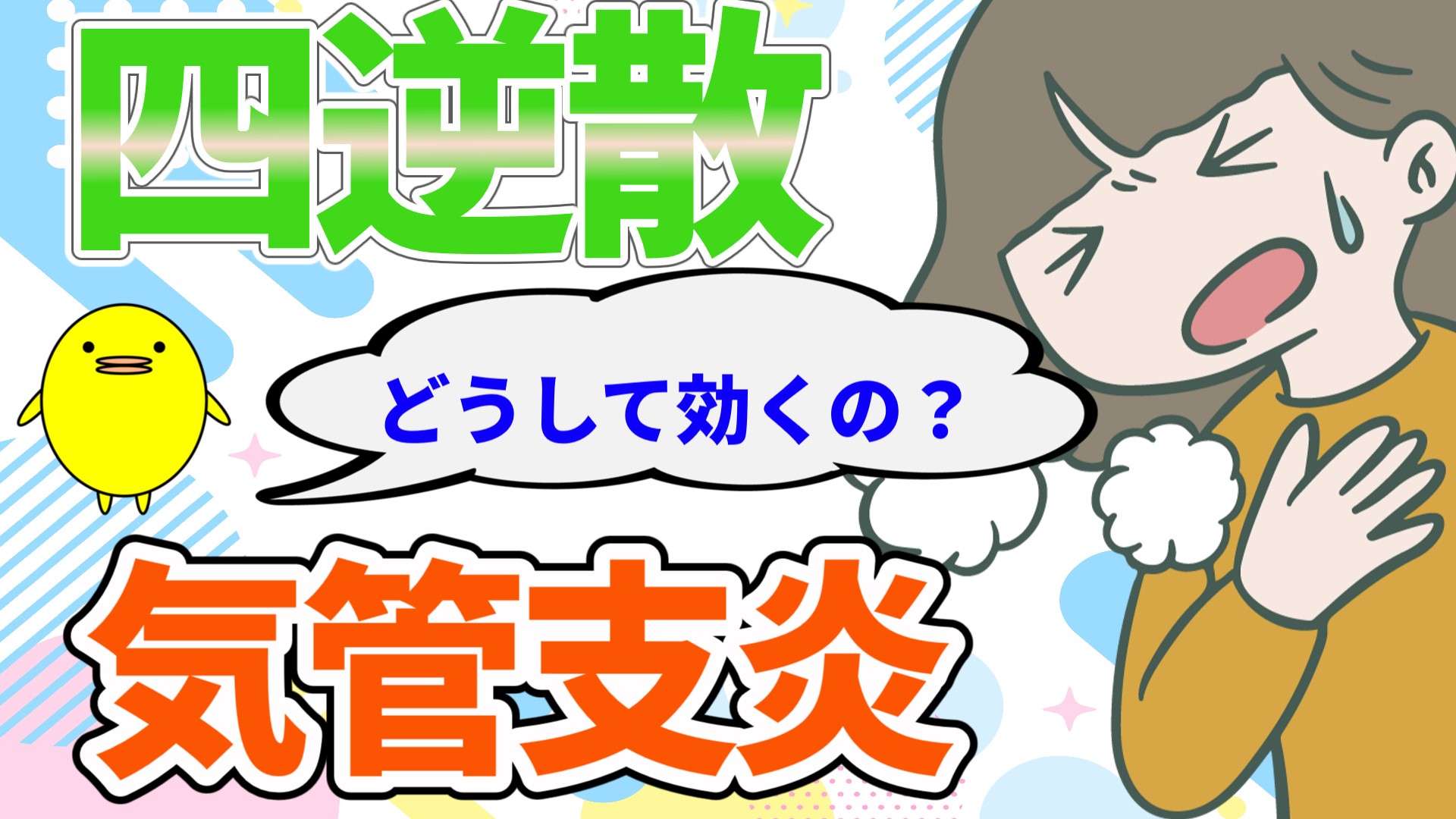こんにちは
どうなさいましたか?

四逆散と気管支炎について知りたい
という質問をいただきましたよ。
「なんだか最近、気分がすぐれない…」「咳や痰が長引いている…」そんな悩みを抱えていませんか?東洋医学では、このような症状は「気の滞り」が原因かもしれません。
今回は、気の巡りを改善し、様々な不調を和らげる漢方薬「四逆散(しぎゃくさん)」について詳しく解説します。ストレス社会に生きる現代人にとって、気の巡りを整えることはとても重要です。四逆散の働きを理解して、あなたの体調管理にお役立てください。
四逆散ってどんな漢方薬ですか?
四逆散は、気を動かしてくれる漢方薬です。東洋医学では「気」はエネルギーであり、生命活動を支える重要な要素と考えられています。この「気」の流れが滞ると、様々な不調が現れるのです。
四逆散は気の巡りを良くすることで、気管支炎の解消に効果を発揮します。また、気の滞りを解消する働きがあるため、以下のような症状の改善も期待できます:
- お腹の張り
- 食欲不振
- 手足の冷え
- ストレスによる不調
体内の気がスムーズに流れるようになると、これらの症状が自然と和らいでいくのです。
気管支炎と気の滞りはどう関係していますか?
気管支炎は、空気の通り道である気管支で炎症が起きるため、咳や痰などの症状が現れます。急性の気管支炎の原因の多くはウイルスや細菌の感染ですが、慢性気管支炎は感染の他にタバコなどの生活習慣が気管支への刺激となって炎症が続きます。
東洋医学の観点からみると、気管支炎と気の滞りには深い関連があります:
- 気の逆流と咳の関係:気が滞っていると、行き場を失った気が逆流することで咳となって表れます。
- 水と気の関係:水は気によって導かれて体内を巡っています。気の滞りがあると水の処理がうまく進まず、気管支周辺に余分な水が停滞します。
- 痰の形成メカニズム:エネルギーである気が滞ることで熱が生じ、その熱が停滞した水を煮詰めてドロドロした痰になります。
このように、気の滞りは気管支炎の症状を悪化させる要因となるのです。
四逆散の働きはどのようなものですか?
四逆散の気を解放する働きが、気管支炎の症状を解消してくれます。具体的には以下のような働きがあります:
- 柴胡(さいこ)の働き:四逆散に含まれる柴胡が、こもって滞っている気を解放して巡りをつけてくれます。
- 枳実(きじつ)の作用:巡り出した気を枳実が下向きに引き降ろすことで、気の上下の巡りを回復させます。
- 芍薬(しゃくやく)の役割:こもって過剰になっている気は芍薬が潤いを補うことで穏やかになだめてくれます。また、滞った水も芍薬によって下向きに運ばれていきます。
これらの生薬の働きにより、気は順調に巡りだすので、行き場を失って逆流することで生じていた咳は解消されます。また、水の巡りも気の巡りが整うことで順調になり、停滞していた水が処理されるので痰の解消にもつながります。
特にストレスを感じやすい方や、気が滞ることで気管支炎の症状が起きやすい方には効果が期待できる漢方薬と言えるでしょう。
使う際の注意点
四逆散は多くの方に効果が期待できる漢方薬ですが、使用する際にはいくつか注意点があります:
- 乾燥傾向の方への注意:潤す作用があるとはいっても、乾かす作用が主体になりますので、過労や寝不足などで特に表層において乾きの症状がある方の場合には、乾きをさらに煽ってしまう可能性があります。
- 対処法:このような場合は、次のような対応が考えられます:
- 潤いを補う漢方薬を組み合わせる
- 穏やかに気を巡らせる別の漢方薬に変える
- 個人差がある:症状が複雑な場合には、単独では効果が現れにくいこともあります。
- 専門家への相談:自己判断だけでなく、当店での漢方相談をご利用いただくことで、あなたの体質や症状に合った漢方薬を選ぶことができます。
まとめ
四逆散は、気の巡りを良くすることで、気管支炎の咳や痰、お腹の張りや冷えなどの症状を改善する漢方薬です。柴胡、枳実、芍薬などの生薬がバランスよく配合されており、特にストレスを感じやすい方や気の滞りが原因の不調に効果が期待できます。
ただし、乾燥傾向の強い方は注意が必要ですし、症状が複雑な場合には、単独では効果が現れにくいこともあります。そのような場合は、当店の漢方相談をご利用いただき、あなたの体質や症状に合った漢方薬を見つけましょう。
YouTubeでも解説しています。

ご自分の体質にあった
漢方薬を試してみたい方は
ピヨの漢方の漢方相談を
ご利用ください。