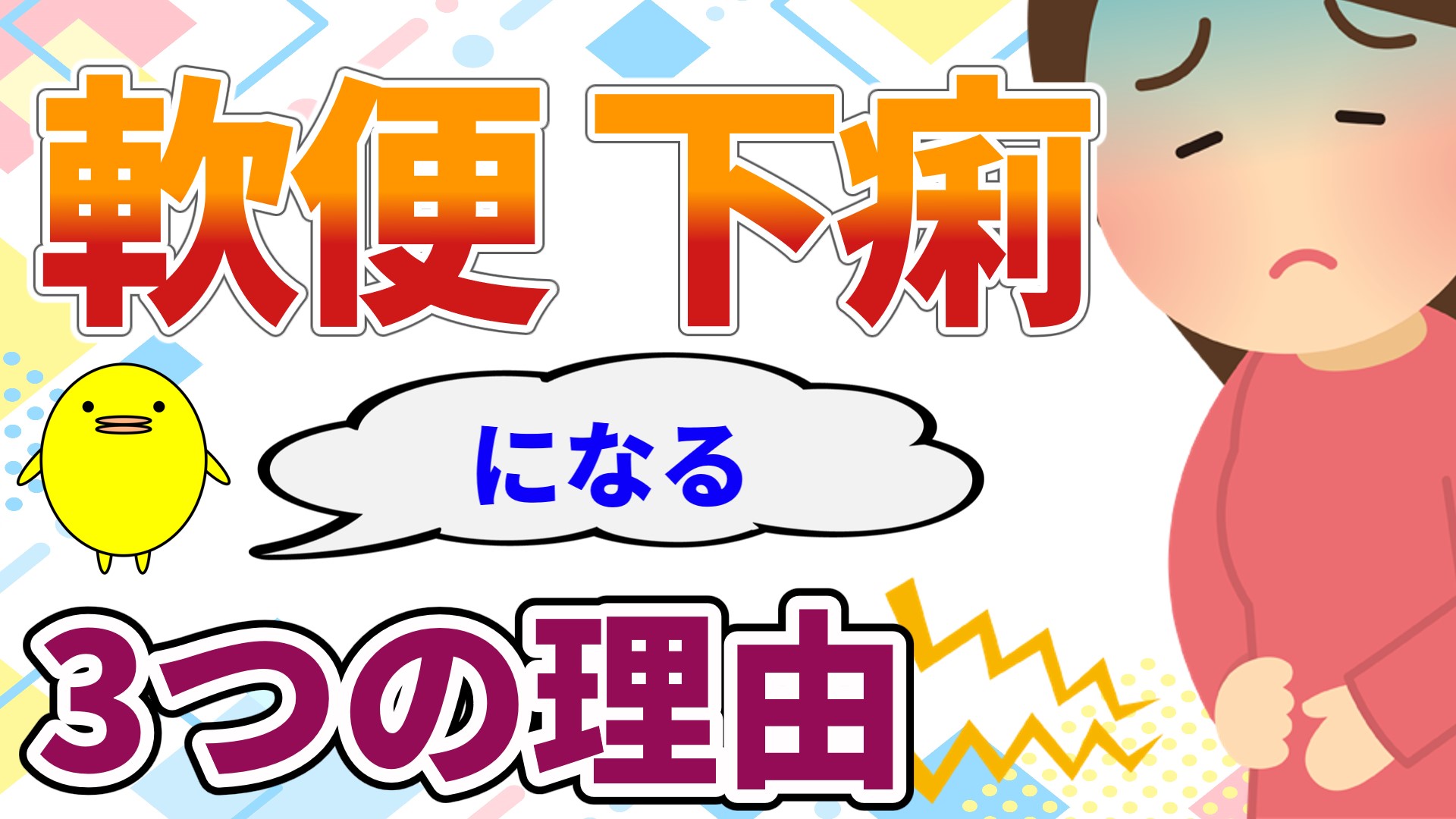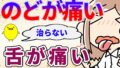「汁物など水分の多い食べ物を摂ると軟便になる」という悩みを抱えている方は少なくありません。健康な状態であれば、水分が多い食事でも体はきちんと吸収して正常な便を形成するはずです。しかし、体の状態によっては、水分の多い食事が軟便の原因となることがあります。
今回は、なぜ汁物などで軟便になるのか、その原因と改善方法について漢方の観点から詳しく解説していきます。お腹の調子を整えて快適な毎日を送るための参考にしてみてください。
異常がなくても軟便になるのか?
健康な状態であれば、汁物など水分の多い食べ物を摂っても軟便になることはありません。お腹の吸収機能に問題がなければ、体内で適切に水分が吸収され、正常な便が形成されるのです。
軟便が続く場合は、何らかの形で消化吸収システムに異常が生じている可能性があります。一時的なものから慢性的な問題まで、様々な要因が考えられますので、継続する場合は注意が必要ですね。
軟便になる理由にはどのようなものがあるのか?
軟便になる理由はいくつかあります。漢方の観点から見た主な原因をご紹介します。
- 食べ過ぎ・飲み過ぎによる吸収拒否
- 体が十分な栄養や水分を吸収済みの場合、余分なものを吸収しないよう軟便で排出します
- 栄養運搬力の低下
- 吸収した栄養を体内に運ぶ力が弱まり、「渋滞」が起こって新たな吸収ができなくなります
- 肝気の異常による栄養運搬の停滞
- 栄養を運ぶ役割を持つ「肝気(かんき)」が乱れると、吸収したものが適切に運ばれません
- 腸の蠕動運動(ぜんどううんどう)の過剰亢進
- 肝気の異常により腸の動きが過剰になると、食べ物が吸収される前に通過してしまいます
これらの要因が単独または複合的に作用して、水分の多い食事を摂った際に軟便が生じやすくなるのです。
どうしたら改善できるのか?
食べ過ぎ・飲み過ぎが原因の場合
食べ過ぎや飲み過ぎが原因の場合は、適切な量を守ることが基本です。
- 空腹感を感じてから食事をする
- のどの渇きを感じてから水分を摂る
- 満腹感を感じる前に食事を終える
体の声に耳を傾けながら、適量を心がけることが大切ですよ。
体の冷えが原因の場合
体の冷えによって栄養の運搬力が低下している場合は、体を温め、お腹の働きを高めることが重要です。
おすすめの漢方薬(体を温めてお腹の働きを高めるもの):
- 人参湯(にんじんとう) – 体を温め、消化吸収力を高める効果があります
- 附子理中湯(ぶしりちゅうとう) – 冷えによる消化器症状に効果的です
- 真武湯(しんぶとう) – 冷えによる水分代謝異常に効果があります
※これらは特定の体質の改善に効果が期待できる漢方薬の例です。症状が複雑な場合、単独では効果が見られないこともあります。当店では個人に合わせた漢方相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。
生活習慣の改善点:
- 適度な運動で体を温める
- 腹部を冷やさないよう注意する
- 温かい飲み物を選ぶ
肝気の乱れが原因の場合
肝気の巡りが乱れている場合は、肝気を整えることが重要です。
おすすめの漢方薬(肝気の巡りを整えるもの):
- 抑肝散加陳皮半夏(よくかんさんかちんぴはんげ) – 気血の巡りを整え、精神的な緊張も和らげます
- 加味逍遙散(かみしょうようさん) – 肝気の鬱滞を改善し、自律神経のバランスを整えます
- 香蘇散(こうそさん) – 気の巡りを良くし、消化機能を高めます
※これらは肝気の乱れに対応する漢方薬の例です。個人の体質や症状によって最適な処方は異なります。専門家による診断をお勧めします。
生活習慣の改善点:
- 歯を噛みしめていないか意識する
- お腹に力みが入っていないか確認する
- 気づいたら意識的に体の力を抜く習慣をつける
- ストレスを溜めないよう工夫する
まとめ
汁物などの水分の多い食べ物で軟便になる原因には、食べ過ぎ・飲み過ぎ、体の冷え、肝気の乱れなど様々な要因があります。健康な状態であれば水分が多い食事でも適切に吸収されるはずですが、体のバランスが崩れると軟便として排出されてしまうのです。
改善するためには、食事量の調整、体を温める工夫、肝気の巡りを良くする意識など、原因に合わせたアプローチが重要です。漢方薬も体質改善の強い味方になりますが、個人の状態に合わせた選択が必要です。
日常生活の小さな習慣改善から始めて、お腹の調子を整えていきましょう。継続的な軟便でお悩みの方は、専門家への相談も検討してみてくださいね。
YouTubeでも解説しています。

ご自分の体質にあった
漢方薬を試してみたい方は
ピヨの漢方の漢方相談を
ご利用ください。