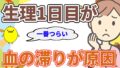こんにちは
どうなさいましたか?

胃もたれにお悩みの方から
質問をいただきましたよ
「食べた後、夜までずっとお腹が張っている」「少ししか食べられなくなった」「食後の胃もたれや吐き気がつらい」
こんなお悩みを抱えていませんか?
食欲不振や胃もたれが続くと、栄養が十分に摂れず、体力も落ちて日常生活にも影響が出てしまいますよね。
実は、こうした症状の背景には、お腹の働きの低下が関わっていることが多いのです。
今回は、食後の胃もたれや食欲不振の原因を中医学の視点から解説し、これらの症状に用いられる漢方薬「六君子湯(りっくんしとう)」について詳しくご紹介します。
どうして食欲不振になるのですか?
食欲不振の原因は、お腹の働きに不具合が起こっていることにあります。
食べた物は口から入り、胃で細かく分解されてから腸へ送られます。そして腸で必要な栄養を吸収し、全身に配られていくのです。
胃気と脾気のバランス
中医学では、この一連の働きを次のように考えます。
胃気(いき):食べ物を受け入れ、分解し、下向きに運ぶ働き
脾気(ひき):栄養を吸収し、上向きに運んで全身に配る働き
この2つがバランスよく働くことで、食べた物は適切に処理され、栄養は全身を巡り、不要なものは排出されます。
お腹の働きが低下する原因
ところが、次のような状況が続くと、胃気も脾気も働きが低下してしまいます。
- 冷たいものや生ものの食べ過ぎ:お腹が冷えて働きが弱まる
- 脂っこいものの食べ過ぎ:余分な熱が胃の潤いを消耗させる
- 甘いものの食べ過ぎ:お腹の中でドロドロした状態になり動きが悪くなる
- 考えすぎ、思い悩み:気が滞り、消化機能に影響する
- イライラやストレス:筋肉が緊張し、胃腸の動きが悪くなる
冷えによる影響
冷たいものや生ものを食べ過ぎると、お腹が冷えて脾気や胃気の働きが弱まります。
食べ物の処理が進まないだけでなく、お腹の痛みも生じます。この痛みは、冷えによって気や血液の流れが悪くなることで起きるため、温めたり揉んだりすると軽くなる特徴があります。
熱や湿による影響
脂っこいものを食べ過ぎると、お腹の中で余分な熱が生じます。
この熱が胃の潤いを消耗させ、胃気の働きが低下して食べ物を分解できなくなるのです。
甘いものを食べ過ぎると、水飴のように粘っこいドロドロした状態になります。脾気の運ぶ働きに負担がかかり、吸収した栄養を上向きに運べなくなってしまいます。
全身への影響
お腹の働きが弱ると、必要な気や血液を作れなくなります。
その結果、次のような症状が現れます。
- 体が痩せて顔色が悪くなる
- 冷えやすくなる
- 全身がだるくなる
- 疲れやすくなる
- 空腹感を感じなくなる
お腹は体の中心部にあり、全身の気血の流れの要となっています。ですので、お腹で停滞が起きると、身体全体の巡りが悪くなってしまうのです。
体は少ないエネルギーで何とかしようとして活動レベルを下げるため、エネルギー摂取の要求も少なくなり、空腹感を感じにくくなります。
ストレスの影響
考えすぎや思い悩み、イライラやストレスがあると、気が滞り、筋肉が強く緊張します。
すると、胃気や脾気の働きに影響が出て、食べた物や栄養を上手く運べなくなるのです。食べた物がお腹の中に停滞し、お腹が張って食欲がなくなります。
特に、お腹の働きが弱っていると、少しの気の滞りでも大きな影響を受けやすくなります。
六君子湯はどんな漢方薬ですか?
六君子湯は、8種類の生薬で構成される漢方薬です。
お腹の働きを高めて気を補い、停滞している気や水を巡らせてくれます。
六君子湯に使われている生薬
- 人参(にんじん): お腹の働きをパワーアップして気を補う
- 白朮(びゃくじゅつ): 余分な水分を取り除きお腹を整える
- 茯苓(ぶくりょう): 余分な水分を排出してお腹の働きを助ける
- 生姜(しょうきょう): お腹を温めて動きを良くする
- 大棗(たいそう): 気や潤いを補って栄養を与える
- 甘草(かんぞう): 気を補い、他の生薬の働きを調和させる
- 陳皮(ちんぴ): 気の巡りを良くしてお腹の張りを解消する
- 半夏(はんげ): 停滞を解消して吐き気を抑える
これらの生薬が協力し合って、弱ったお腹の働きを回復させてくれるのです。
どうして胃もたれが良くなるのですか?
六君子湯の8種類の生薬は、それぞれが役割を持って働きます。
お腹の働きを高める
人参、白朮、茯苓がお腹の働きを高めます。
人参は、お腹の働きをパワーアップして、消化吸収機能や新陳代謝を高めます。食欲を増進し、体に必要な栄養の合成機能を向上させることで、強力に気のエネルギーを補充してくれます。
白朮、茯苓は、停滞している余分な水分を巡らせて排除します。お腹の中に余分なものが停滞しないよう土台を整えることで、脾気・胃気のパワー不足によって体の中に停滞してしまった余分な水分が動き出すようになります。
気や水を動かす
生姜、大棗、甘草がお腹の中の気や水を動かします。
生姜は、お腹を温めながら、停滞している気や水をやや発散させるように動かします。腸管を下向きに引き降ろすことも応援してくれるのです。
しかも、生姜は胃液の分泌を増加させ、胃腸の蠕動運動を高めてくれます。消化機能が高まって、食欲が回復するというわけですね。
大棗、甘草は、綺麗な潤いと気の材料を提供します。お腹の働きを高めることで、これらの働きを支えてくれるのです。
生姜、大棗、甘草の組み合わせでは、大棗・甘草によって補充した体の潤いを、生姜の消化機能を高める働きによって上手に利用できるようになります。気や潤いの補充が進み、体の中心部の巡りもさらに良くなるのです。
停滞を解消する
陳皮、半夏がお腹の中の停滞を解消します。
陳皮、半夏は、お腹の中に停滞しているドロドロしたものを温めながら動かします。固まっている状態を砕いて下向きに引き降ろすことで、排除してくれるのです。
また、陳皮・半夏には気を下向きに引き降ろす働きもあります。気の滞りによってお腹が張って痞えている状態を解消してくれます。
全体の働きをまとめると
もう一度整理してみましょう。
- 人参でお腹の働きを高め、気を補充
- 白朮、茯苓で停滞している余分な水分を巡らせて排除
- 生姜で腸管の蠕動運動などを促進
- 大棗、甘草で気や潤いの材料を補充
- 陳皮、半夏でお腹の中に停滞している気や水を下向きに引き降ろす
こうして、弱ってしまったお腹の働きが回復し、邪魔なものが排除され、新陳代謝が上昇して活動レベルが高くなります。
その結果、心地よい空腹感を感じられるようになるのです。
どんなタイプの人に向いている?体質別おすすめコメント
六君子湯は、次のようなタイプの方に特に向いています。
お腹の働きが弱っている方
元々胃腸が弱く、少し食べるとすぐお腹が張ってしまう方、疲れやすく体力がない方に適しています。
食後の不快感が続く方
食後から夜まで満腹感が続く、胃もたれや吐き気がある、少ししか食べられなくなった方におすすめです。
ストレスの影響を受けやすい方
考えすぎや思い悩み、ストレスによってお腹の調子が悪くなる方にも向いています。
まとめ
今回は、食後の胃もたれや食欲不振と、六君子湯についてお話ししました。
お伝えしましたように、食欲不振になってしまう原因には、食事の不摂生やストレスが関わっています。
日常生活でできること
食欲不振にお悩みの方は、次のことを試してみてください。
- 空腹感を感じてから食べるようにする
- 食べる場合でも腹八分目にしておく
- よく噛んで食べるようにする
- 体力の状態に合わせて適度に運動する
運動は、気の滞りやストレスの解消になります。体の活動レベルが上がっていくと、自然に体がエネルギー摂取を要求してくる状態に変わっていくはずです。
ぜひお試しください。
症状が複雑な場合や、単独では効果が実感できない場合もあります。当店では漢方相談を行っておりますので、お気軽にご相談ください。
YouTubeでも解説しています。

ご自分の体質にあった
漢方薬を試してみたい方は
ピヨの漢方の漢方相談を
ご利用ください。