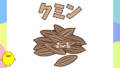こんにちは
どうなさいましたか?

肌荒れにお悩みの方から
質問をいただきましたよ
肌トラブルに悩まされていませんか?化粧品や外用薬を試しても改善しない肌荒れや痒みには、実は体の内側からのアプローチが必要かもしれません。
東洋医学では、肌の状態は内臓の健康状態を映す「鏡」と考えられています。つまり、体内の不調が肌トラブルとなって表れるのです。
今回は、なぜ肌が荒れたり痒くなったりするのか、東洋医学の視点から解説していきます。外側からのケアだけでなく、内側からケアすることの重要性について理解を深めていきましょう。
外見的な特徴とお悩みの症状
- 30代女性
- BMIは標準
- 顔色は黒ずみがち
- 髪の毛は乾燥、硬く多い
- 声は大きい
- 舌の色は白く、苔の上は水っぽい
- 舌の裏は細いが見える
- 足にむくみあり
主な症状:
- アトピー(仕事終わりや緊張時、ストレス時に悪化)
- 全身の倦怠感や無力感
- 手足の冷え、寒がり
- 食後の腹部膨満感
- 立ちくらみ
- あざができやすい、皮下出血しやすい
- 耳鳴り、腰痛
- 口の粘り
- 雨の日の体調不良
- 湿疹ができやすい・膿みやすい
- 痒みを頻繁に感じる
- 2〜3日に1回の硬い便秘
- げっぷやガスが出ると楽になる
- イライラ、怒りっぽい
- 不眠
- 皮膚の乾燥
- 夢をよく見る
- 強い不安感
- 物忘れ
- 筋肉の痙攣やつり
- 抜け毛
- 目の疲れや乾燥
- しびれ
- シミ・そばかす、皮膚の黒ずみ
- 肩こり
どうして肌は荒れて痒くなるの?
結論から言いますと、体の中を巡っている気や血液が正常に流れていないと、肌は荒れてしまいます。
東洋医学では、皮膚の色つやや張りの状態を見て、その人の内臓の健康状態を判断します。これは、皮膚が内臓の健康状態を映し出す「鏡」のような役割を果たしているからです。
当然、身体の調子が悪いと、皮膚の状態も悪化します。では、東洋医学では皮膚をどのように考えているのか、詳しく見ていきましょう。
皮膚の役割と構造について
皮膚には、いくつもの働きがありますが、最も重要な役割は、体の外側からやってくる様々な邪魔物を、体の内側に侵入させないためのバリアとしての働きです。
皮膚の最も外側にある角質層は、細胞核の抜かれた細胞が積み重なり壁のようになって体を守っています。この角質層には血液が流れていません。なぜなら、角質層に血液が流れていると、外側からの衝撃で傷ついた場合、血液の流れを通じて簡単に体の奥深くまで異物が侵入してしまうからです。
そのため、血液の流れていない角質層に栄養を与えるには、体の内側からの潤いが必要になります。
皮膚は深い部分にある基底層で分裂して作られた細胞が、順次表層へと押し出されて、表皮になって剥がれ落ちることで新しい皮膚に生まれ変わっていきます。この仕組みを「ターンオーバー」と言いますが、このターンオーバーは皮膚だけで勝手に行われているわけではありません。
身体の内側から血液の流れに乗って皮膚へと材料が届けられ、そして皮膚で代謝された不要物が体の内側へと回収されることで、皮膚は適度に新陳代謝が行われ、健康が保たれます。
しかし、皮膚に材料が届かなければ、皮膚は新しく作られなくなってボロボロになりますし、不要物が残ったままだと、皮膚はゴミ屋敷のように汚れがたまってしまいます。
これは災害で道路が寸断され、村落が孤立して食料も届けられず、住民も外に出られない状況に例えられます。同様に、体の内側と外側を結ぶ血液や栄養の流れが滞ると、肌は荒れてしまうのです。
痒みの原因は「滞り」
皮膚の症状の一つに痒みがありますが、東洋医学では、**痒みの原因は「滞り」**であると考えています。
私たちは痒いとどうするでしょうか?掻くことで解決しようとしますね。この「掻く」という行動は、滞った何かを動かして巡らせようとする行為なのです。
東洋医学の古典「此事難知」に「不通則痛・通則不痛」という言葉があります。これは、身体にとって必要な気や血液が通っていないから痛み、通っていれば痛まないという意味です。
この考えを押し広げると、全く通じなくなっていると痛みに、それより軽いけれど通じない場合にはしびれに、さらに軽くなると痒みになるとの考え方があります。つまり、滞りの程度によって、痛み、しびれ、痒みといった症状の違いが生じるのです。
滞りを引き起こす5つの原因
滞りを引き起こす原因は個々の状態で様々ですが、主に以下の5つに分けられます:
- 体の冷え
- お腹の働きの低下
- 食事の不摂生
- ストレスなどの精神的な影響
- 過労や夜更かし
それぞれ詳しく見ていきましょう。
1. 体の冷えが肌に与える影響
東洋医学では、体の芯部の熱である「腎陽」によって、体の中の潤いや水分が温められて軽くなることで巡っていると考えています。ちょうどお風呂の水が温められて循環しているような感じです。
お風呂の水が適量でも、火力が弱すぎると、上は熱くても下は冷たいままになります。これは火力不足により循環が弱くなっているからです。
同様に、人間の身体も冷えると循環する力が低下し、皮膚に必要な栄養が届きにくくなります。さらに、体の下が冷えて、役に立たない熱だけが皮膚に集まると、皮膚が乾燥したり痒くなったりします。
また、水の循環が悪いと皮膚の下に水が停滞し、必要な潤いを皮膚へ届けるのを阻害するため、皮膚の表面は乾燥しているのに、皮膚の下はむくんでいる状態になることもあります。
体の芯部の熱は身体の全ての機能の原動力ですので、ここが冷えると全身の機能が低下し、皮膚の健康維持が難しくなります。
2. お腹の働きの低下と肌の関係
食べたものは口から胃に入り、細かく分解されてから腸に送られます。お腹の吸収する働きによって、体に必要な材料が吸収され、それが「気」や「血」に作り変えられて全身へ配られます。
東洋医学では、食べ物を受け入れ分解し下向きに運ぶ働きを「胃気」、必要な材料を吸収して栄養に作り変え上向きに運び、肝気と共同で全身に配る働きを「脾気」と呼びます。
これら二つの働きが協調することで、食べ物は体の栄養となって全身を巡り、不要なものは体外へ排出されます。
しかし、お腹の働きが弱ると、皮膚を作るエネルギー源(気)や材料(血)が不足します。家の補修に例えると、気は職人、血は建材のようなものです。職人も建材も不足していれば家の補修ができないように、皮膚も十分に修復されずに肌荒れが起こります。
3. 食事の不摂生が肌に与える影響
食事内容も肌の健康に大きく影響します。
東洋医学では、脂っこいものの食べ過ぎはお腹に余分な熱を生じさせ、胃の潤いを消耗させます。その結果、胃気の働きが低下して食べ物の分解や運搬ができなくなります。
また、甘いものの食べ過ぎは、水飴のようにお腹の中でドロドロした状態を作り、脾気の運ぶ働きに負担をかけます。
冷たいものの摂り過ぎも胃腸の働きを邪魔します。これには喉の渇き以上に水分を飲みすぎることも含まれます。温度だけでなく、そのものの性質も関係しているため、体を冷やす性質のものは、熱い状態で摂取しても結局は体を冷やします。
お腹は体の中心部にあり、全身の気血の流れをリードしていますので、お腹で停滞が起きると身体全体の動きが滞ります。その結果、体のエネルギー不足と巡りの悪化によって、皮膚に必要な栄養が届かず肌荒れにつながります。
4. ストレスが肌に与える影響
お腹で作られた気や血は、芯部の熱で温められ、「肝気」によって全身へ届けられます。これは工場で作られた商品が運送業者によって世界中に届けられるようなものです。
ストレスにより気が滞ると、気血が溢れる場所と不足する場所が生じます。例えば、皮膚で気が余ると皮脂分泌が過剰になり、不足すると乾燥や栄養不足になります。
さらに、気はエネルギーなので、滞って集中すると体に役立たない熱が生じ、上向きに上昇する流れを作ります。この熱により皮膚が乾燥して痒くなったり、皮膚の常在菌のバランスが崩れたりします。
皮膚の常在菌は、多くの病原菌から体を守る重要な役割を果たしています。例えばニキビの原因となるアクネ菌も、正常な状態では肌を弱酸性に保ち、有害な菌の増殖を防いでいます。
しかし、気の滞りにより皮脂分泌が増えすぎたりターンオーバーが過剰になると、毛穴が詰まり、そこでアクネ菌が急増して炎症を起こしニキビになります。
常在菌のバランスを維持するには体内からの潤いが不可欠なので、気の滞りによって補給が乱れると肌荒れが目立つようになります。
5. 過労や夜更かしが肌に与える影響
過労や夜更かしが続くと、体全体の潤いの基となる「腎陰」が不足します。腎陰は自動車でいうと冷却水やガソリンのようなもので、これが不足すると体はオーバーヒート状態になります。
人間は、熱源である腎陽と潤いの基である腎陰がバランスを取れていると健康を保てます。しかし、過労や寝不足で腎陰が消耗すると、相対的に腎陽が過剰になり、体の熱を適切に冷ますことができなくなります。このタイプの方は皮膚の乾燥と共に火照りを感じることが多くなります。
また、腎陰は心の穏やかさを保つ役割もあるため、不足するとイライラしやすくなりストレスを感じやすくなります。
さらに、体のエネルギーである気は、腎陽が腎陰を活性化させることで作られます。過労や寝不足で腎陰が消耗すると「燃料の基」がなくなり、気が不足して疲れやすくなり、気血の巡りが悪くなります。
腎気は成長、骨、細胞、髪の毛、腰、脳などの働きも司っているため、弱ると老化が早まり、骨が脆くなったり、細胞が弱ってシワになるなど、皮膚状態も悪化します。
ではこの方に、おススメの自然療法を教えて下さい
今回ご紹介した方の症状から、冷え、余分な水の停滞、潤いの不足、気の滞りと気の逆流が見られます。
肌荒れの原因は人によって異なりますので、誰かが良いと言った方法が自分にも合うとは限りません。大切なのは、ご自身の体質を知り、それに合わせた対策を取ることです。
このような体質の方におすすめの自然療法としては:
- 腎陰を補うため早寝早起きの生活リズムを整える
- 温かい食べ物を適量取り、冷たいものや脂っこいもの、甘いものを控える
- 適度な運動で気の巡りを良くする
- ストレスを溜めない工夫をする(趣味や深呼吸など)
- お湯で足湯をして冷えを取る
肌荒れに効果が期待できる漢方薬
特定の体質改善に効果が期待できる漢方薬をいくつかご紹介します。ただし、これはあくまで一般的な情報であり、個人の症状に合わせた処方ではありません。
- 当帰芍薬散:血行不良と水の停滞による冷えや肌荒れに効果が期待できます。特に下半身の冷えやむくみを伴う方に適しています。
- 加味逍遙散:ストレスによる気の滞りから来る肌荒れ、イライラ、のぼせなどに用いられます。特に女性ホルモンのバランスの乱れを整える効果も期待できます。
- 六味丸:腎陰不足による内側からの乾燥、のぼせ、疲れやすさを改善します。特に疲労や夜更かしで消耗した方におすすめです。
症状が複雑な場合には、単独の漢方薬では効果が現れにくいこともあります。ピヨの漢方では、お一人おひとりの体質や症状に合わせた漢方相談を行っておりますので、お気軽にご相談ください。
まとめ
東洋医学から見た肌荒れの原因は、体内の気血の流れの滞りにあります。皮膚は内臓の健康状態を映す鏡であり、体の内側からのケアが大切です。
肌荒れの主な原因は:
- 体の冷え
- お腹の働きの低下
- 食事の不摂生
- ストレス
- 過労や夜更かし
特に重要なのは、早く眠ることです。肌を健康に保ちたいなら、今日から早寝を心がけましょう。自分の体質を知り、それに合わせた生活習慣の改善と必要に応じた漢方薬の活用で、肌荒れを根本から改善していきましょう。

ご自分の体質にあった
漢方薬を試してみたい方は
ピヨの漢方の漢方相談を
ご利用ください。