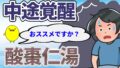こんにちは
どうなさいましたか?

喉の痞え感にお困りの方から質問をいただきましたよ。
「喉に何かが詰まっている感じがする」「食事をしても何かが引っかかる感覚がある」という不快な症状で悩んでいる方は少なくありません。特に胃カメラ検査で器質的な異常が見つからないにもかかわらず、症状が続く場合は対処法に困ってしまいますよね。
このような症状は西洋医学だけでなく、東洋医学の視点から見ることで新たな改善策が見つかることがあります。今回は、喉や食道のつかえ感に悩む方の実例をもとに、漢方医学的な観点からの原因と対策について詳しく解説していきます。
「胃カメラで異常なしなのに、なぜつかえ感があるの?」
胃カメラ検査で異常が見つからないにもかかわらず、喉や食道につかえ感がある場合、それは「機能的な問題」である可能性が高いです。つまり、器質的な異常(潰瘍や腫瘍など)ではなく、体の「動き」の問題と考えられます。
ゲップが多く、逆流性食道炎と診断されている場合、東洋医学では「上向きの気の勢いが強い状態」と捉えます。気(エネルギーの流れ)のバランスが崩れ、本来下に向かうべきエネルギーが上に向かっているのです。
胸を叩くとゲップが出て楽になるというのは、叩くことで「気の滞り(よどみ)」に巡りが付き、停滞していたガスが外へ出られるようになるためと考えられます。これは東洋医学的な視点からの理解です。
「なぜ六君子湯と半夏厚朴湯が効かなかったの?」
六君子湯や半夏厚朴湯が効果を示さなかった理由は、あなたの症状の根本的な原因と合っていなかった可能性があります。
それぞれの漢方薬の特徴を見てみましょう:
- 六君子湯: お腹の働きを応援して、気や水と共に腸管を下向きに動かす漢方薬。体力が低下して消化機能が弱った方に適しています。
- 半夏厚朴湯: 気の巡りを整えながら、余分な水も下向きに引き降ろす漢方薬。のどの異物感や不安感を和らげる効果があります。
一見、どちらも下向きの作用があるので良さそうに思えますが、実際には:
- 強い気の滞りがある場合には、これらの漢方薬単独では効果が出にくいことがあります
- 六君子湯は働きを応援する薬なので、気の力不足ではなく気の滞りが原因の場合、かえって滞りを強めてしまうことも
- どちらの漢方薬も水分を乾かす作用があり、潤いの不足によって気の滞りが強くなり、結果的に気の上昇が強まった可能性があります
「ではこの方に、おススメの自然療法を教えて下さい」
漢方薬のアプローチ
気の滞りを解消し、肝気(ストレスや緊張によって乱れる気)を鎮める漢方薬が効果的かもしれません。以下は気の滞りと上向きの気を改善する代表的な漢方薬です:
- 柴胡加竜骨牡蛎湯: 肝気の上昇を抑え、精神的な緊張を和らげる効果があります。胸脇苦満(みぞおちや脇の張り)がある方に向いています。
- 加味逍遙散: 肝気の滞りを解消しながら、潤いも補充するバランスの良い処方です。イライラや上半身のほてりがある方に適しています。
- 香蘇散: 気の巡りを良くして、胸腹部の不快感を和らげます。胸のつかえ感と精神的な緊張がある方に効果的です。
※これらは特定の体質の改善に効果が期待できる一般的な漢方薬の紹介です。症状が複雑な場合には、単独では効果がない場合もあります。当店では、あなたの体質や症状に合わせた漢方相談も行っておりますので、お気軽にご相談ください。
生活習慣の改善
- 適度な運動: 体を動かして気の巡りを良くしましょう。特に軽いウォーキングや深呼吸を伴うヨガなどがおすすめです。
- 食事の心がけ: 空腹感を感じてから、ゆっくりと良く噛んで食べることを意識しましょう。早食いは気の流れを乱す原因になります。
- セルフケア: ご自分の手で顎の周辺やお腹を気持ち良い程度の力でマッサージすると、緊張が緩みやすくなります。特に就寝前のリラックスタイムに取り入れてみてください。
- 睡眠の質を高める: 早めの就寝と十分な睡眠時間を確保しましょう。肝気の巡りを整えるには、質の良い睡眠が欠かせません。
まとめ
喉や食道のつかえ感は、西洋医学的に器質的な異常がなくても、東洋医学的には「気の流れの乱れ」として説明できる症状です。特に「上向きの気の勢い」が強く、「気の滞り」がある場合には、それに合わせたアプローチが必要になります。
漢方薬だけでなく、日常生活での心がけも大切です。適度な運動、ゆっくり食べる習慣、リラクゼーション、質の良い睡眠を意識することで、症状の改善につながることが期待できます。
気長に体質改善に取り組むことで、喉のつかえ感やゲップの症状が徐々に緩和されていくでしょう。ぜひ今日からできることから始めてみてくださいね。
YouTubeでも解説しています。

ご自分の体質にあった
漢方薬を試してみたい方は
ピヨの漢方の漢方相談を
ご利用ください。