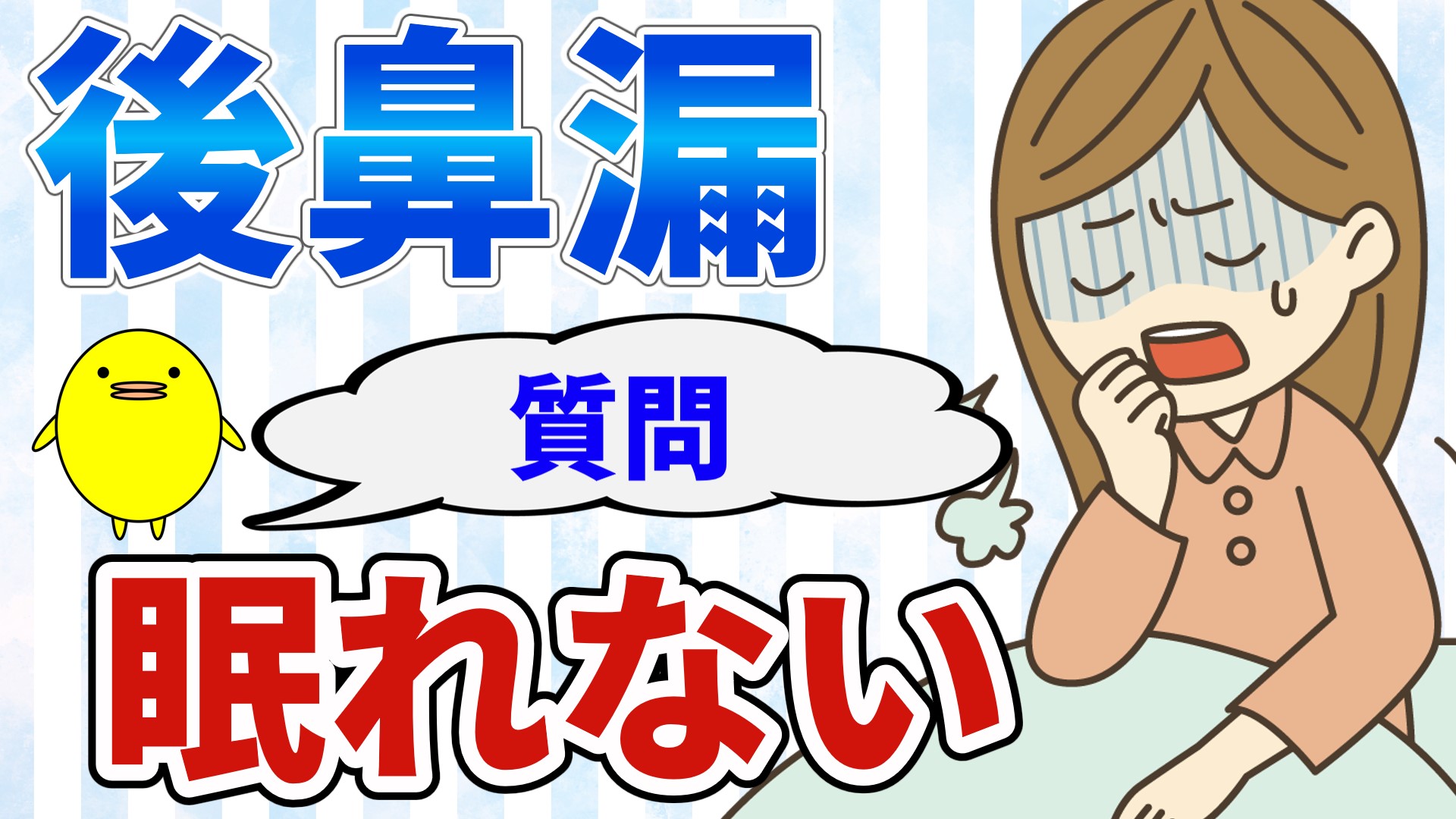こんにちは
どうなさいましたか?

鼻水からの咳にお困りの方から
質問をいただきましたよ。
のどの奥に鼻水が流れ落ちる「後鼻漏」。その不快な症状によって痰や咳が起こり、夜も眠れないとお悩みの方は少なくありません。「横になると咳が止まらない」「痰がからんで寝付けない」といった経験はありませんか?
実は東洋医学的な視点から見ると、後鼻漏には体質やライフスタイルが深く関わっています。本記事では、後鼻漏から始まる不快な症状の原因と、東洋医学に基づいた効果的な対処法をご紹介します。自然な方法で症状を和らげ、質の高い睡眠を取り戻しましょう。
後鼻漏とは何なのでしょうか?
後鼻漏とは、鼻の奥から喉へと鼻水が流れ落ちる症状を指します。この状態になると、のどに刺激を与えて咳や痰を引き起こすことがあります。特に横になった時に症状が悪化し、睡眠を妨げる要因となってしまうのです。
東洋医学から見る後鼻漏の原因は?
東洋医学では、後鼻漏の原因をいくつかの要素から考えます。主な原因としては以下が挙げられます:
- 鼻水の量が多くなる
- 鼻水の性質が粘っこくなる
- 体が冷えて水の巡りが悪くなる
- ストレスで余分な熱が生じ神経が過敏になる
これらの要因によって、本来なら気にならないはずの鼻水が喉へと流れ落ち、不快な症状として感じられるようになります。それぞれの原因について詳しく見ていきましょう。
なぜ鼻水の量が多くなるのですか?
鼻水の量が増えてしまう主な原因は、体内、特に鼻の周囲に余分な水分が停滞していることです。これは日常の生活習慣と深く関わっています。
例えば、本当にお腹が空いていなくても時間だからという理由で食事をとったり、喉が渇いていないのに習慣的に水分を摂取したりする生活を続けると、体の中に余分な水分が蓄積します。この余分な水分が鼻の周囲に停滞し、鼻水の量を増やす原因となるのです。
体が必要としている以上の水分や食事を取り続けることで、体内の水のバランスが崩れ、結果として後鼻漏の症状につながることがあります。自分の体が本当に必要としているタイミングで食事や水分を摂ることが大切ですね。
どうして鼻水が粘っこくなるのでしょうか?
鼻水が粘っこくなる原因は、主に過労や夜更かしなどの生活習慣と関連しています。十分な休息をとらずに体に負担をかけ続けると、二つの問題が生じます。
まず、体に必要な潤いが不足することで鼻水が粘り気を持ち始めます。また、十分な睡眠がとれていないと体を適切に冷やすことができず、相対的な熱が生じて鼻水を濃縮させてしまうのです。
この問題を解決するためには、規則正しい生活リズムを心がけ、十分な睡眠時間を確保することが重要です。また、辛い食べ物や飲み物は体に余分な熱を生じさせるため、控えめにするとよいでしょう。
体の冷えはどのように影響するのですか?
体が冷えると、全身の水分の巡りが悪くなります。特に鼻周囲の水分循環が滞ると、停滞している間に水分は粘り気を持ち始め、後鼻漏の原因となります。
この状態を改善するためには、適度な運動を取り入れて体を温めることが効果的です。また、冷たい飲み物や冷たい食べ物の摂取を控え、温かい食事や飲み物を選ぶよう心がけましょう。体を芯から温めることで、水分の巡りを良くすることができます。
ストレスはどのように後鼻漏に関係するのですか?
ストレスは東洋医学では「気の滞り」を引き起こすと考えられています。この気の滞りは体内に余分な熱を生じさせ、鼻水を粘っこくしたり神経を過敏にしたりします。
ストレスによって神経が過敏になると、通常なら気にならない程度の後鼻漏でも強く意識してしまい、症状が悪化したように感じることもあります。
改善のためには、散歩やストレッチなどの適度な運動を取り入れ、上手にストレスを発散させることが大切です。リラックスできる時間を意識的に作り、気の巡りを良くすることで症状の緩和が期待できます。
なお、これらの原因は単独で起こるだけでなく、複数の要因が組み合わさって症状を引き起こすこともあります。ご自身の生活習慣を振り返り、体質に合った改善策を少しずつ取り入れていくことが大切です。
ではこの方に、おススメの自然療法を教えて下さい
後鼻漏から痰と咳が出て眠れないという症状に対しては、以下の自然療法が効果的です:
- 就寝時の姿勢の工夫
- 少し高めの枕を使って、上半身を少し高くする
- 横向きに寝ることで、後鼻漏が喉に落ちにくくなる
- 部屋の湿度管理
- 適切な湿度(50〜60%程度)を保つ
- 乾燥しすぎると粘膜が刺激され、湿度が高すぎるとカビなどの原因に
- 就寝前の簡単なケア
- 鼻うがいで鼻腔内を清潔に保つ
- 軽い首や肩のストレッチでリラックス
- 食事の見直し
- 乳製品や小麦製品を一時的に控える(粘液を増やす可能性があるため)
- 温かい食事を中心に、生冷たいものは避ける
- 辛い刺激物は控える
これらの方法を組み合わせながら、ご自身に合った方法を見つけていくことが大切です。症状が長く続く場合は、専門家への相談も検討してみてください。
後鼻漏改善に効果が期待できる漢方薬
後鼻漏の症状改善に効果が期待できる漢方薬をいくつかご紹介します。ただし、これらは特定の体質改善に効果が期待できる一般的な漢方薬であり、個人の症状に合わせたものではありません。
- 小青竜湯(しょうせいりゅうとう):水っぽい鼻水や痰、くしゃみなどの症状に用いられる漢方薬。体が冷えて水分代謝が悪くなっている方に適しています。
- 辛夷清肺湯(しんいせいはいとう):鼻づまりや後鼻漏、蓄膿症などの症状に効果的。鼻から喉にかけての粘膜の炎症を鎮める働きがあります。
- 半夏厚朴湯(はんげこうぼくとう):のどに何かが詰まった感じ(咽喉頭異常感)や不安感がある方に。痰の絡みも改善します。
症状が複雑な場合には、単独の漢方薬では効果が現れないことがあります。当店では個人の体質や症状に合わせた漢方相談も行っておりますので、お気軽にご相談ください。
まとめ
後鼻漏からの痰と咳で眠れない症状は、東洋医学的な視点から見ると、体内の水分バランスの乱れや、体の冷え、ストレスなど様々な要因が絡み合っています。
日常生活では、必要な時に適切な量の食事と水分を摂ること、十分な睡眠をとること、体を冷やさないこと、そしてストレスを溜め込まないことを意識してみましょう。また、就寝時の姿勢の工夫や部屋の湿度管理なども効果的です。
症状が改善しない場合は、漢方相談を受けることで、あなたの体質に合った対策を見つけることができるかもしれません。少しずつ生活習慣を見直し、後鼻漏の症状を改善していきましょう。
YouTubeでも解説しています。

ご自分の体質にあった
漢方薬を試してみたい方は
ピヨの漢方の漢方相談を
ご利用ください。