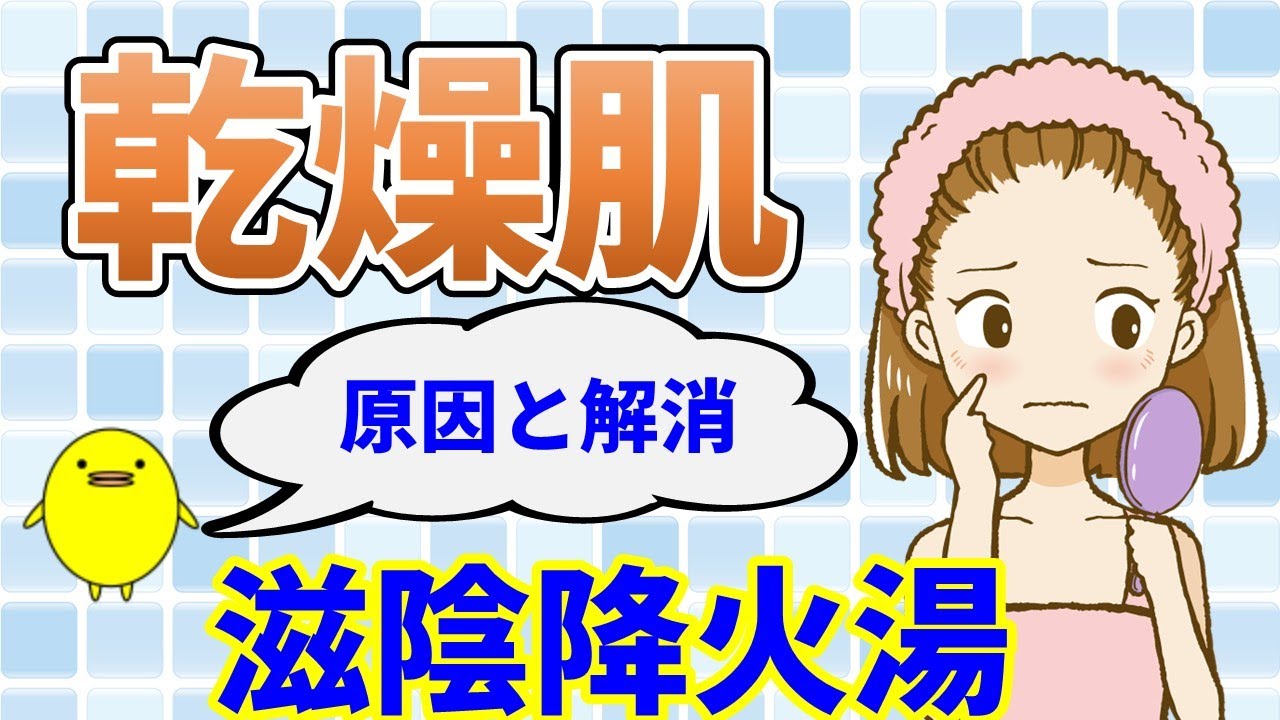こんにちは
どうなさいましたか?

乾燥肌にお悩みの方から
質問をいただきましたよ
冬の季節になると、外に出るたびに凍えそうな寒さを感じますね。
寒さだけでなく、空気の乾燥も気になる季節です。肌も唇もカサカサと粉を吹くように乾燥し、喉もイガイガして乾いた咳が出てしまう。クリームを塗ったり、加湿器で湿度を保とうとしても、なかなか良くならない…そんなお悩みを抱えている方は多いのではないでしょうか。
実は、乾燥肌は表面的なケアだけでは改善が難しいことがあります。中医学では、体の内側からの潤い不足が原因と考えるからです。
今回は、体の深い部分から潤いを補い、乾燥肌を改善する漢方薬「滋陰降火湯(じいんこうかとう)」について、詳しくお伝えしていきます。
どうして乾燥肌になってしまうのですか?
皮膚には、外部の刺激から体の内側を守るバリア機能があります。
このバリアとして働いているのが角質層です。角質層が正常な状態に保たれていると、角質細胞に含まれるアミノ酸やセラミドが肌の水分を適度に保持してくれます。こうして、体から必要な水分が蒸発するのを防いでいるのです。
皮膚は常に外部環境にさらされているため、誰でも乾燥する可能性があります。しかし、体が健康な状態であれば、体の内側から皮膚へと潤いが補充されるため、乾燥することはありません。
ところが、皮膚を乾燥から守っている潤いの供給が不足すると、たちまち乾燥が始まります。
皮膚は自分で潤いを作れない
皮膚自体は、健康な状態を保つために必要な潤いや栄養を作ることができません。また、皮膚の代謝で生じた不要物を処理することもできないのです。
そのため、皮膚が健康でいるには、潤いや栄養を作れる体の内側と、途切れることなく連携している必要があります。
この連携が途切れてしまうと、皮膚は孤立してしまいます。やがて角質層も壊れ、バリア機能が働かなくなって水分を保持できなくなってしまうのです。
潤いが不足する3つのパターン
皮膚へ供給する潤いが足りなくなる理由は、大きく3つに分けられます。
- 身体全体で潤いが不足する
- 作った潤いを皮膚まで届けることができない
- 皮膚へ潤いを届けるのを邪魔するものがある
今回ご紹介する滋陰降火湯は、特に**「身体全体で潤いが不足する」**タイプの乾燥肌に深く関わっています。
身体全体で潤いが不足すると、少ない水分を全身で分け合うことになります。当然、それぞれの部位へ配分される量は減りますので、皮膚でも不足するようになるのです。
しかも、体は全体として不足している場合、優先的に大切な働きのある中心部へ材料を配分しようとします。そのため、皮膚などの末端部へは届けられなくなり、ますます乾燥が強まってしまいます。
潤い不足には2つのタイプがある
身体全体で潤いが不足する場合でも、2つのパターンがあります。
1つは、潤いを作る機能が低下している場合です。体の働きが衰えて、潤いそのものを作れなくなっているタイプですね。
もう1つは、反対に体の活動が過剰になりすぎて、潤いを過度に消耗してしまう場合です。
例えば、過労や夜更かしなどが続くと、体の潤いを作るための基礎材料が消耗されてしまいます。潤いを作ろうにも材料が不足しているため、作ることができなくなってしまうのです。
このような場合、潤いには体を冷却する働きもあるため、不足すると体を適度に冷やせなくなります。その結果、皮膚の乾燥とともに、元気のない火照り、体温は高くないのに熱感、不眠などを感じることもあるのです。
滋陰降火湯はどんな漢方薬ですか?
滋陰降火湯は、10種類の生薬から構成されている漢方薬です。それぞれの生薬が協力し合って、体の潤いを回復させてくれます。
滋陰降火湯に使われている生薬は以下の通りです。
- 地黄(じおう): 体の深部に潤いを与える
- 天門冬(てんもんどう): 体の表面を潤す
- 麦門冬(ばくもんどう): 肺や喉を潤す
- 知母(ちも): 熱を冷まし潤いを補う
- 黄柏(おうばく): 熱を冷まし下へ導く
- 芍薬(しゃくやく): 筋肉の緊張を緩める
- 当帰(とうき): 血液を補い巡りを改善
- 白朮(びゃくじゅつ): 胃腸の働きを高める
- 陳皮(ちんぴ): 気の巡りを良くする
- 甘草(かんぞう): 諸薬を調和させる
どうして乾燥肌が良くなるのですか?
滋陰降火湯は、これら10種類の生薬の働きによって、潤いを補充して熱を冷まし、気や水分、血液の流れを応援することで、体の潤いを回復させてくれます。
では、それぞれの生薬がどのように働くのか、順を追って見ていきましょう。
体の深部から表面まで潤いを補充する
まず、地黄、天門冬、知母、芍薬、当帰、甘草で、体へ潤いの材料を補充します。
特に地黄、天門冬、知母は、体の深い部分へ潤いを提供します。これにより、体全体の潤いの基礎となる材料が補充されるのです。
そして、天門冬、麦門冬、知母は、皮膚を含めた体の表面部分を潤します。乾燥肌とともに、乾いた咳の解消にもつながる働きですね。
筋肉の緊張を緩めて巡りを改善する
地黄、芍薬、甘草には、筋肉の緊張を緩める働きがあります。筋肉の痙攣が緩むことで、気血の巡りが改善されます。
潤いを全身に届けるには、巡りの良さも大切なポイントです。
浮き上がった熱を冷まして落ち着かせる
知母、黄柏は熱を冷ましてくれる生薬です。
潤いが不足すると、体の冷却水の働きをする潤いが足りないため、勢いはないものの身体の上の方へ熱が浮き上がってしまいます。
知母で熱を冷ましながら潤いを補充し、黄柏で熱を冷ましながら尿から排出することで解消してくれるのです。
しかも、知母と黄柏には神経の興奮を鎮める作用もあります。過労が溜まっていて、何となく興奮して乾いたようになっている精神状態を、穏やかな状態に落ち着かせてくれます。
この熱を冷まし、興奮を鎮める働きには、天門冬、麦門冬、芍薬の利尿作用も加わっています。体の下の方へ水を引き込んでくる作用で、熱を下へ導いてくれるのです。
ちなみに、天門冬、当帰には通便作用もありますので、便秘の解消にも効果が期待できます。
血液の巡りを改善する
当帰と芍薬は、潤いが不足してドロドロと動きが悪くなっている血液の巡りを改善してくれます。同時に、血液の材料を補充することも助けてくれるのです。
血液は栄養や潤いを運ぶ重要な役割を持っていますから、その巡りが良くなることは、皮膚の健康回復に大きく貢献します。
胃腸への負担を防ぐ工夫
ここまでで、体の深い部分から皮膚などの表面まで潤いが補充されました。
しかし、地黄など潤いを補充する生薬には、粘っこくしつこい性質があります。お腹の弱い方の場合、負担となって停滞することがあるのです。
そのため、白朮、陳皮によって、お腹の中の水の動きを応援して巡らせます。これらの生薬には気を下向きに引き降ろす働きもあるので、潤いを補充する生薬がお腹に停滞することで起こるお腹の張りや、お腹の中で粘っこいドロドロした状態になるのを防いでくれます。
働きをまとめると
これらの働きをまとめますと、次のようになります。
- 地黄、天門冬、知母: 体の深い部分へ潤いを補充
- 天門冬、麦門冬、知母: 皮膚などの体の表層部分へ潤いを補充
- 当帰、芍薬: 血液の補充と血液の巡りを応援
- 知母、黄柏: 頭の方へ浮き上がった熱を引き降ろして興奮を鎮める
- 地黄、芍薬、甘草: 筋肉の痙攣を鎮める
- 白朮、陳皮: お腹の働きを応援して気や水の巡りを助ける
これによって、体の深い部分から表層へと潤いが補充され、浮き上がっていた熱が引き降ろされて冷やされます。
その結果、体が乾燥してしまったことによる皮膚の乾燥、乾いた咳、こもった火照りなどが解消されるのです。
どんなタイプの人に向いている?体質別おすすめコメント
滋陰降火湯は、特に以下のような体質の方におすすめです。
過労や夜更かしが続いている方に特に向いています。忙しい日々で体の潤いの基礎材料が消耗されてしまい、潤いを作れなくなっているタイプの方ですね。
乾燥肌とともに、元気のない火照りや体温は高くないのに熱感を感じる方、不眠気味の方にもおすすめです。これらは潤い不足によって体を適度に冷却できなくなっているサインです。
また、乾いた咳が出る方や便秘がちの方にも効果が期待できます。肺や腸管を潤すことで、これらの症状も改善されていきます。
ただし、注意点もあります。
滋陰降火湯に含まれる潤いを補充する生薬は、粘っこい性質があるため、胃腸が弱い方の場合は負担になることがあります。処方には胃腸を助ける生薬も配合されていますが、お腹の調子を見ながら服用することが大切です。
また、症状が複雑な場合には、滋陰降火湯単独では効果が十分でないこともあります。そのような時は、当店での漢方相談もご利用ください。お一人お一人の体質や症状に合わせて、最適な処方をご提案いたします。
まとめ
今回は、乾燥肌になる原因と、滋陰降火湯について解説いたしました。
乾燥肌になってしまう理由はいくつかありますが、最も大切なのは、皮膚の健康を保つための体の内側と皮膚との連携です。この連携が途切れてしまい、皮膚へ潤いが届けられなくなることが、乾燥肌の大きな原因なのです。
滋陰降火湯は、体の深い部分から表面まで潤いを補充し、浮き上がった熱を冷まして落ち着かせる働きがあります。乾燥によって起きる乾いた咳や便秘の解消にも、肺や腸管を潤すことで効果を発揮します。
ですが、どんなに優れた漢方薬でも、睡眠の代わりになるものはありません。
過労や夜更かしなどが原因で体の潤いが消耗され続けていると、どんなに薬で応援しようとも、焼け石に水となって効果が現れにくくなります。
肌荒れがなかなか改善しないとお悩みの方は、少しでも早めに眠ることを心がけると改善が早くなりますので、ぜひお試しください。
YouTubeでも解説しています。

ご自分の体質にあった
漢方薬を試してみたい方は
ピヨの漢方の漢方相談を
ご利用ください。