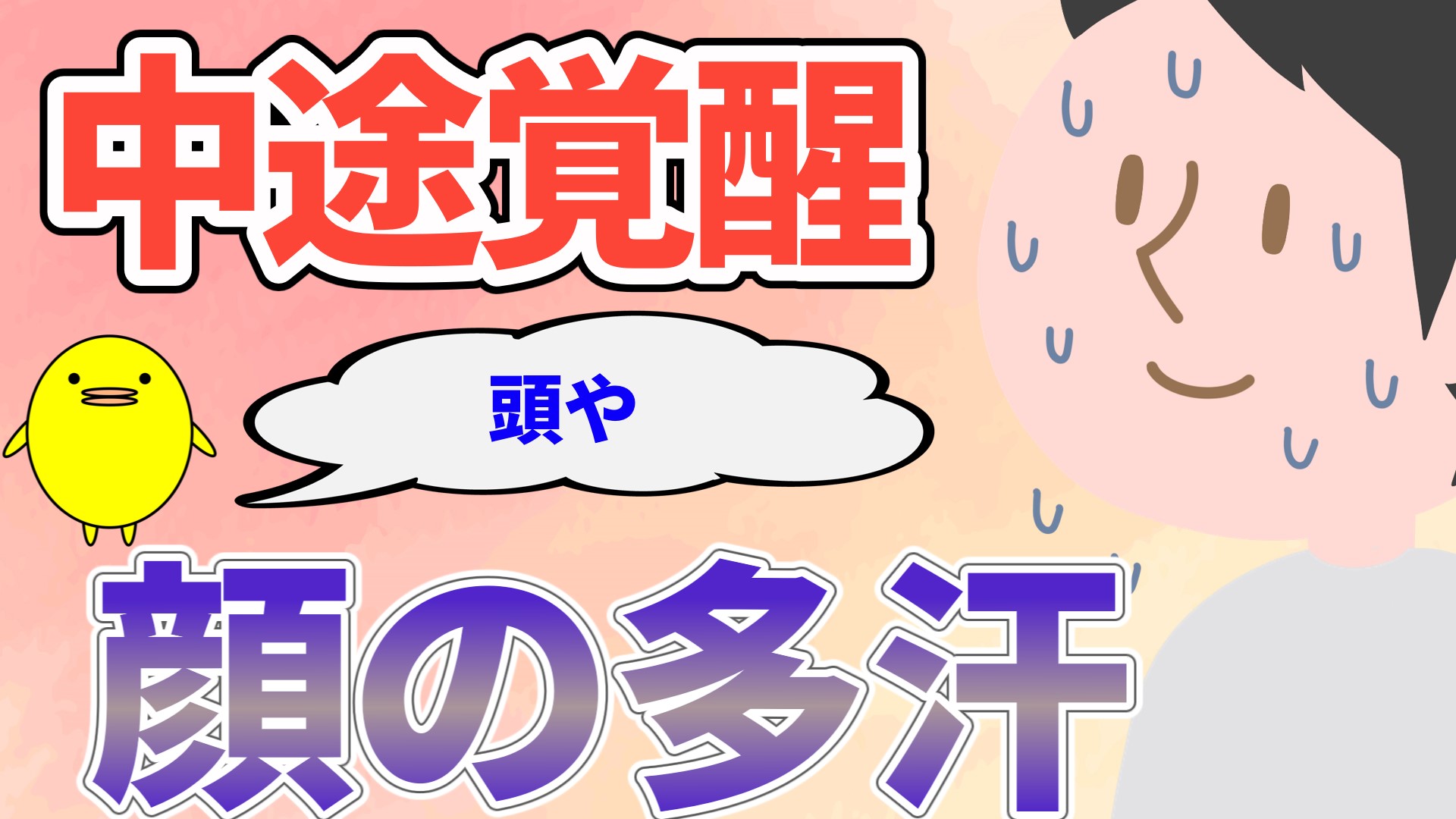こんにちは
どうなさいましたか?

顔からの汗にお困りの方から
質問をいただきましたよ。
多汗症でお悩みの方は少なくありません。特に顔や頭部からの異常な発汗は、日常生活に大きな影響を与えることがあります。「周りの人より汗が多い」「仕事中に顔から汗が止まらない」といった悩みを抱えていませんか?
今回は、建築関係のお仕事をされている方からの相談をもとに、顔と頭からの多汗症について東洋医学の視点から解説します。単なる体質や暑さだけが原因ではなく、心と体のバランスの乱れが関係している可能性があるのです。
この記事では、多汗症と不眠の関連性や、自然な方法での改善策についてもご紹介します。過剰な発汗に悩まされている方は、ぜひ参考にしてみてください。
顔と頭からの多汗症はなぜ起こる?
外見的な特徴とお悩みの症状
- 職業:建築関係
- 主な症状:
- 顔と頭から大量の汗が出る
- 同じ環境の周囲の人と比べても異常な量の汗
- 夜中に何度も起きる不眠症
このような症状が見られる場合、東洋医学では「心気の働きの異常」が疑われます。なぜでしょうか?
顔は「心の華」という東洋医学の考え方とは?
東洋医学では、**顔は「心の華」**と表現されます。ここでいう「華」とは、外から臓腑(内臓)の機能状態や様子が分かる場所を意味します。
心気は精神思惟活動を司る場所とされており、意識状態や睡眠などに深く関わっています。例えば、私たちの表情にすぐに気持ちが表れることからも分かるように、顔は精神状態を調整する中枢である心気の状態を表に出す場所なのです。
また、心気は睡眠の調整にも深く関わっています。心気が乱れると、質の良い睡眠が取れなくなり、不眠症状につながることがあるのです。
なぜ夜中に何度も目が覚めてしまうの?
夜中に何度も起きてしまう「中途覚醒」は、睡眠を維持する潤いの不足が原因かもしれません。東洋医学的には、身体の潤いが不足すると、体内の熱を穏やかに調整することができなくなります。
その結果、相対的な熱が生じ、心気の安定が保てなくなって中途覚醒を引き起こします。さらに、この相対的な熱が汗を押し出す「肝気」の力を強めてしまうことで、多汗症状につながると考えられるのです。
つまり、潤いの不足→体内の熱の不均衡→心気の乱れ→不眠と多汗という連鎖が起きている可能性があります。
ではこの方に、おススメの自然療法を教えて下さい
東洋医学的な視点から、心気の乱れと潤いの不足による多汗症と不眠に対しては、以下のような自然療法がおすすめです。
漢方薬による改善
以下は顔と頭からの多汗と不眠に関連する心気の乱れに効果が期待できる漢方薬です:
- 黄連解毒湯(おうれんげどくとう):体内の熱を冷まし、のぼせや発汗を抑える効果が期待できます
- 加味逍遙散(かみしょうようさん):肝気の乱れを整え、イライラや不眠を改善する働きがあります
- 酸棗仁湯(さんそうにんとう):潤いを補いながら、心を落ち着かせ、不眠を改善する効果があります
ただし、これらはあくまで一般的な心気の乱れや多汗症に効果が期待できる漢方薬であり、個人の体質や症状によって合う漢方薬は異なります。症状が複雑な場合には、単独では効果がない場合もありますので、当店での漢方相談をご利用いただくことをおすすめします。
生活習慣の改善
心気の乱れと気の巡りを整えるためには、生活習慣の見直しも大切です:
- 緊張をほぐす運動を取り入れる:ヨガや気功などのゆったりとした運動で、体の緊張感を緩めましょう
- 意識的な呼吸法を実践する:広場などで散歩をする際に、呼吸に意識を向けてみてください
- 頭の中の思考に気づいたら呼吸に戻る:考えが湧き上がってきたことに気づいたら、すぐに呼吸に意識を向け直しましょう
このような実践を続けることで、心気の働きが穏やかになり、顔や頭からの多汗や不眠症状が改善する可能性があります。
まとめ:心と体のバランスを整えて多汗症を改善しよう
顔や頭からの多汗症は、単なる体質だけでなく、東洋医学的には心気の乱れや体内の潤いの不足が原因となっていることがあります。特に不眠を伴う場合は、心と体のバランスが崩れているサインかもしれません。
漢方薬による内側からのアプローチと、呼吸を意識した運動や日々の実践による外側からのアプローチを組み合わせることで、徐々に症状の改善が期待できます。
あなたの体質に合った対策を見つけて、心地よい日常を取り戻しましょう。多汗症でお悩みの方は、ぜひ一度東洋医学的なアプローチを試してみてはいかがでしょうか。
YouTubeでも解説しています。

ご自分の体質にあった
漢方薬を試してみたい方は
ピヨの漢方の漢方相談を
ご利用ください。