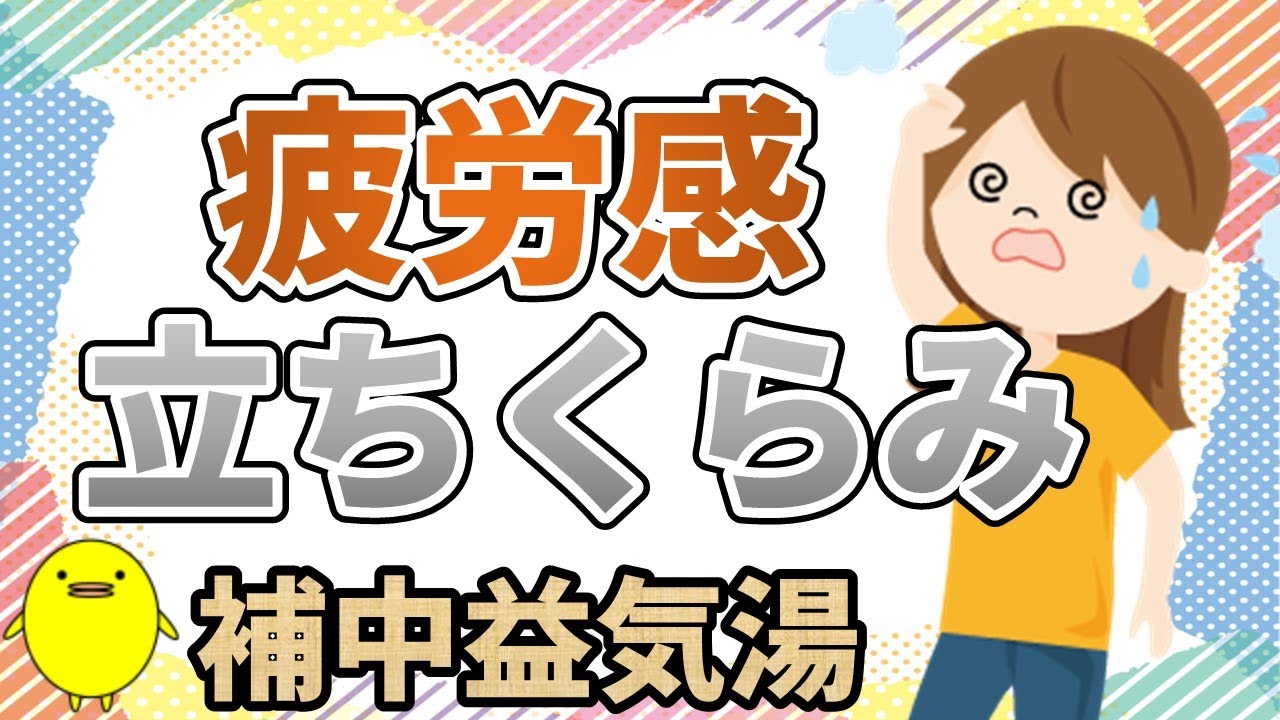こんにちは
どうなさいましたか?

立ちくらみにお悩みの方から
質問をいただきましたよ
疲れがなかなか取れない、食欲がわかない、立ち上がるとクラッとする…。こんな症状にお悩みではありませんか?
季節の変わり目や、忙しい日々が続くと、体は知らず知らずのうちに疲れを溜め込んでしまいます。特に胃腸が弱っていると、体のエネルギー源である「気(き)」が不足して、さまざまな不調が現れやすくなるんですね。
今回ご紹介する**補中益気湯(ほちゅうえっきとう)**は、お腹の働きを高めて気を補い、体の巡りを整えてくれる漢方薬です。疲労感や立ちくらみ、食欲不振などでお困りの方におすすめの処方となっています。
では、なぜ疲れが取れないのか、そして補中益気湯がどのように働くのか、詳しく見ていきましょう。
どうして疲れが取れないのですか?
気が不足すると疲れやすくなる
健康な状態では、「気」が体に十分にあり、全身をスムーズに巡っています。気とは、体を動かすエネルギーのようなものだと考えてください。
**お腹の働きが弱ってしまうと、この気が不足します。**さらに、気を運ぶ働きも低下するため、必要な場所に気が届かなくなり、疲れを感じやすくなるのです。
気はどうやって作られるの?
気を作るためには、食べ物と酸素が必要です。そのプロセスを見ていきましょう。
まず、食べ物が口から入ると、お腹の働きによって消化され、栄養が吸収されます。吸収された栄養は、体の中にある材料と融合して、気の原料となるものが出来上がります。
この段階では、まだエネルギーである気にはなっていません。食べ過ぎや飲み過ぎでお腹に負担をかけすぎると、かえって気を消耗してしまうんですね。
次に、気の原料は、お腹の働きによって体の上の方にある肺へと運び上げられます。肺に届いた気の原料が、呼吸によって取り込まれた酸素と結びつくことで、ようやく体のエネルギーである「気」になるのです。
お腹が弱ると何が起こる?
お腹の働きが弱ってしまうと、さまざまな問題が起こります。
- 食欲がなくなる: そもそも空腹感を感じなくなります
- 栄養不足になる: 無理して食べても消化吸収できず、下痢で排出されてしまいます
- 体に不要なものが溜まる: 気の原料にまで合成できないと、体に蓄積して他の機能を邪魔します
また、気の原料が肺まで運び上げられなくなると、体の下の方に充満してしまい、さまざまな悪影響を及ぼします。
立ちくらみが起こる理由
気の原料を運び上げる働きには、平滑筋(内臓や血管の壁にある筋肉)の適度な緊張が関係しています。
平滑筋が緊張していることで、血流に乗って気の原料が運び上げられ、内臓も正しい位置に留まっていられます。ところが、平滑筋が緩んでしまうと、材料が体の上へと運ばれなくなります。
すると、脳でエネルギー不足が起こり、めまいや立ちくらみが生じるのです。
さらに、肺にまで気が届かなくなると、呼吸も弱くなり、息切れを感じるようになります。気の原料があっても酸素と結びつけないため、疲れがさらに増すという悪循環に陥ってしまうんですね。
補中益気湯はどんな漢方薬ですか?
補中益気湯は、10種類の生薬で構成されています。それぞれの生薬が協力して、お腹の働きを高め、気を上向きに運び上げる働きをしてくれます。
補中益気湯に含まれる生薬
- 黄耆(おうぎ): 気を上に持ち上げる
- 人参(にんじん): 気を補う
- 白朮(びゃくじゅつ): お腹の働きを高める
- 甘草(かんぞう): 諸薬を調和させる
- 大棗(たいそう): 気を補う
- 生姜(しょうきょう): 消化を促す
- 柴胡(さいこ): 気を上昇させる
- 升麻(しょうま): 気を引き上げる
- 陳皮(ちんぴ): 気の巡りを整える
- 当帰(とうき): 血を補い巡らせる
これらの生薬が協力することで、お腹の働きを高め、気を補い、体の巡りを改善してくれるのです。
どうして疲れや立ちくらみが良くなるのですか?
補中益気湯の働きを、生薬のグループごとに見ていきましょう。
気を持ち上げる働き
まず、黄耆が、体の下の方に落ち込んで停滞している気を、盛り立てるようにして広げながら上の方へと届けます。
力なくこもっていた気が扇のように拡げられることで、肺にまで気が届き、呼吸や皮膚の状態も改善されます。
柴胡と升麻は、黄耆の働きを助けて、滞って下にこもっていた気を解放しながら上へと昇らせ、表層にまで到達させます。
気を補う働き
ただ広げるだけでは、気が量的に足りない場合、少ないものが余計に少なくなってしまいます。
そこで、人参、白朮、甘草、大棗によって、お腹の働きを高めながら気の材料を補充し、気を量的に補ってくれます。
生姜は、消化を促すことでお腹の働きを高めるとともに、停滞した水分を発散して体の表層から排除する働きも応援します。
巡りを整える働き
陳皮は、お腹の気を下向きに巡らせることで、補充された材料を停滞させないようにし、お腹の負担を減らします。
当帰は、不足していた血を補いながら巡らせてくれるので、気が届けられるのを血液の巡りから応援してくれます。
補中益気湯の総合的な働き
これらの働きをまとめると次のようになります。
- 黄耆、柴胡、升麻が、下の方にこもって落ち込んでいた気を解放しながら上へと持ち上げる
- 人参、白朮、甘草、大棗、生姜が、気を量的に補充する
- 陳皮が気を下向きに引き降ろして停滞を防ぐ
- 当帰が血液を巡らせて気が届くのを助ける
**お腹の働きが回復することで、気の原料が補充され、それが体の上の方へと届けられるようになります。**その結果、疲労、立ちくらみ、食欲不振、下痢、便秘といったさまざまな症状が解消されるのです。
どんなタイプの人に向いている?体質別おすすめコメント
補中益気湯は、特に次のようなタイプの方におすすめです。
お腹が弱く疲れやすい方
胃腸の働きが弱く、食欲がわかない、すぐに疲れてしまうという方に適しています。お腹の働きを高めて気を補うことで、根本から体質を改善してくれます。
立ちくらみやめまいがある方
気が脳にまで届かないことで起こる立ちくらみやめまいに悩んでいる方に。気を上に持ち上げる働きで、脳へのエネルギー供給を助けます。
頭がぼーっとする方
疲れて頭がぼんやりしてしまう、集中力が続かないという方にもおすすめです。気を補って脳にまで届ける働きが、頭のクリアさを取り戻してくれます。
風邪をひきやすい方
お腹が弱く疲れやすくて、すぐに風邪をひいてしまうという方にも。気を補って肺にまで届けることで、外から侵入してくる邪魔ものを追い払う力を応援し、免疫力を高めてくれます。
特にこれから寒くなる季節には、風邪予防としても役立ってくれるはずです。
まとめ
今回は、疲れやすくて食欲がなく、立ちくらみなどを解消する漢方薬として、補中益気湯をご紹介しました。
お腹の働きが弱ってしまうと、食欲がなくなり、気が拡がらなくなってしまうため、疲れや立ちくらみが起こります。
補中益気湯は、お腹の働きを高めるとともに、こもって落ち込んでいた気を引き挙げて解放する働きがあります。日常的に疲れを感じていたり、頭がくらくらして立ちくらみになるような体質の改善に役立ってくれます。
また、気を補って脳にまで届ける働きも助けてくれるので、疲れて頭がぼーっとする方、いつも疲れてぼんやりとしてしまう方にも、とても助けになってくれるはずです。
ただし、症状が複雑な場合には、補中益気湯単独では効果が十分に得られない場合もあります。当店では一人ひとりの体質に合わせた漢方相談も行っておりますので、お気軽にご相談ください。
YouTubeでも解説しています。

ご自分の体質にあった
漢方薬を試してみたい方は
ピヨの漢方の漢方相談を
ご利用ください。