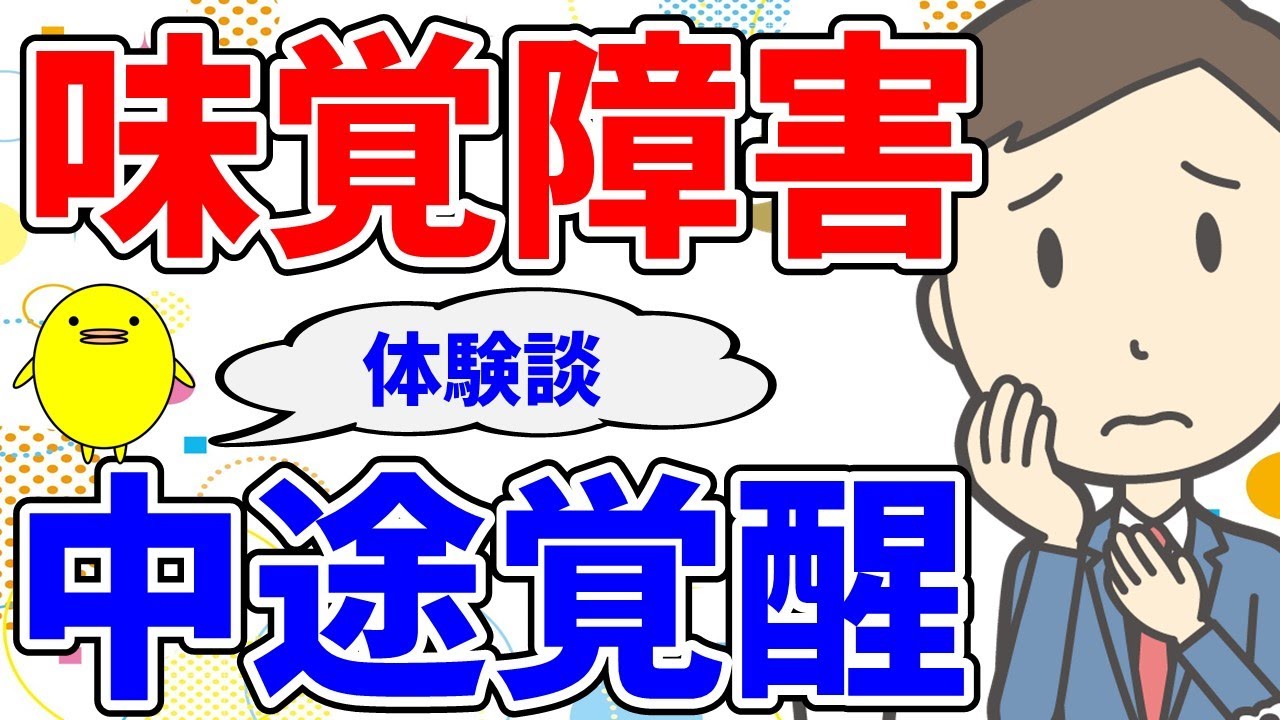こんにちは
どうなさいましたか?

味覚障害にお悩みの方から
質問をいただきましたよ
味覚障害は単なる「味がわからない」だけでなく、「味が異常に濃く感じる」「特定の味が受け付けられない」など、様々な形で現れる症状です。現代の食生活の乱れや環境の変化により、味覚に悩む方が増えています。
東洋医学では、味覚の異常は単に舌の問題だけでなく、全身の気血の巡りや内臓の状態と深く関連していると考えます。今回は、酸味を受け付けず味が異常に濃く感じるという味覚障害でお悩みの60代男性の体験談をもとに、東洋医学的な視点から原因と対策を考えていきましょう。
味覚障害でお悩みの方の外見的な特徴とお悩みの症状
この方の外見的特徴は以下の通りです:
- 60歳・男性
- 身長:182cm
- 体重:70kg
- BMI:21.13(標準範囲内)
- 皮膚や髪は乾燥気味
- 舌の色は白く、歯の痕があり、苔はベタっとしている
- 舌の裏の静脈は太く膨らんでいる
主な症状:
- 味覚障害(味が異常に濃く感じ、酸味は受け付けない)
- 血清亜鉛値減少(65)
- 食物アレルギー
- 夜間頻尿
- 中途覚醒
- 脚のつり
- 玄米や雑穀米を続けると舌がひりひりしたり、口内が苦く感じる
- 香辛料や添加物の多い食品でも同様の症状が出る
- 果物の酸味を全く受け付けなくなった
味覚とは?東洋医学的に考える味覚の役割
まずは味覚について簡単に考えてみましょう。
舌は主に横紋筋からなる舌筋によって構成され、その表面には舌乳頭(ぜつにゅうとう)と呼ばれる小さな突起が無数に存在しています。舌乳頭には4種類あり、最も多いのが糸状乳頭です。また、有郭乳頭や葉状乳頭は舌の後方に存在し、これらと茸状乳頭には味蕾(みらい)があるため、味覚の受容を担っています。
東洋医学では、舌は以下の役割があると考えます:
- 味覚を感じることから脾気や胃気と関わりがある
- 話をする際に意思を伝える器官として心気との関わりがある
- 身体に必要なものか不要なものかを判断する「バリア」として肺気との関わりがある
舌は単なる味を感じる器官ではなく、全身の状態を映し出す鏡のような役割も果たしているのです。
この方の東洋医学的な体質とは?
この方の症状から体質を分析してみましょう。
味が異常に濃く感じ、酸味を受け付けられないという症状は、気血を巡らせる肝気や、食べ物を受け入れる胃気において余分な熱が過剰になっている可能性があります。
また、口の中が苦く感じることから、肝気には熱がこもっており、体の中には水分や熱が過剰になっている湿熱の状態も見られます。
体の中の熱の様子を探ってみると:
- イライラしやすく怒りっぽい
- 喉が渇いて水が飲みたい
- 目が疲れやすく乾燥しやすい
これらは体の乾きや熱の症状を示していますが、顔色や舌の色からは、それほど強い熱の状態ではなさそうです。
体の水分の状態については:
- 口が粘る
- 筋肉が痙攣したり攣りやすい
- 髪の毛が抜けやすい
これらは体を潤す材料の不足が目立ちます。一方で、痰はあまりないものの薄めの黄色で、舌苔がベタっとしていることから、動きの悪い水分がドロドロしている様子がうかがえます。
また、1日に9回で昼間は少なく夜間に多量に出る尿の様子、舌の周辺の歯の痕、舌の裏の静脈の膨らみから、水の充満があり、さらに水分の巡りが順調ではない状態が見られます。
喉の渇きによる水分摂取が体に負担となっているようで、寒がりではないものの手足が冷えることから、水分が上部や末端部まで届いていないように感じられます。
この状態により、体の中では乾きやこもった熱と、停滞している水分が結びついて、肝胃に熱がこもり、それが口の中に湧き上がってくることで酸味や苦味などの味覚異常を感じさせているのでしょう。
ではこの方に、おススメの自然療法を教えて下さい
この方の体質を踏まえると、以下の自然療法がおすすめです:
- 水分摂取の工夫
- 舌に歯の痕がある、夜間尿の量が多い、喉が渇くという症状から、水分摂取の方法を工夫しましょう
- がぶ飲みせず、喉の渇きを癒すように少量ずつ飲むことをおすすめします
- 舌の色が白っぽいことから、体内の熱源に負担がかかっているため、冷たすぎる飲み物は避けましょう
- 睡眠環境の改善
- 不眠、中途覚醒、夜間頻尿の症状があるため、質の良い睡眠を確保することが重要です
- できるだけ早く部屋を暗くして、布団に入るようにしましょう
- 体を冷却する潤いや血の材料は夜間の睡眠中に作られるため、十分な睡眠時間の確保が必要です
- 適度な運動
- 水分の巡りが悪いため、昼間はできるだけ体を動かして水分の巡りを良くしましょう
- 散歩などの軽い運動で排尿を促し、適度に体を疲れさせることで良質な睡眠につながります
- 体を動かすことで、こもった熱やドロドロした水分の解消にもつながります
- 食事療法の継続
- すでに実践されている亜鉛やミネラルの摂取、免疫力を上げる食事は引き続き続けてください
- ただし、玄米や雑穀米で舌がヒリヒリする場合は、消化に負担がかかっている可能性があるため、白米と混ぜるなど負担を軽減する工夫をしましょう
この体質改善に効果が期待できる漢方薬
この方のような湿熱と水分の巡りが悪い体質には、以下の漢方薬が効果を期待できます。ただし、これらはこの方個人に処方を推奨するものではなく、あくまで同様の体質の方に一般的に用いられる漢方薬です。症状が複雑な場合には、単独では効果が得られないこともありますので、ピヨの漢方での漢方相談をおすすめします。
- 五苓散(ごれいさん):水分代謝を改善し、余分な水分を排出する効果があります。夜間頻尿や水分の巡りの悪さに働きかけます。
- 柴胡桂枝乾姜湯(さいこけいしかんきょうとう):胃腸の働きを整え、水分代謝を改善する作用があります。味覚異常や消化不良の症状に効果が期待できます。
- 竜胆瀉肝湯(りゅうたんしゃかんとう):肝の熱を取り、湿熱を改善する効果があります。口内の苦みや舌のヒリヒリ感などの症状に効果的です。
まとめ
今回は60代男性の味覚障害の体験談をもとに、東洋医学的視点から体質と対策を考えてみました。この方の場合、体内の湿熱や水分の巡りの悪さが味覚障害の原因と考えられます。
対策としては:
- 水分摂取の仕方を工夫する
- 質の良い睡眠を確保する
- 適度な運動で水分の巡りを良くする
- 食事療法を継続する
これらの対策を組み合わせることで、体質の改善が期待できます。また、症状に合った漢方薬の服用も検討してみてはいかがでしょうか。
味覚障害は生活の質に大きく影響します。少しずつでも改善していくことで、食事の楽しみを取り戻していただければと思います。体質改善には時間がかかりますが、焦らず続けることが大切です。
YouTubeでも解説しています。

ご自分の体質にあった
漢方薬を試してみたい方は
ピヨの漢方の漢方相談を
ご利用ください。