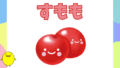こんにちは、皆さん。今回は私たちの食卓でもおなじみの「栗」について、その素晴らしい薬効や活用法を東洋医学の視点から詳しくご紹介します。
栗(くり)はブナ科クリ属の落葉高木で、その実は世界中で古くから食されてきました。日本では縄文時代の遺跡からも炭化した栗が発見されており、非常に長い食文化の歴史があります。
秋の味覚として親しまれる栗ですが、実は単なる美味しい食材ではなく、古来より東洋医学では重要な薬効を持つ食材として珍重されてきました。健康維持や体調管理に関心がある方は、ぜひ最後までお読みください。
栗の性味・帰経とは?東洋医学的特性
東洋医学では、食材や生薬の性質を「性味」と「帰経」で表します。栗の場合は:
- 性味:温、甘
- 帰経:脾、胃、腎
この意味するところは、栗が体を温める性質(温)を持ち、味は甘く、主に脾(消化器系)、胃、腎に作用するということです。これらの特性が栗の健康効果の基盤となっています。
栗にはどんな薬効がある?東洋医学的効能
栗には東洋医学的に見て、いくつかの重要な薬効があります。
1. 脾を補い下痢を止める(補脾止瀉)
栗は脾気虚(消化吸収機能の低下)による以下の症状に効果的です:
- 食欲不振
- 疲労感
- 腹部の冷えによる痛み
- 下痢
現代的に言えば、胃腸の働きを助け、消化吸収を促進する効果があるということですね。特に冷えによる胃腸トラブルに悩んでいる方には、栗を取り入れた食事がおすすめです。
2. 腎を補い筋肉を強くする(補腎強筋)
腎虚(腎機能の低下)による以下の症状を改善します:
- 足腰のだるさ
- 咳や喘息
- 頻尿や夜尿
東洋医学では腎は「先天の本」と呼ばれ、生命エネルギーの源とされています。栗を食べることで腎の働きを活性化させ、全身の元気を取り戻す手助けとなるのです。
3. 血行を促進し出血を止める(活血止血)
以下のような出血症状にも効果があります:
- 鼻血
- 吐血
- 血便などの出血
栗に含まれるタンニンには収れん作用があり、これが止血効果につながっていると考えられています。
栗を食べる際の注意点は?禁忌と使用上の注意
栗は多くの方に有益ですが、すべての方に適しているわけではありません。特に注意すべき点は:
- 熱性体質の方や気滞による便秘がある方は避けるべきです
- 糖分含有量が高いため、糖尿病の方は摂取量に注意が必要です
- 生の栗は消化しにくいため、しっかり加熱して食べましょう
- 保存時は通風の良い乾燥した場所に置き、カビの発生を防ぎましょう
栗は栄養価が高く、特に炭水化物を多く含むため、摂取量には気をつけることも大切です。一日の適量を守り、バランス良く摂取することをお勧めします。
栗の現代的健康効果と活用法
栗には東洋医学的な効能に加え、現代栄養学の観点からも多くの利点があります:
- 高い栄養価:ビタミンB群、ビタミンC、カリウム、食物繊維などを豊富に含みます
- 抗酸化作用:渋皮に含まれるタンニンには強い抗酸化作用があり、老化防止やがん予防効果が期待されています
- 腸内環境改善:食物繊維が豊富で、腸内環境の改善に役立ちます
- 美肌効果:ビタミンCを含み、美肌効果や免疫力向上に貢献します
まとめ:栗の魅力と効能
栗は単なる秋の味覚ではなく、東洋医学的にも現代栄養学的にも優れた食材です。その主な効能をまとめると:
- 脾胃の機能を高め、消化吸収を促進する
- 腎の働きを助け、足腰の強化に貢献する
- 血行を良くし、出血を止める効果がある
- 抗酸化作用により老化防止に役立つ
- 食物繊維が豊富で腸内環境を整える
ただし、体質や体調によっては摂取を控えるべき場合もあるため、自分の体調に合わせた適量を心がけましょう。
栗は秋が旬の食材ですが、冷凍保存などを活用すれば一年を通して楽しむことができます。東洋医学の知恵を生かし、栗を健康維持に役立てていきましょう。
皆さんも栗の持つ素晴らしい効能を知り、日々の食生活に取り入れてみてはいかがでしょうか?
参考文献

ご自分の体質にあった
漢方薬を試してみたい方は
ピヨの漢方の漢方相談を
ご利用ください。