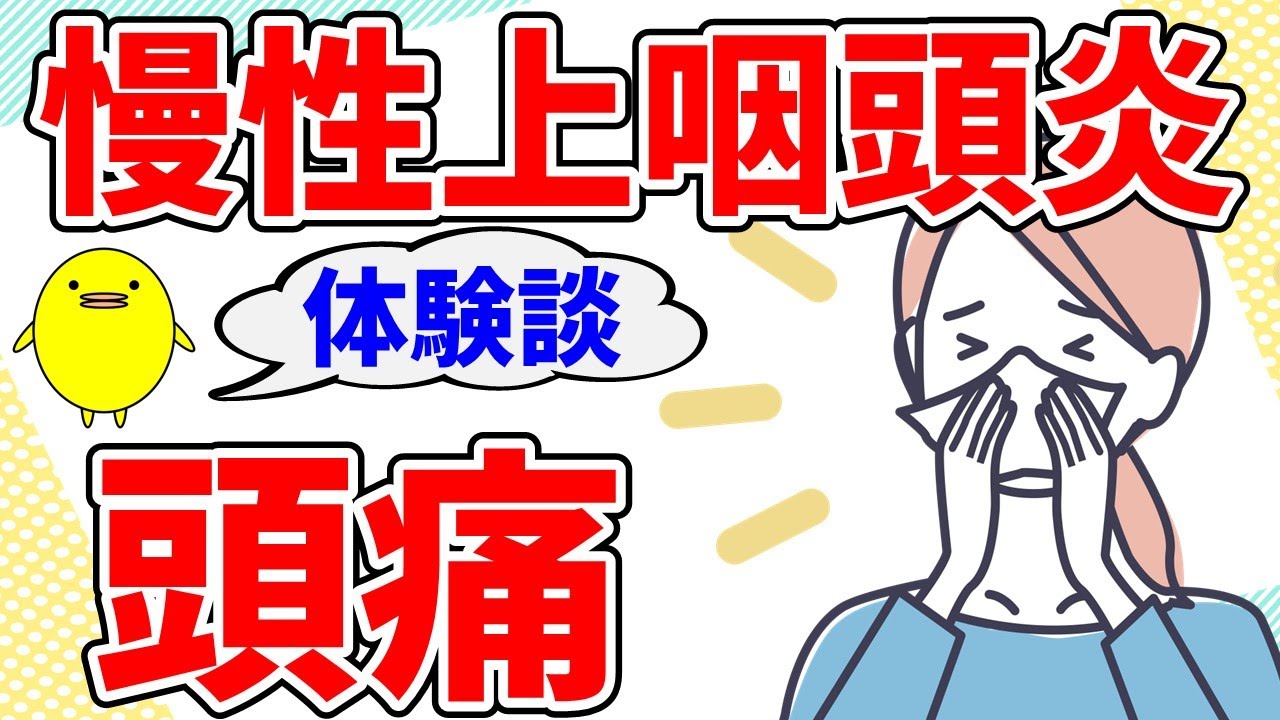こんにちは
どうなさいましたか?

咽頭炎にお悩みの方から
質問をいただきましたよ
上咽頭は私たちの呼吸において重要な役割を担う部位ですが、そこに炎症が起きると日常生活に大きな支障をきたします。慢性上咽頭炎は、後鼻漏や頭痛といった不快な症状を引き起こし、多くの方が悩まされています。
特に、通常の治療を受けてもなかなか改善しない場合、東洋医学的なアプローチが有効なケースがあります。今回は、44歳女性の貴重な体験談をもとに、慢性上咽頭炎と後鼻漏・頭痛の関係について、東洋医学の視点から解説していきます。
症状の背景にある体質を理解することで、より効果的な対策が見えてくるかもしれません。それでは、詳しく見ていきましょう。
外見的な特徴とお悩みの症状
今回ご相談いただいたのは44歳の女性の方です。まずは外見的特徴と症状を確認してみましょう。
- 年齢:44歳
- 身長:158cm
- 体重:47.5kg
- BMI:19.03
主な症状:
- 慢性上咽頭炎
- 後鼻漏
- 頭痛
- EAT治療後に後鼻漏、頭痛に悩まされている
- 漢方治療中(ツムラ9、104)
- 自身では鼻うがい、ストレッチ、赤なた豆茶などを実践
- 治療後に発熱や頭痛で動けなくなることがある
見た目の特徴としては、顔色が白っぽく、皮膚は乾燥気味です。また、髪の毛は乾燥して細く薄い状態です。舌の状態は白くて厚ぼったく、歯の痕があり、部分的に紫色が見られます。舌苔は白くて厚く、はがれているところもあり、舌の裏の静脈は太く膨らんでいるとのことです。
上咽頭炎とは?どんな病気なのか?
まずは、上咽頭炎について簡単に理解しておきましょう。
咽頭は鼻と喉の間にあり、食べ物と空気が交差する部位にあって、それらを振り分ける働きをしています。上咽頭は鼻の奥で喉の上部に位置し、空気が通る道となっている重要な部位です。
鼻から入った空気は上咽頭で向きを変えて肺へと下降していきます。上咽頭には重要な機能があります:
- 呼吸した空気の通り道
- 空気中のゴミやチリを取り除くフィルターとしての役割
- 通過する空気に適度な温度と湿度を加える加湿器のような働き
これらの働きによって、肺への直接的な刺激が緩和されているのです。
呼吸によって体内に入ってきた異物を外へ追い出すためには、鼻や喉の粘膜から分泌された粘液が異物を絡めて、線毛運動によって外側へと排除しています。
しかし、空気が乾燥しすぎていると粘膜も乾燥しやすくなり、冷たい空気によって鼻の粘膜が冷やされて血流が悪くなると、線毛運動による排除機能が低下して異物の侵入を許してしまうことになります。
上咽頭炎の主な原因と東洋医学的見解
上咽頭に炎症が起きると、痛み、乾燥、痰、声が出にくい、頭が重いなどの症状が現れます。炎症の原因はまだ明確にはわかっていませんが、よく言われるものとしては:
- 細菌やウイルスによる感染
- 疲労や睡眠不足
- 空気の乾燥
- 体の冷え
- ストレス
- 鼻づまりを起こす種々の原因
- 逆流性食道炎
- 喫煙
これらを東洋医学的な視点から見てみると、次のような考え方ができます。
1. 肺気の不足による機能低下
細菌やウイルスによる感染は、外部からの異物を排除する肺気の不足による機能低下が原因かもしれません。肺気とは、東洋医学で肺の持つエネルギーのことを指します。
2. 体内の潤いの不足
疲労や睡眠不足が続くと、体の潤いが不足して、異物を追い払うための粘液分泌が減少します。そのため、外部からの邪魔物を追い払えなくなり、局所的な炎症が起こります。
乾燥したところでは火が燃え広がりやすいように、潤いの不足によって炎症が助長されやすくなることも考えられます。空気が乾燥している季節には、体内が乾いている方の場合、その環境の影響がさらに強まります。
3. 体の冷えによる水分循環の悪化
体内の水分は、体の芯部の熱である腎陽によって温められて循環しています。身体が冷えると、水の巡りが悪くなります。
水分は体の熱によって温められて上方へ向かい、肺気の働きによって体表面を潤したり、体内へ戻したりする調整が行われます。しかし、腎陽が冷えると肺気の働きも低下し、周辺の血流も悪化します。その結果、異物を追い払えなくなり炎症が起き、粘膜で水が停滞すると鼻づまりにつながります。
4. 体内の水分過剰による問題
鼻づまりは体内の水分が充満している場合も起こります。鼻の粘膜で水が溢れると、周辺の水の巡りも悪くなります。
同じ火力のお風呂でも、適度な水量なら水は正しく循環しますが、水量が多いと温まりにくく循環しません。同様に、水が充満していると鼻周辺の水の巡りが悪くなり、水の停滞で血管が圧迫されて先に潤いが届かなくなるため、炎症が起こります。
5. ストレスによる気の滞りと熱の発生
身体の水分は腎陽によって温められて動きの勢いが作られ、肺気や脾気の働きで巡っていきますが、肝気の調節によって必要な場所へと配分されています。
ストレスなどで肝気が滞ると熱が生じ、それだけで炎症の原因になります。また、停滞している水分が熱によって煮詰められ、ドロドロとした状態に変化します。
ストレスによる筋肉の緊張は気や血液の巡りを悪くします。気が停滞すると内側にエネルギーが集中して熱が生じる一方、表層ではまばらになり、隙間から異物が侵入しやすくなって炎症につながります。
体質の特徴から見るこの方の状態
この方の体質的特徴を見てみましょう。
舌の形が厚く歯の痕があり、苔も厚くて水っぽいことから、体内には余分な水分が充満しているように思われます。小便の回数が1日1回で普通量であること、足や顔に浮腫みがあること、口が粘り、頭が重く感じられることが多いこと、雨の日は体調が悪いことなどから、水の巡りに勢いがなく停滞している様子がうかがえます。
手足が冷える、寒がり、顔色が白い、舌の色も白いことから、熱の不足が関係していそうです。ただし、BMIが19.03と問題ないことから、体全体で水分が溢れているわけではなさそうです。皮膚の乾燥、髪の毛が抜けやすく細くて薄い、不眠になりやすいといった症状から、体の上部を中心に熱や乾きの症状が見られます。
一方で、イライラしやすく怒りっぽい、肩こりがあるなど、気の滞りを感じさせる症状もあり、単なる冷えだけで水分の流れが悪いわけではなさそうです。
喉に何かが引っかかる感じがする、食べると腹が張りやすい、吐き気を感じるなど、腸管を中心に気が逆流して上向きになっている様子があります。
気の流れは上向き過剰になっていますが、熱の不足と余分な水分の充満により、水を巡らせる力に余裕がなく、必要な血を上部へ届けることができません。さらに、小便の回数が少ない、頭が重い、顔に浮腫みがあるなどから、上に昇って行った水分が降りてこられなくなり、鼻や咽頭の周辺に水の充満を引き起こしています。
月経血の量が少ない、顔色や舌の色が白い、髪の毛が抜けやすいことから、血の不足も感じられます。体温が高くないのに熱っぽく感じるのは、炎症を鎮静化させるための潤いが不足しているためと考えられます。そのため、咽頭の炎症がなかなか収まらないのでしょう。
ではこの方に、おススメの自然療法を教えて下さい
この方の体質を踏まえると、以下の自然療法がおすすめです。
1. 適切な運動で水分循環を改善
体内には動きの悪い水分が充満している様子が見られますので、体を動かして体の熱を作り、気の滞りを解消することが大切です。運動によって水の巡りが改善すれば、停滞している水分も適切に排出されるようになります。
現在続けられているストレッチに加えて、リラックスを心がけながら近所の公園などを散歩するのも良いでしょう。運動不足を感じる場合は、無理のない範囲で活動量を増やしてみてください。
2. 身体の緊張をほぐす
顎を噛みしめる、眉間に力が入る、喉を締める、お腹が力むなど、どこかに力みが入っている癖があると、それが気の流れを阻害して炎症の原因となることがあります。心当たりがあれば、意識的に緩めるようにしましょう。
3. 食事の調整
痛みが強い場合には、食事はできるだけ薄味にして、味の濃い物や脂っこい物、辛い物、アルコールなどは炎症を強めるので控えましょう。刺激物は避けるようにすることが大切です。
4. 炎症を鎮める食材の活用
以下の食材は咽頭の炎症を鎮める効果があるので、上手に取り入れてみましょう:
- 薄荷(はっか)
- 菊の花
- 大根
- 梨
- 柿
- 梅
- レモン
- 蜂蜜
- 氷砂糖
- ほおずき
- 胖大海(はんだいかい)
この体質改善に効果が期待できる漢方薬
この方のような体質の改善に効果が期待できる漢方薬としては、以下のようなものがあります。ただし、これらは一般的な情報であり、この方に特定して処方されるものではありません。
- 清上防風湯(せいじょうぼうふうとう) – 上咽頭の熱を取り除き、炎症を鎮める効果が期待できます。喉の痛みや乾燥感の改善に用いられます。
- 滋陰降火湯(じいんこうかとう) – 体内の熱を冷まし、潤いを補う作用があります。上部に熱がこもりやすい体質の改善に役立ちます。
- 加味逍遙散(かみしょうようさん) – 気の滞りを解消し、肝気を調整する効果があります。イライラや不眠、肩こりなどの症状改善に期待できます。
なお、症状が複雑な場合には、これらの漢方薬を単独で使用しても十分な効果が得られないことがあります。ピヨの漢方では、お一人おひとりの体質や症状に合わせた漢方相談を行っておりますので、お気軽にご相談ください。
まとめ
慢性上咽頭炎は、東洋医学的に見ると、体内の水分バランスの乱れ、熱の不足、気の滞り、血の不足など、様々な要因が複雑に絡み合って起こる症状です。
この方の場合、体内の余分な水分が充満し、熱の不足と共に血などの潤いも不足している状態と考えられます。さらに気の滞りもあり、これらが複合的に作用して慢性的な炎症を引き起こしているようです。
自然療法としては、適度な運動による水分循環の改善、身体の緊張をほぐすこと、食事の調整、そして炎症を鎮める食材の活用が効果的でしょう。
また、体質改善のための漢方薬も補助的に活用することで、症状の改善が期待できます。しかし、体質や症状は個人差が大きいため、専門的な相談をおすすめします。
YouTubeでも解説しています。

ご自分の体質にあった
漢方薬を試してみたい方は
ピヨの漢方の漢方相談を
ご利用ください。