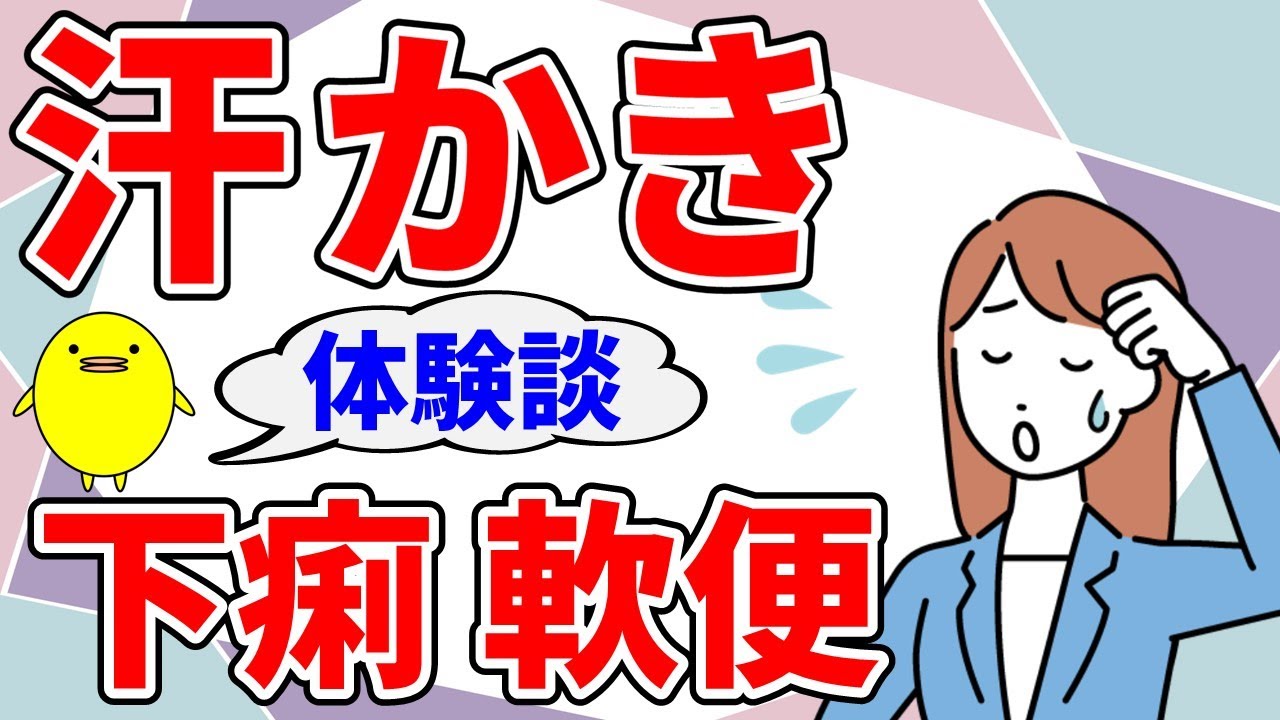こんにちは
どうなさいましたか?

多汗にお悩みの方から
質問をいただきましたよ
暑い季節になると特に悩まされるのが「汗の量」ではないでしょうか。少し動いただけで服が汗でびっしょりになってしまったり、冷房がきいた室内でも汗が止まらなかったり…。そんな「多汗症」に悩む方は意外と多いものです。
今回は62歳の女性から寄せられた体験談をもとに、東洋医学の観点から多汗症の原因と対策について詳しく解説していきます。体質や症状に心当たりのある方は、ぜひ参考にしてみてください。
多汗症に悩む方の体験談〜外見的な特徴とお悩みの症状
まずはこの方の特徴と症状をご紹介します。
外見的な特徴:
- 62歳女性
- 身長155cm
- 体重85kg
- BMI 35.38
- 赤ら顔
- 皮膚や髪の毛は乾燥
- 舌の色は紫色で溝や割れ目がある
- 舌苔は白くて厚い
- 舌の裏の静脈は太く膨らんでいる
主な症状:
- 若い頃(体重40kg台)から大量の汗に悩まされている
- 冷房完備の職場でも、バレーボール2個分の洗濯物を持ち帰る
- 短時間の通勤でも下着まで交換が必要なほど汗をかく
- 家事中は5分おきにTシャツ交換が必要
- 夏場は尿量が極端に少なくなり、膀胱炎を起こしやすい
- コントレックスや天然水の2Lペットボトルで水分摂取をしているが、汗と下痢に水分が回ってしまう
- お腹は慢性的に緩い
- 脚や顔はいつも浮腫んでいる
- 寝つきが悪く、夜中に何度も起きる
汗とは?東洋医学からみた発汗のメカニズム
汗は単なる体の不要物ではなく、体温調節に欠かせない重要な働きをしています。東洋医学では、この汗の調節に関わる体の仕組みを詳しく説明しています。
体は外気温の上昇や運動による体温上昇に対して、皮膚表面にある汗腺から汗を出し、その蒸発熱により体温を下げようとします。この過程には次のような要素が関わっています:
- 津液(しんえき):体内の潤いの源となる水分
- 肝気(かんき):体の内側から汗を押し出して外へ運ぶ働き
- 肺気(はいき):皮膚表面で汗の量を調整する働き
これらのバランスが取れていると、適切な量の汗が出て体温調節がうまくいきます。しかし、どこかに不具合があると発汗の異常が起こるのです。
多汗症が起こる主な原因とは?
1. 肺気の異常による多汗
肺気は体の表層を覆い、バリアやバッファーとして機能し、気や水分の巡りを調整します。門番のような役割を持ち、必要な水分は外へ放出し、不要な分は体内へ戻します。
しかし、気の不足などで肺気の働きが低下すると、汗を体内へ戻せなくなり多汗になります。これは門番が少なくなって門が開きっぱなしになり、出ていく人を止められない状態です。
この状態では、あまり動かなくても自然と汗が出たり、少し動いただけで汗が止まらなくなります。また、外からの邪気も侵入しやすくなるため、風邪をひきやすくなります。
2. 肝気の異常による多汗
体が活動して熱が生じると、肝気の活動が活発になり、汗を放出して熱を冷まそうとします。しかし、ストレスや強い緊張状態があると、汗を押し出す肝気の働きが強くなりすぎて、肺気の制御を超えて汗が多く出てしまいます。
この状態では、イライラや熱感を伴う多汗症状が現れやすくなります。
3. 体の潤いの不足による多汗
水分を運搬し汗を押し出す肝気は、体の潤いによって制御されています。潤いが不足すると、相対的に肝気の働きが過剰になり、汗を押し出す力が強くなります。
特に寝汗として現れることが多く、過労や夜更かしなどで体全体の潤いが不足している人に見られます。睡眠中に気が内側に戻る際に、バランスが崩れたあぶれた気が強い勢いで飛び出し、表面の水分を巻き込んで寝汗となります。
4. 心気の乱れによる多汗
肝気は心気からの指令でコントロールされています。心気は精神活動に関わる働きを司り、不具合があると考えや感情の働きが行き過ぎて落ち着きを失います。
国のトップが乱れると兵士たちが混乱するように、心気の乱れは肝気の正常な働きを妨げ、緊張が強まり、気の外向きの力が強くなって多汗になります。
この方の体質分析
今回の相談者の方の症状から、次のような体質的特徴が考えられます:
- BMIや舌の苔から、体内に余分な水分が停滞している
- 多汗から、体の表層では外側へ向かう力が制御力を上回っている
- 冷房の効いた場所でも汗が出ることから、体の活動による熱産生とは関連が薄い
- 熱っぽさや不眠から、体を冷却する潤いが不足し、肝気の巡りは滞って上方へ向かっている
- 下痢や軟便は、肝気と脾気(消化吸収を司る)の調和が取れていないサイン
- 顔や足の浮腫みは、上方へ向かう気の流れに水分が巻き込まれ、また余分な水分が停滞している
- 腰痛や膝の脱力感は、腎気(体の根本的なエネルギー)の低下を示している
- 赤ら顔は、こもった熱によるものと考えられる
この方の多汗症の原因をまとめると:
腎陰・腎陽の機能低下を背景に、肝気の滞りと潤いの不足によって制御が外れた勢いが加わり、気の外向きの力が強まっています。また、潤いの不足と肝気の滞りで生じたこもった熱が喉の渇きを生じさせ、水分摂取増加→体内水分の停滞→汗の材料増加という悪循環が起きています。
さらに夏は気が外向きになりやすく、上昇する気の流れに巻き込まれた水分が正しく下降できず尿になれないため、排尿量が減り膀胱炎を起こしやすくなっているのです。
ではこの方に、おススメの自然療法を教えて下さい
この方の状態を改善するためには、次のような自然療法がおすすめです:
- 適度な運動:停滞した水分の巡りを良くし、気の滞りを解消するため、リラックスしながらの散歩がおすすめです。これにより体の巡りが良くなり、下半身の筋力強化で上に上がりやすい気の流れが手足の末端へと降りやすくなります。
- 呼吸法:足の裏に意識を向けながら長い呼吸を繰り返すと、副交感神経が優位になり、緊張感が緩み、熱が冷めて気の滞りが解消しやすくなります。
- 緊張緩和の意識:無意識の噛みしめや顎の緊張に気づき、意識的に緩めることで全身の気血の巡りが改善します。顔の体操のように口を大きく開いて口角を上げるだけでも気持ちに変化が現れます。
この体質改善に効果が期待できる漢方薬
この体質の方に効果が期待できる漢方薬をいくつかご紹介します:
- 五苓散(ごれいさん):水分代謝を改善し、むくみや下痢を改善する効果があります。体内の余分な水分を正しく排出するのを助けます。
- 当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん):血行を促進し、冷えやむくみを改善します。特に女性ホルモンのバランスを整える効果も期待できます。
- 柴胡加竜骨牡蛎湯(さいこかりゅうこつぼれいとう):精神的な緊張や不安を和らげ、自律神経のバランスを整えます。のぼせや不眠にも効果的です。
ただし、これらはあくまで特定の体質改善に効果が期待できる一般的な漢方薬の紹介であり、個人の症状に合わせた処方ではありません。症状が複雑な場合には、単独では効果がない場合もあります。ピヨの漢方では漢方相談も行っておりますので、お気軽にご相談ください。
まとめ
多汗症は単なる汗の量の問題ではなく、体内の気・血・水のバランスの乱れが原因となっています。特に、肺気・肝気の働きと体の潤いのバランスが重要です。
今回ご紹介した方のように、冷房完備の場所でも大量の汗をかく場合は、体質的な要因が大きいと考えられます。適切な運動、呼吸法、緊張緩和の工夫などの自然療法と、必要に応じて漢方薬を取り入れることで改善が期待できます。
自分の体質に合った対策を見つけることが大切です。一人で悩まず、専門家に相談してみることもおすすめします。
YouTubeでも解説しています。

ご自分の体質にあった
漢方薬を試してみたい方は
ピヨの漢方の漢方相談を
ご利用ください。