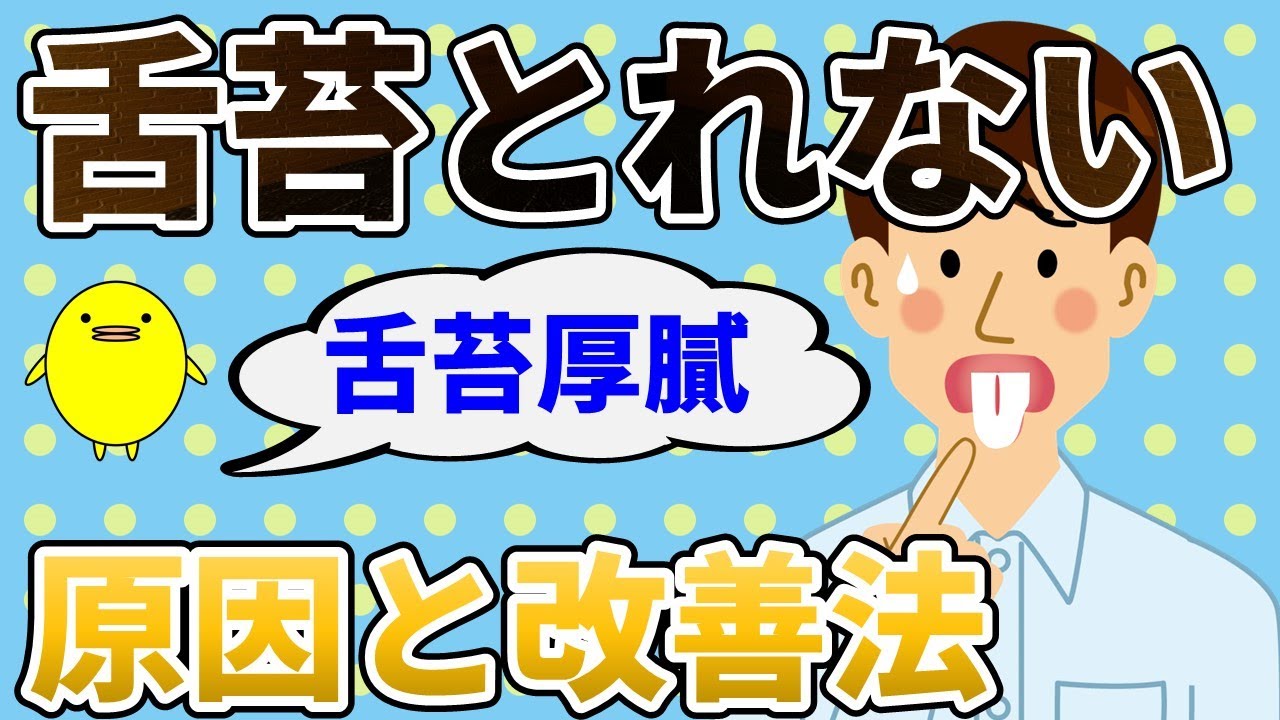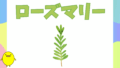こんにちは
どうなさいましたか?

舌苔にお悩みの方から
質問をいただきましたよ
あなたの舌に白い苔のようなものが付いていませんか?それは単なる口腔内の汚れではなく、あなたの体が発している健康信号かもしれません。
東洋医学では、舌の状態は全身の健康状態を映し出す「舌診」として重要視されてきました。特に舌苔(ぜったい)の量や色、分布パターンには、あなたの体内で起きている変化が反映されています。
今回は、気になる舌苔が増える原因と、東洋医学の視点からみた自然な改善方法についてご紹介します。このお話を通じて、舌苔の改善に役立つヒントが得られるはずです。
舌の構造とは?舌苔が生まれる仕組み
まず、舌苔が生まれる仕組みを理解するために、舌の構造について知っておきましょう。
舌の周囲は粘膜で覆われていますが、表面には「舌乳頭」と呼ばれる小さな突起が無数に存在しています。舌乳頭には4種類ありますが、特に舌の表面を多く占めているのが「糸状乳頭」です。
糸状乳頭は先のとがった小さな円錐形をしていて、表面が角化することで乳白色に見えます。この角化して硬くなっている糸状乳頭の根元に、食べ物のカスや脱落した細胞、粘液、老廃物、細菌などが積み重なることで舌苔が形成されます。そのため、健康な人でもうっすらと白く見えるのが正常な状態なのです。
また、「茸状乳頭」も糸状乳頭に比べると数は少ないものの、舌の表面に広く分布しています。茸状乳頭はその構造から内部の毛細血管が透けて見えるため、それぞれの人の状態によって舌の色を決めていると考えられます。
健康な人の舌は、血色の良いうっすらと淡い赤い色で、その表面に薄っすらと白い苔が乗っている状態です。東洋医学ではこれを「淡紅舌、薄白苔」と呼びます。
東洋医学における舌診とは?体全体と舌の関係性
東洋医学には、人間は自然界の一部であり、外界の状況が体の内部に影響を与えるという考えがあります。つまり、全体と一部はつながっているという見方から、局所である舌の状態が、身体全体の状態を反映していると考えるのです。
この考えによれば、舌の各部位は体の異なる部分と関連しています:
- 舌の根っこの方:身体の土台を司る腎気の様子
- 舌の中央部:身体の中心部に位置しお腹の働きを調整する脾気の様子
- 舌の先端:体の表層や頭部の働きを調整する心気や肺気の様子
- 舌の側面:身体全体に材料を運搬している肝気の様子
これは単なる伝統的な考えではなく、現代医学的にも一定の根拠があります。舌の奥は内臓と同じ内胚葉から発生・分裂成長し、舌の前方は皮膚や中枢神経などと同じ外胚葉から発生していると考えられています。
そのため、内臓に何らかの変化が生じると、同じ胚葉から分裂成長した舌にもその影響が現れる可能性があるのです。
舌苔が増える原因は?体内環境の変化と舌苔の関係
では、舌苔が多くなってしまう原因について考えてみましょう。
舌苔は糸状乳頭の根元に食べ物のカスなどが積み重なって形成されるため、糸状乳頭が大きくなると食べ物のカスなどがより多く積もるようになります。
糸状乳頭は毛細血管から栄養を受けて成長するため、血液中の糖分やたんぱく質などの栄養分が多いと、糸状乳頭の角化が遅くなってより長く伸び、大きくなります。その結果、より多くの微小な物質が引っかかるようになり、舌苔が目立つようになるのです。
つまり、体の中に余分なものが蓄積していることで舌苔が目立つようになります。東洋医学では、舌苔が厚く積み重なっている状態を見ると、「湿邪」が体内に停滞していると推測します。
例えば以下のような生活習慣が原因となることがあります:
- 必要以上に食べ過ぎている
- カロリーの高い飲み物を飲み過ぎている
- 空腹感がないのに時間が来たからという理由で食事をしている
特に最後の点は意外かもしれませんが、空腹感もないのに時間で食べてしまう場合、身体が必要としていない食べ物を摂取することになり、体に余分なものが蓄積してしまうのです。
舌苔の色や場所から読み取る体の状態
舌苔の色の違いによって、体内の活動状態を判別することもできます。
- 白い舌苔:正常か、または体が冷えている状態
- 黄色い舌苔:体の中に動きの悪い熱が存在している状態
- 黒っぽい舌苔:熱が極まった状態
舌苔が黄色く見える場合は、熱によって増殖した細菌や、その細菌と戦った免疫細胞の死骸が糸状乳頭にひっかかる量が増えることで色が変化します。
また、舌苔の分布にも意味があります:
- 舌の根っこに舌苔が多い場合:体の下の方である腎の領域に余分な水分が充満している可能性があります。体の芯部が冷えると水分の巡りが悪くなり、体の下方に水分が滞留します。この場合、舌苔は白っぽく見えることが多いです。
- 舌の先端や側面の舌苔が少ない場合:体に熱がこもっている可能性があります。舌の先端(心気・肺気)や側面(肝気)の部位は熱の影響を受けやすく、熱によって潤いが消耗されると、その部位の舌苔が少なくなります。一方で舌の根っこには厚い舌苔が残ります。この場合、舌は赤く、苔は黄色くなることが多いです。
ではこの方に、おススメの自然療法を教えて下さい
舌苔は体内に余分な水分が充満すると増えますので、その排除方法を2つご紹介します。
1. 体の芯部が冷えている場合の対策
体の芯部が冷えて舌苔が増えている場合には、体の熱を増やして水分の巡りを改善し、余分な水分を外へと排除する必要があります。
おすすめの対策:
- 適度な運動を行う:体内の水分は体の熱によって巡っています。身体が冷えていると水の巡りが悪化し、体のあちこちに停滞してしまいます。
- 体を冷やす食べ物を控える:冷たい飲食物や生野菜の摂りすぎに注意しましょう。
- 適切な水分摂取:喉が渇いていないのに水分を摂るのは控えましょう。このタイプの方は水の巡りが悪いことで喉元に水分が巡らず熱が生じて喉が渇くことがあります。喉が渇いたら飲むようにし、一気にがぶ飲みせず少しずつこまめに喉を潤すように飲みましょう。
- 身体の声に耳を傾ける:空腹感がないのに食事をしている方は、お腹が空いたら食べるようにしましょう。
2. 身体に熱がこもっている場合の対策
体に熱がこもって舌苔が変化している場合も、食事と運動に気をつけることが重要です。
おすすめの対策:
- 余分な熱を生み出す飲食物を控える:カロリーの高いもの、濃厚な味付け、アルコール類の摂り過ぎを控えましょう。
- 特に注意したい食品:
- 味の濃厚なものやこってりしたもの
- ポテトチップスやドーナツなどの油で揚げてある食品
- チーズやヨーグルトなどの乳製品(体内で停滞しやすい性質があります)
- 適度な運動を行う:体の中にこもっているものを体外へ追い出すのを手助けしてくれます。無理せず続けることが効果的です。
- ストレス管理:ストレスで気が滞ると余計な熱が生じ、それが過食の原因にもなります。適度な運動によって気の巡りを改善しましょう。
舌苔の改善に効果が期待できる漢方薬
舌苔の状態によって、以下のような漢方薬が効果を期待できます。ただし、これらは特定の体質の改善に効果が期待できる漢方薬の紹介であり、あなた個人に合う漢方薬とは限りません。症状が複雑な場合には、単独では効果がない場合もありますので、ピヨの漢方での漢方相談をご利用ください。
- 苓桂朮甘湯(りょうけいじゅつかんとう):水分代謝を促し、体内の余分な水分を排出する効果が期待できます。冷えによる水分停滞に有効です。
- 黄連解毒湯(おうれんげどくとう):体内の熱を冷まし、熱による炎症を鎮める効果があります。黄色い舌苔が見られる場合に考慮される漢方薬です。
- 半夏瀉心湯(はんげしゃしんとう):胃腸の機能を整え、水分と熱のバランスを調整する効果があります。舌苔が厚く、消化不良の症状がある場合に使用されることがあります。
まとめ:舌苔から読み取る健康と改善の鍵
舌苔は単なる口の中の汚れではなく、体内環境を映し出す健康のバロメーターです。舌苔が増える主な原因は、体内に余分な水分や熱が蓄積することにあります。
改善のポイントは以下の通りです:
- 適切な食生活:体質に合わせて、冷やす食品や熱を生み出す食品の摂取量を調整する
- 適度な運動:体内の水分循環を促進し、余分なものを排出する
- 水分摂取の工夫:体の声に耳を傾け、適切なタイミングと量を心がける
- ストレス管理:気の巡りを良くして、熱の蓄積を防ぐ
舌苔の状態は日々の生活習慣を見直すきっかけになります。小さな変化を積み重ねて、健康な舌と体を取り戻しましょう。
YouTubeでも解説しています。

ご自分の体質にあった
漢方薬を試してみたい方は
ピヨの漢方の漢方相談を
ご利用ください。