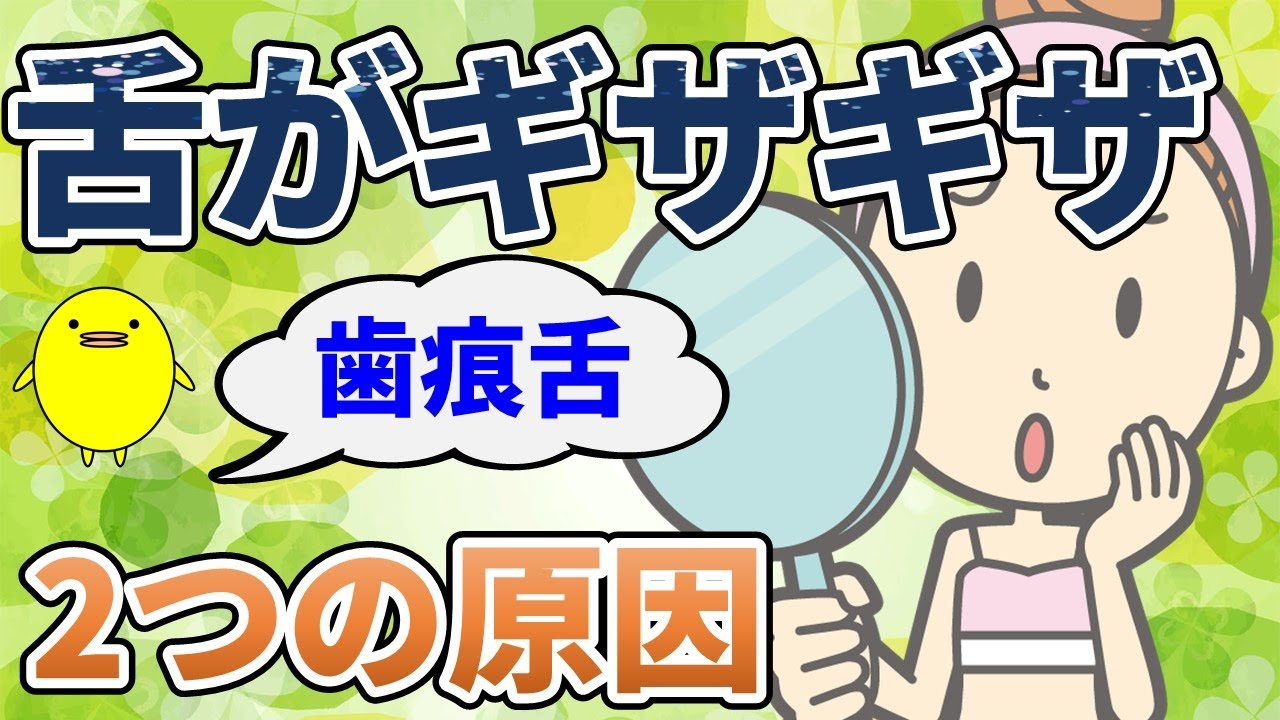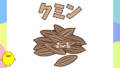こんにちは
どうなさいましたか?

舌のギザギザにお悩みの方から
質問をいただきましたよ
「最近、舌に歯の跡がくっきり残るようになった…」「ギザギザになった舌が元に戻らなくて不安…」このようなお悩みをお持ちではありませんか?
実は舌の状態は、私たちの体の内部環境を映し出す「体内の鏡」とも言われています。特に東洋医学では、舌を診ることで体の状態を知る「舌診」が古くから重要視されてきました。
舌にギザギザの歯形が残る状態は「歯痕舌(しこんぜつ)」と呼ばれ、ただの一時的な現象ではなく、体からのサインかもしれません。今回は、この歯痕舌の原因と改善法について詳しくご紹介します。
このお話を理解することで、舌のギザギザを改善するための有効なヒントが得られるでしょう。ぜひ最後までお読みください。
外見的な特徴とお悩みの症状
舌がギザギザになる方には、以下のような特徴や症状が見られることがあります:
- 舌に歯形の跡が残る(歯痕舌)
- 舌が通常より大きい(胖大舌)
- 舌の色が白っぽい、または淡い赤色
- 舌苔(ぜったい:舌の表面の白っぽい膜)が白く水っぽい
主な症状:
- 寒さに弱い
- 手足が冷える
- 食欲不振
- 消化不良
- 関節痛や筋肉痛
- 全身のだるさや疲れやすさ
- 汗が出やすく風邪をひきやすい
舌の構造とは?基本を理解しましょう
まずは舌の基本的な構造について理解しておきましょう。
舌は口の中にある突起状の器官で、主に横紋筋からなる舌筋によって構成されています。この筋肉の周囲には豊富な血管と神経が走行しており、非常に繊細な組織です。
舌の表面は粘膜に覆われていて、その表面には「舌乳頭」と呼ばれる小さな突起状のものが無数に存在しています。特に「茸状乳頭(じょうじょうにゅうとう)」はその構造から内部の毛細血管が透けて見えるため、それぞれの人の体調によって舌の色を決めていると考えられています。
意外と知られていませんが、舌はほぼ筋肉でできていて、重さは約200gもあるといわれています。そのため、筋肉が弱ってしまうと張りがなくなって垂れ下がってくることもあるのです。
また、舌は体の内部にあることから、内臓の状態を反映しているとも考えられています。内臓に何らかの変化が生じると、同じ胚葉から分裂成長した舌にその影響が現れるのです。
では、なぜ舌がギザギザになってしまうのでしょうか?その原因について見ていきましょう。
舌がギザギザになる2つの原因とは?
舌に歯の跡が残ってしまう状態を、東洋医学では「歯痕舌」と呼びます。文字通り舌に歯の痕が残っている状態ですが、この歯痕が出来るためには舌が大きくなっていることが前提となります。
舌が大きくなる原因は主に「舌のむくみ」です。「舌もむくむの?」と思われるかもしれませんが、足がむくむのと同じように、舌もむくむことがあります。
東洋医学では舌が大きくなることを「胖大舌(はんだいぜつ)」と呼びますが、これは体の中に余分な水分が充満しているサインと考えられています。
原因1:体の芯部の冷え
余分な水分が充満する最初の原因として考えられるのが、身体の芯部が冷えていることです。体の芯が冷えると、体内の水分を巡らせることができなくなり、水が停滞してしまいます。
体内を巡る水分は、体の芯部の熱源である「腎陽(じんよう)」によって温められ軽くなってから、「脾気(ひき)」と「肝気(かんき)」の働きによって循環しています。芯部が冷えてしまうと、水分の巡りが悪くなり、あちこちで溢れるように停滞するため、舌にもその状態が反映されて胖大舌となります。
このような状態になると、舌も含めた全身の血流が悪くなるため、舌乳頭の下を通過する赤血球の量が減少し、舌の色は白っぽく見えるようになります。
原因2:舌の張りの弱さ(気の不足)
舌に歯の痕が残る原因にはもう一つ、舌の張りの弱さという重要な要因があります。
例えば、風船に水がパンパンになるほど入っていれば、指で押してへこんでも指を放すと元の張りのある状態に戻ります。これは風船に外側へと押し拡がろうとする弾力性と張りがあるからです。
つまり、舌にへこみが残ってしまうのは、へこみを押し戻す張りの弱さが原因です。このような張りのない舌のことを「嫩舌(どんぜつ)」といいます。
人間の身体において、張りを維持するためには「気」が必要です。胃下垂や遊走腎、子宮脱など、内臓が下垂してしまう様々な症状は、内臓を正しい位置に保持する筋肉の緊張が緩んでしまうことが原因です。
東洋医学では、「気」が持つ運んだり持ち上げたりする働きが筋肉の緊張感を保ち、内臓の位置を維持していると考えています。そのため、気のパワーが量的に不足すると、筋肉は緩み、舌にも歯の痕が残るようになります。
このような場合、「気」は熱を生じさせる元でもあるため、気が不足すると冷えが生じやすくなり、舌は白っぽくなることが多いです。また、体が冷えることで水の巡りも悪くなり、むくみが生じることもあるため、舌が大きくなることもよく見られます。
ではこの方に、おススメの自然療法を教えて下さい
舌のギザギザの改善には、タイプ別のアプローチが効果的です。お悩みの症状に合わせた自然療法をご紹介します。
冷えとむくみが原因の場合(舌が大きく白い)
舌が大きく、色が白っぽく、苔も白く水っぽい場合は、体の冷えと水の巡りの悪さが原因と考えられます。このタイプの方には以下の対策がおすすめです:
- 水分摂取の見直し 喉の渇きを感じない時の過剰な水分摂取は控えましょう。特に冷たい飲み物は体を冷やす原因になります。
- 体を冷やす食べ物を控える キュウリやトマト、スイカなどの体を冷やす性質のある食べ物はバランスを考えて摂取しましょう。
- 適度な運動習慣 体が軽く汗ばむ程度の運動を定期的に行い、血液循環を促しましょう。これにより停滞している余分な水分を排出する効果が期待できます。
気の不足が原因の場合(舌の大きさ普通、色は正常なことも)
舌の大きさが普通で色も淡い赤色(正常)なのに歯痕がある場合は、**舌の張りの不足(気の不足)**が原因と考えられます。このタイプの方には以下の対策がおすすめです:
- バランスの良い食事 和食を中心に、消化に負担をかけない食事を心がけましょう。空腹感を感じたときに、よく噛みながら腹八分目を意識して食べることが大切です。
- 適度な負荷のある運動 体に無理のない程度の負荷をかける運動は、身体のエネルギー生成システムを活性化させ、「脾気」の働きを高めるのに役立ちます。
- 規則正しい生活リズム 十分な睡眠と規則正しい生活は、体のエネルギーを回復させるのに不可欠です。特に午後10時から午前2時までの間の質の良い睡眠を心がけましょう。
舌のギザギザ改善に効果が期待できる漢方薬
舌のギザギザ(歯痕舌)の改善に効果が期待できる漢方薬をいくつかご紹介します。ただし、これらは特定の体質改善に効果が期待できる一般的な漢方薬であり、個人の症状に合わせた処方ではありません。
- 六君子湯(りっくんしとう): 脾胃の機能を高め、気の不足を補う漢方薬です。消化不良や食欲不振、全身倦怠感がある方に適しています。
- 補中益気湯(ほちゅうえっきとう): 中焦(胃腸)の気を補い、疲労回復や免疫力向上に効果があります。気虚による全身倦怠感や汗が出やすい方におすすめです。
- 五苓散(ごれいさん): 水分代謝を改善し、むくみの解消に効果が期待できます。体の水の巡りが悪く、むくみやすい方に適しています。
症状が複雑な場合には、これらの漢方薬を単独で服用しても十分な効果が得られないことがあります。ピヨの漢方では漢方相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
まとめ
舌のギザギザ(歯痕舌)は、単なる見た目の問題ではなく、体からの重要なサインです。主な原因は以下の2つに集約されます:
- 体の芯部の冷えによる水分の停滞(むくみ)
- 気の不足による舌の張りの低下
これらの問題を改善するためには、体質に合わせた食生活の見直し、適度な運動習慣、そして必要に応じて漢方薬などの自然療法が効果的です。
舌の状態は日々変化します。生活習慣の改善とともに、少しずつ舌の状態も良くなっていくことが期待できますので、焦らず継続的なケアを心がけましょう。
YouTubeでも解説しています。

ご自分の体質にあった
漢方薬を試してみたい方は
ピヨの漢方の漢方相談を
ご利用ください。