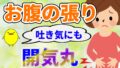こんにちは
どうなさいましたか?

唾液の出過ぎにお困りの方から
質問をいただきましたよ。
「口の中に唾液が溜まって困る」というお悩みを抱えている方は意外と多いものです。特に緊張しやすい方や胃腸の不調を感じている方に見られるこの症状は、日常生活に支障をきたすこともあります。
東洋医学では、唾液の分泌には「押し出す力」と「留めておく力」のバランスが重要だと考えられています。このバランスが崩れることで唾液過多の症状が現れるのです。
今回は、唾液が多くなる原因を東洋医学の視点から解説し、自然な方法で改善するためのアプローチをご紹介します。体の緊張を緩め、本来の健やかな状態を取り戻しましょう。
外見的な特徴とお悩みの症状
- 口の中に唾液が溜まる
- 胃の不調がある
- 唇が乾燥している
- 首や口周りに常に緊張感がある
- 歯の噛みしめがある
- 唾液が溜まった際は飲み物で一緒に流し込んでいる
唾液が多くなる原因とは?
まずは実際に唾液過多でお悩みの方の症状を見てみましょう。
唾液の分泌量が正常に保たれるためには、「唾液を押し出す力」と「唾液を留めておく力」のバランスが大切です。どちらかが過剰になったり、不足したりすると、唾液の分泌に問題が生じます。
この方の場合、胃の不調があることから脾の働きが関係していると考えられます。東洋医学では、脾は消化吸収に関わる重要な臓器とされています。
しかし、唾液が溜まっても飲み物と一緒に流し込めるということは、現在の脾気(脾の働き)自体には大きな問題がないかもしれません。
では何が問題なのでしょうか?
症状を詳しく見ていくと、首や肩回りの緊張感や歯の噛みしめがあることがわかります。東洋医学では、このような体の緊張は「肝気(かんき)」という気の巡りを調整する機能に影響を与えると考えられています。
体の緊張が肝気を旺盛にすると、唾液を押し出す力が強まり、留めておく力を上回ってしまいます。その結果、唾液の分泌量が増えているのではないでしょうか。
さらに、この肝気の偏りが「脾気」を攻撃するようになり、胃腸の不調を引き起こしていると考えられます。また、唇の乾燥は「陰」の不足を示し、これが肝気をさらに煽って唾液を押し出す力を強めている可能性もあります。
ではこの方に、おススメの自然療法を教えて下さい
この症状の改善には、気の巡りを穏やかにし、肝気を巡らせる働きのある漢方薬が効果的です。
おすすめの漢方薬
- 四逆散(しぎゃくさん): 肝気の緊張を緩和し、気の巡りを改善する効果があります
- 大柴胡湯(だいさいことう): 肝気の鬱滞を解消し、消化器系の働きを整える働きがあります
- 抑肝散加陳皮半夏(よくかんさんかちんぴはんげ): 肝気の昂ぶりを鎮め、気の巡りを良くする効果があります
※これらは特定の体質改善に効果が期待できる漢方薬のご紹介であり、必ずしもすべての方に合うものではありません。症状が複雑な場合には、単独では効果がない場合もありますので、当店での漢方相談をご利用ください。
また、日常生活での自己ケアも重要です。歯を噛みしめてしまう方は体が緊張しやすくなりますので、以下のようなセルフケアを取り入れてみましょう:
- 顎の周囲を軽くマッサージして緩める
- 呼吸に意識を向けて体の緊張を緩める
- 横隔膜やおへその周囲を中心に、気持ちの良い範囲でマッサージをする
これらのケアを1日のうちに何度でも、ふと気づいた瞬間に行うことで、自分で緊張を緩める習慣をつけることができます。継続することで、唾液の分泌バランスが整い、症状の改善が期待できますよ。
まとめ
唾液が多くなる症状は、東洋医学的に見ると体の緊張による肝気の偏りが主な原因であることがわかりました。この緊張が唾液を押し出す力を強め、脾気にも影響を与えて胃腸の不調を引き起こしているのです。
改善には、肝気を穏やかにする漢方薬の服用と、日常的な体の緊張を緩めるセルフケアが効果的です。特に顎や横隔膜のマッサージ、意識的な呼吸法は、自分でできる有効な対策となります。
体の緊張を緩めることで、唾液の分泌バランスが整い、口内に唾液が溜まる不快感から解放されるでしょう。ぜひ今日から実践してみてください。
YouTubeでも解説しています。

ご自分の体質にあった
漢方薬を試してみたい方は
ピヨの漢方の漢方相談を
ご利用ください。