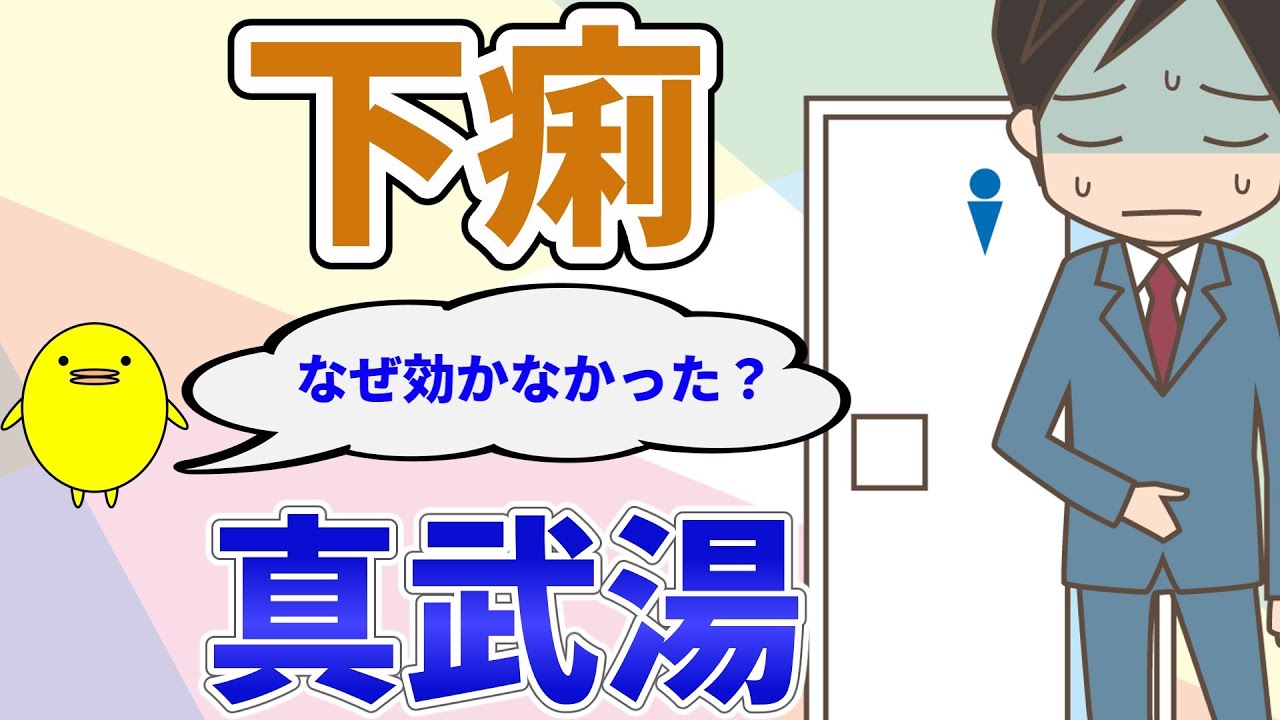こんにちは
どうなさいましたか?

排便異常にお悩みの方から
質問をいただきましたよ
トイレに駆け込む回数が多く、日常生活に支障をきたしていませんか?下痢が続くと、外出先でのトイレ探しに不安を感じたり、仕事や人間関係にも影響したりしますよね。特に「検査をしても異常なし」と言われると、なおさら悩みは深まります。
今回は、1日に何度も下痢になる症状について、東洋医学の観点から原因と対策を探っていきましょう。特に「湿熱」と「肝気の乱れ」という概念に注目して、症状が改善される可能性のある自然療法をご紹介します。
外見的な特徴とお悩みの症状
- 1日に何回も排便がある
- 便はスッキリしない軟便
- 黄色くベタベタした便で便器にくっつく
- 食後はゲップが出る
- 胃の中で水の音が聞こえる
- 腹部膨満感がある
- イライラしやすくなった
- 脂肪肝やコレステロールも上昇している
- 検査では異常が見つからない
- 真武湯や半夏瀉心湯を飲んでも効果がない
- トイレを探す不安から常に落ち着かない
なぜ下痢が続くのでしょうか?
まず注目すべきは便の状態です。黄色っぽくベタベタしていて便器に付着しやすい状態は、東洋医学では「湿熱」が停滞して悪さをしている状態と考えられます。
「湿熱」とは体内に余分な水分と熱がこもった状態で、さまざまな不調の原因となります。
「下痢だからお腹の吸収力が弱っているのでは?」と思われるかもしれませんが、この方の場合は少し違います。健康診断で肥満傾向や脂肪肝、コレステロール値の上昇が見られることから、吸収力の低下が主な原因とは考えにくいのです。
吸収できないために下痢になっているなら、脂肪肝やコレステロール値の上昇といった「吸収過剰」の症状は出にくいはずですね。
肝気の乱れがカギを握る?
東洋医学では、お腹が張るという症状やイライラしやすくなったという精神面の変化から、「肝気」の働きの乱れが関係していると考えられます。肝気とは、気血(栄養)を運搬する役割を担っています。
お腹が吸収した栄養を肝気がきちんと運ぶことができない状態、つまり「吸収と運搬の連携が上手く取れない」ことで下痢が起きていると考えられるのです。
食べたものは「脾気」や「胃気」(消化器系の気)によって運ばれますが、肝気もこのプロセスに大きく関わっています。肝気が乱れると、脾気も胃気も乱れて、腸の正常な蠕動運動(ぜんどううんどう:腸の波打つような動き)ができなくなります。
また、「トイレを探さないといけないため落ち着かない」という不安感も気になるポイントです。肝気は「心気」(精神面の気)によって調整されるため、心気の乱れが肝気の乱れを引き起こしている可能性もあります。これは不安を感じると体が緊張してしまうのと似た現象です。
なぜ漢方薬が効かなかったのでしょうか?
真武湯は体を温めて余分な水分を排出する漢方薬です。半夏瀉心湯は体を温めて脾気を高めながら、余分な熱や水を下向きに引き降ろして解消する漢方薬です。
しかし、これらの漢方薬だけでは肝気や心気の調整には十分踏み込めないため、効果が限定的だったのかもしれません。肝気の乱れが主な原因である場合、それに対応した漢方薬の選択が必要になります。
ではこの方に、おススメの自然療法を教えて下さい
脂肪肝やコレステロール値の上昇が見られることから、まずは食生活の見直しが重要です。以下の点に注意してみましょう:
- 食べ過ぎ・飲み過ぎを控える
- 空腹感がないのに食事を摂らない
- のどの渇きもないのに冷たい飲み物を摂り過ぎない
すでにお腹に十分な栄養がある状態で食べ物を摂ると、体は「もう必要ない」と判断して追い返す形で下痢になります。また、停滞している間に体内の熱によって「煮詰められて」しまい、症状を悪化させることがあります。
このようなお腹の状態になると、ストレスなどの影響をより受けやすくなります。食生活の乱れに心当たりがある方は、まずはそこから改善していくことが大切です。
この症状に効果が期待できる漢方薬
この記事で紹介する方のような「湿熱」と「肝気の乱れ」がある方には、以下の漢方薬が効果を発揮する可能性があります。ただし、これらは一般的な説明であり、個人の体質や症状によって合う漢方薬は異なります。
- 柴胡桂枝湯(さいこけいしとう):肝気の巡りを改善し、ストレスによる消化器症状に効果が期待できます
- 茵蔯蒿湯(いんちんこうとう):湿熱を取り除き、特に黄色い下痢便に効果的とされています
- 四逆散(しぎゃくさん):肝気の滞りを解消し、腹部膨満感やイライラを和らげます
症状が複雑な場合には、単一の漢方薬では効果が現れないこともあります。当店では漢方相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。
まとめ
1日に何度も下痢になる症状は、「湿熱の停滞」と「肝気の乱れ」が原因となっている可能性があります。特に便の状態が黄色くベタベタしている、お腹が張る、イライラしやすいなどの症状がある場合は、この視点から改善を図ることが大切です。
食生活の見直しを中心に、ストレス管理も含めた総合的なアプローチが効果的でしょう。漢方薬を試す場合は、肝気と心気の調整も考慮した処方が必要かもしれません。
自分の体質に合った方法を見つけるためには、専門家に相談することをおすすめします。一人で悩まず、まずは体質改善の第一歩を踏み出してみましょう。
YouTubeでも解説しています。

ご自分の体質にあった
漢方薬を試してみたい方は
ピヨの漢方の漢方相談を
ご利用ください。