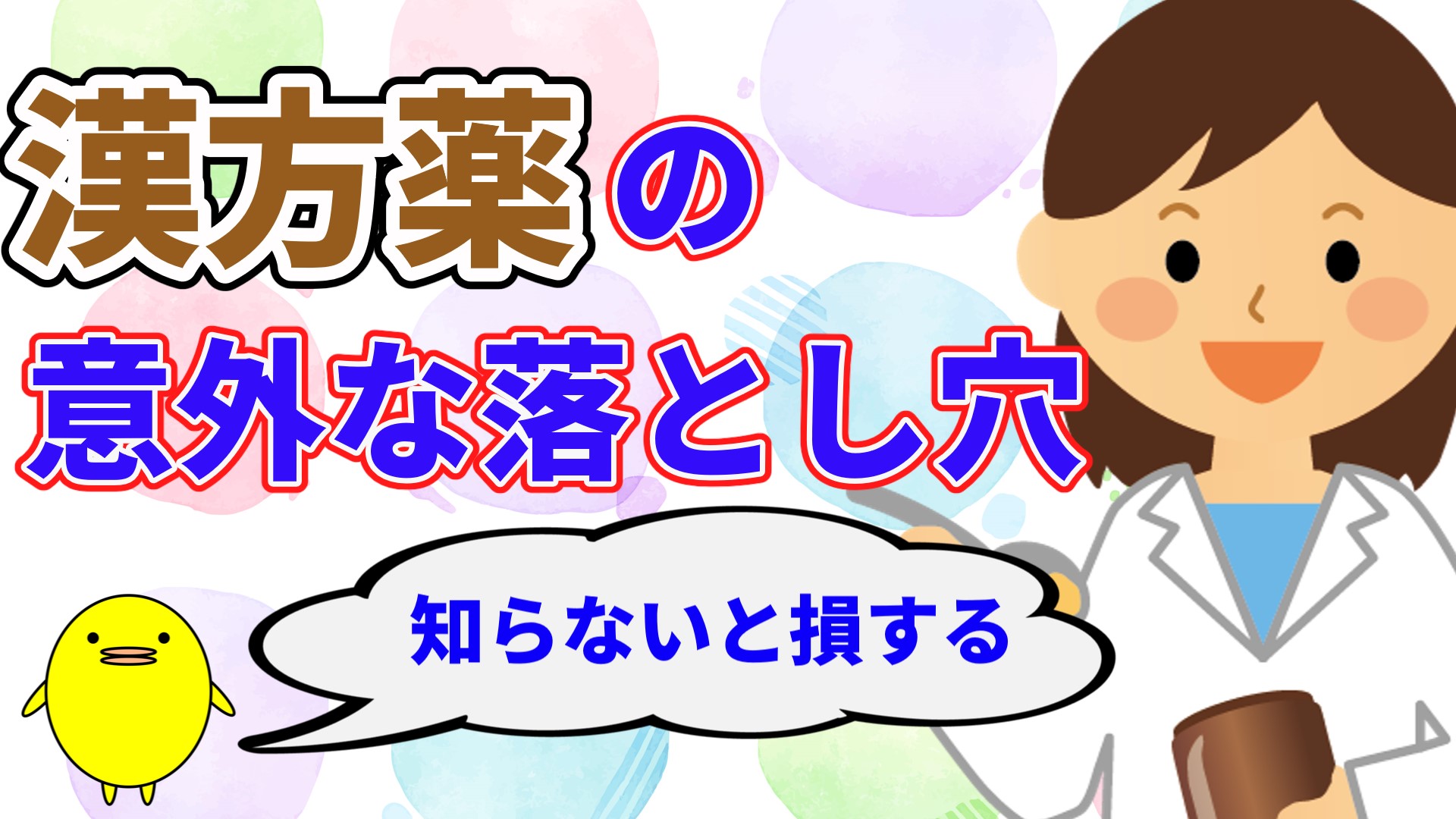こんにちは
どうなさいましたか?

漢方薬の効果にお悩みの方から
質問をいただきましたよ
漢方薬を飲んだことがある方なら、一度は「同じ名前の漢方薬なのに、A社とB社で効果が全然違う」という経験をされたことがあるのではないでしょうか。
実は、漢方薬は名前が同じでも、製薬会社によって内容が大きく異なることがあります。これが効果の違いを生む主な原因なんです。
今回は、なぜ同じ名前の漢方薬でも効果に差が出るのか、その理由を3つの要因に分けて詳しく解説していきますね。漢方薬選びで失敗しないためのポイントもお伝えしますので、ぜひ最後までお読みください。
なぜ同じ名前の漢方薬でも効果が違うのですか?
漢方薬の効果に違いが生まれる理由は、主に3つの大きな要因があります。
それぞれの要因を詳しく見ていくことで、漢方薬の違いを理解できるようになりますよ。
1. 生薬の種類の違い
同じ名前の漢方薬でも、使われている生薬の種類が会社によって異なります。
例えば、A社では9種類の生薬を使っているのに、B社では16種類使われているということがあります。また、一部の生薬が入れ替わっていることも珍しくありません。
生薬にはそれぞれ異なった働きがあります。そのため、生薬が入れ替わっていれば、その目的とする働きも当然変わってしまいます。
具体的な例を見てみましょう:
- A社の製品: 水を穏やかに巡らせながら表層を引き締める働きのある生薬を使用
- B社の製品: 水を勢いよく発散させながら巡らせ、表層でも発散させるような働きのある生薬を使用
このように、全く別の商品のような働きになってしまうことがあります。
2. 生薬の配合比率の違い
基本処方はある程度決まっていますが、各社が微調整している場合があります。
例えば、A社のある製品では4対2対1の比率であるものの、B社では4対3対2の比率であるということがあります。
生薬の配合には意味があります。運ぶ働きをする生薬と、材料を提供する生薬との比率が悪いと、以下のような問題が起こります:
- 材料はたくさん集まっているのに、運ぶ働きは力が足りない
- 運ぶことができなくなって、余計に邪魔をしてしまう
- 効果が悪くなってしまう
3. エキスの抽出方法の違い
煎じ時間や温度、抽出溶媒などの違いで、有効成分の濃度に差が出ます。
生薬によっては、抽出時間が長すぎたりすると、その有効成分がダメになってしまい、初めから入ってないのと同じようになる場合もあります。
実際の例を見てみましょう:
- A社の場合: 生薬成分がしっかりと抽出されているため、体の潤いを補充しながら余分な水分を排除するのにとても重宝する
- B社の場合: 余分な水を排除するのには使えるものの、潤いを補充するのにはあまり役に立ってくれない
このように、使う時を上手く見極めないといけないケースもあります。
漢方薬を選ぶ際の注意点を教えてください
漢方薬を選ぶ際は、以下のポイントを押さえておくことが大切です。
名前が同じでも効果は同じではない
まず、漢方薬は名前が同じでも効果が同じではないということを理解しましょう。
漢方相談などで処方された製品と、市販で見かけた同名の製品は、似て非なるものである可能性があるため、安易に置き換えない方が良いと思います。
価格だけで判断しない
値段が安いからと言って飛びついたはいいが、思ったほどの効果が出ないだけでなく、かえって症状が悪化することもありますので、注意が必要です。
まとめ
同じ名前の漢方薬でも効果が違う理由は、生薬の種類・配合比率・抽出方法の3つの要因によるものです。
漢方薬を選ぶ際は、名前だけでなく、製薬会社による違いを理解し、価格だけで判断しないことが大切ですね。
特に、漢方相談で処方された製品と市販品を安易に置き換えることは避け、専門家のアドバイスを求めることをおすすめします。
適切な漢方薬選びで、より良い健康管理を目指していきましょう。
YouTubeでも解説しています。


ご自分の体質にあった
漢方薬を試してみたい方は
ピヨの漢方の漢方相談を
ご利用ください。