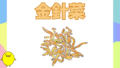こんにちは
どうなさいましたか?

吐き気にお悩みの方から
質問をいただきましたよ
朝食は問題なく食べられるのに、昼食や夕食になると突然吐き気を感じて食事ができなくなる…そんな症状で悩んでいませんか?
さらに不思議なことに、食事を中止すると気分が良くなるというパターンを経験している方も多いでしょう。この症状は単なる胃腸トラブルではなく、東洋医学的な観点から見ると、体内の陰陽バランスの乱れが関係している可能性があります。
今回は、このような時間帯によって変化する消化器症状について、東洋医学の視点から原因と改善方法をご紹介します。この記事を読むことで、あなたの体調不良を改善するための重要なヒントが得られるはずですよ。
外見的な特徴とお悩みの症状など
このような症状がある方には、以下のような特徴が見られることがあります:
- やや痩せ型で神経質なタイプ
- 疲れやすく、ストレスを感じやすい
- 睡眠が浅い、または不足しがち
- 肩こりや頭痛を伴うことがある
主な症状:
- 朝は食欲があるが、昼から夕方にかけて食欲が低下
- 食事中や食後に吐き気を感じる
- 食べるのを止めると気分が回復する
- イライラしやすい、または気分の変動がある
消化器系の基本的な働きとは?
まずは、私たちの消化器系がどのように働いているのかを簡単に説明しましょう。
食べ物は口から入って噛み砕かれた後、食道を通って胃に入ります。そこでさらに細かく分解された後、腸へと送られていきます。腸では体に必要な栄養素が吸収され、全身へと配られる仕組みになっています。
東洋医学では、この消化プロセスを3つの重要な「気」の働きで説明します:
- 胃気:食べ物を受け入れ、分解し、下向きに運ぶ働き
- 脾気:栄養素を吸収して栄養に変え、上向きに運ぶ働き
- 肝気:脾気と協力して栄養を全身に配る働き
これら3つの「気」が協調して働くことで、私たちは食べた物を栄養として取り入れ、不要なものを排出することができます。この3つのバランスが崩れると、様々な消化器症状が現れるのです。
なぜ時間帯によって症状が変わるのか?
朝は問題なく食事ができるのに、なぜ昼から夜にかけて吐き気が生じるのでしょうか?
その鍵は、東洋医学の重要な概念である「陰陽変化」にあります。
陰陽変化とは、**陽(熱や活動的な状態)と陰(水や鎮静を表す性質)**が、一日の中で少しずつ役割を交代しながらバランスを取ることを意味します。通常、昼間は陽が優位になり、夜間は陰が優位になります。
太極図で例えると、夜中の12時頃に陰から陽へと主役が切り替わり、正午にかけて陽の働きが最も強くなります。そして正午を過ぎると、今度は陽から陰へと主役が切り替わり始めるのです。
この陰陽のバランスが正常であれば、時間的な変化があっても体は健康を保てます。しかし、バランスが崩れていると、時間の変化に対応できずに体調不良が現れます。
吐き気が起こるメカニズム
吐き気は体の防御反応です。食べ物の性質が悪い時や、胃腸の働きが弱っている時に、体を守るために起こります。本来下向きに運ぶべき食べ物が、上向きに逆流して口から出そうとする状態と言えるでしょう。
食べるのを止めると気分が良くなるのは、肝気の働きが上手く連携できていない可能性があります。肝気は陰の働きによって、ゆったりとした性質を保つことができます。
しかし、陰が不足している体質の場合、本来陰が活躍すべき昼や夕方になると、肝気の働きが過剰になり過ぎてしまいます。すると肝気の穏やかさが失われ、過剰に上方へ向かう流れが生じ、食事によって胃腸が刺激されると吐き気を催してしまうのです。
ではこの方に、おススメの自然療法を教えて下さい
解説したように、このような症状の主な原因は陰の不足にあると考えられます。そのため、陰を回復させることが改善の鍵となります。
睡眠の質と時間を見直す
陰を回復させるためには、陰の時間帯である夜間に適切な睡眠をとることが最も重要です。夜中の12時前後に陰の勢力が最も強くなるため、できれば22時頃に就寝するのが理想的です。
深夜を過ぎてから就寝する生活が続くと、睡眠時間自体は十分でも、陰の補充効率が低下します。これは人体の中を流れる気の配分とも関係しています。深夜には体の内側を修復するために気が内側を巡りますが、深夜を過ぎると気の配分が外側に向かい始めるためです。
また、睡眠不足はストレスへの耐性を下げ、イライラしやすくなるなど精神的な安定感も失われやすくなります。これによっても肝気の巡りが乱れてしまいます。
早寝早起きのリズムを整えることで、陰の回復を促し、消化器症状の改善につながるでしょう。
食事の工夫
以下のような食事の工夫も効果的です:
- 消化の良い食事を心がける
- 昼食や夕食は量を控えめにし、ゆっくり食べる
- 刺激物(カフェイン、アルコール、辛いもの)を控える
漢方薬による改善
陰不足と肝気の乱れによる症状改善には、以下のような漢方薬が効果的とされています:
- 柴胡加竜骨牡蛎湯(さいこかりゅうこつぼれいとう):精神不安や不眠を伴う消化器症状に効果が期待できます
- 甘露飲(かんろいん):胃熱による不快感や口内炎などの症状に用いられる漢方薬です
- 加味逍遙散(かみしょうようさん):イライラや不安感を伴う消化器症状に効果が期待できます
なお、これらは特定の体質の改善に効果が期待できる漢方薬の一例であり、この方に必ずしも合うわけではありません。症状が複雑な場合には、単独では効果がない場合もありますので、ピヨの漢方での相談をおすすめします。
まとめ:陰陽バランスを整え、健やかな消化機能を取り戻そう
今回は、朝は食べられるのに昼から夜にかけて食事の不調を感じる理由についてお話ししました。
朝は問題ないのに昼から夜にかけて体調が悪くなる原因は、陰の不足と肝気の乱れによるものと考えられます。
解決策として最も大切なのは質の良い睡眠です。早寝を心がける生活習慣への改善が、この症状の改善に大きく貢献するでしょう。
もし寝不足が続いていると感じる方は、今日から少しずつでも早寝を心がけてみてください。小さな習慣の変化が、大きな体調改善につながることがありますよ。
YouTubeでも解説しています。

ご自分の体質にあった
漢方薬を試してみたい方は
ピヨの漢方の漢方相談を
ご利用ください。