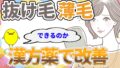こんにちは
どうなさいましたか?

胃腸の調子が悪い方から
質問をいただきましたよ。
梅雨から夏にかけて、なぜか胃腸の調子が悪くなる…そんな経験はありませんか?
カラッとした秋冬は比較的調子が良いのに、湿度が高く蒸し暑い季節になると胃腸トラブルに悩まされる方は実は多いのです。特に便秘と下痢を繰り返す方にとって、この季節の変わり目は要注意。
今回は、「梅雨や夏に胃腸の調子が不安定で困っている」というお悩みについて、漢方の観点から原因と対策を詳しく解説します。季節によって変わる体質と、それに合わせた養生法や漢方薬の選び方についてもご紹介していきましょう。
外見的な特徴とお悩みの症状
- 子どもの頃から胃腸が敏感
- 便秘や下痢を繰り返している
- 秋冬は酸化マグネシウムが効くが、梅雨・夏は効かない
- 冷房が苦手で冷えると軟便や下痢になる
- 生ものやアイスを食べると胃腸の動きが止まる
- 五苓散を飲んだら便秘が悪化した
胃腸不調の原因はどこにある?
まず便秘の根本的な原因は、腸管が正常に動かないことにあります。冷房が苦手で冷えから軟便や下痢になったり、生ものや冷たい食べ物を摂ると腸が動かなくなるという症状は、体の芯にある熱源の弱さを示唆しています。
しかし、生ものやアイスを食べられるということは、ある程度お腹に余裕があるとも言えます。子供の頃から胃腸が敏感とのことですので、食べ物を吸収する働きとそれを運搬する働きの連携が、「気の滞り」などの影響でうまく取れていない可能性があります。
酸化マグネシウムはどのように働いているの?
酸化マグネシウムは、腸内で糞便に水分を呼び込み、それを膨らませる働きがあります。このふくらみが腸管を刺激することで、腸が動き出し排便につながります。
つまり、便を柔らかくする力はありますが、腸管を動かす「スイッチ」が入りづらい状態にあると考えられます。このスイッチが季節によって働き方が変わってくるのです。
なぜ夏は薬が効かないの?
秋冬の季節は、体の気(エネルギー)が内側へと向かう時期です。この時期は体の内側の機能が主体となるため、酸化マグネシウムの働きにより腸管に水が集まりやすくなり、排便のスイッチが入りやすくなります。
一方、梅雨や夏は気が外側に向かう時期。特に夏場は気の力が強まるため、もともと気の滞りがある方は、その滞り感がより強まり、排便のスイッチが入りにくくなります。
さらに、梅雨や夏は冷房や冷たい飲食物で腸管が冷やされ、動きが悪くなりがちです。そのため、たとえ排便のスイッチが入っても、腸管の動きが悪いために便秘が改善しないというケースが考えられます。
五苓散で便秘が悪化した理由は?
五苓散は体を温めて余分な水分を排出する漢方薬ですが、「肝気」の巡りには直接働きかけません。そのため、腸の動きを促すスイッチが入りづらいままです。
また、五苓散の水分排出作用は、酸化マグネシウムが糞便に水分を呼び込む働きと相反するため、結果的に便秘が悪化してしまったと考えられます。
ではこの方に、おススメの自然療法を教えて下さい
漢方薬による対策
この方には、肝気の働きを整える漢方薬が適しています。特定の体質改善(肝気の滞り)に効果が期待できる漢方薬としては、以下のようなものがあります:
- 四逆散(しぎゃくさん):肝気の滞りを改善し、胃腸の動きを促進する効果があります
- 大柴胡湯(だいさいことう):肝気の巡りを良くし、便秘と下痢を繰り返す状態を改善します
- 柴胡桂枝湯(さいことけいしとう):肝気の滞りと冷えの両方に働きかけ、腸の動きを整えます
ただし、これらは一般的な肝気の滞りに対する漢方薬であり、症状が複雑な場合には単独では効果が現れないこともあります。当店では個々の症状に合わせた漢方相談も行っておりますので、お気軽にご相談ください。
生活習慣の工夫
腸管の動きを良くするためには、冷たい食べ物や飲み物を控えることが大切です。冷たい飲食物を最初に受け入れるのは胃や腸管なので、ここが冷やされると腸の動きが悪くなり、便秘の原因となります。
以下の点に注意して生活習慣を見直してみましょう:
- 冷たい飲み物は常温に近い温度にして飲む
- アイスやかき氷などの冷たいデザートは控える
- 生野菜よりも温野菜を中心にした食事を心がける
- 腹部を冷やさないよう、冷房の効いた部屋では腹巻きなどを活用する
- 適度な運動で腸の働きを活性化させる
まとめ
梅雨や夏に悪化する胃腸トラブルは、季節による体内の「気」のバランスの変化と、外的な冷えの影響が大きく関わっています。
特に便秘と下痢を繰り返す体質の方は、肝気の滞りを改善する漢方薬と、冷えを防ぐ生活習慣の両面からアプローチすることが効果的です。秋冬と梅雨・夏で体質の現れ方が変わることを理解し、季節に合わせた対策を取ることが大切です。
自分の体質を知り、それに合った漢方薬や生活習慣を取り入れることで、季節を問わず安定した胃腸環境を作っていきましょう。
YouTubeでも解説しています。

ご自分の体質にあった
漢方薬を試してみたい方は
ピヨの漢方の漢方相談を
ご利用ください。