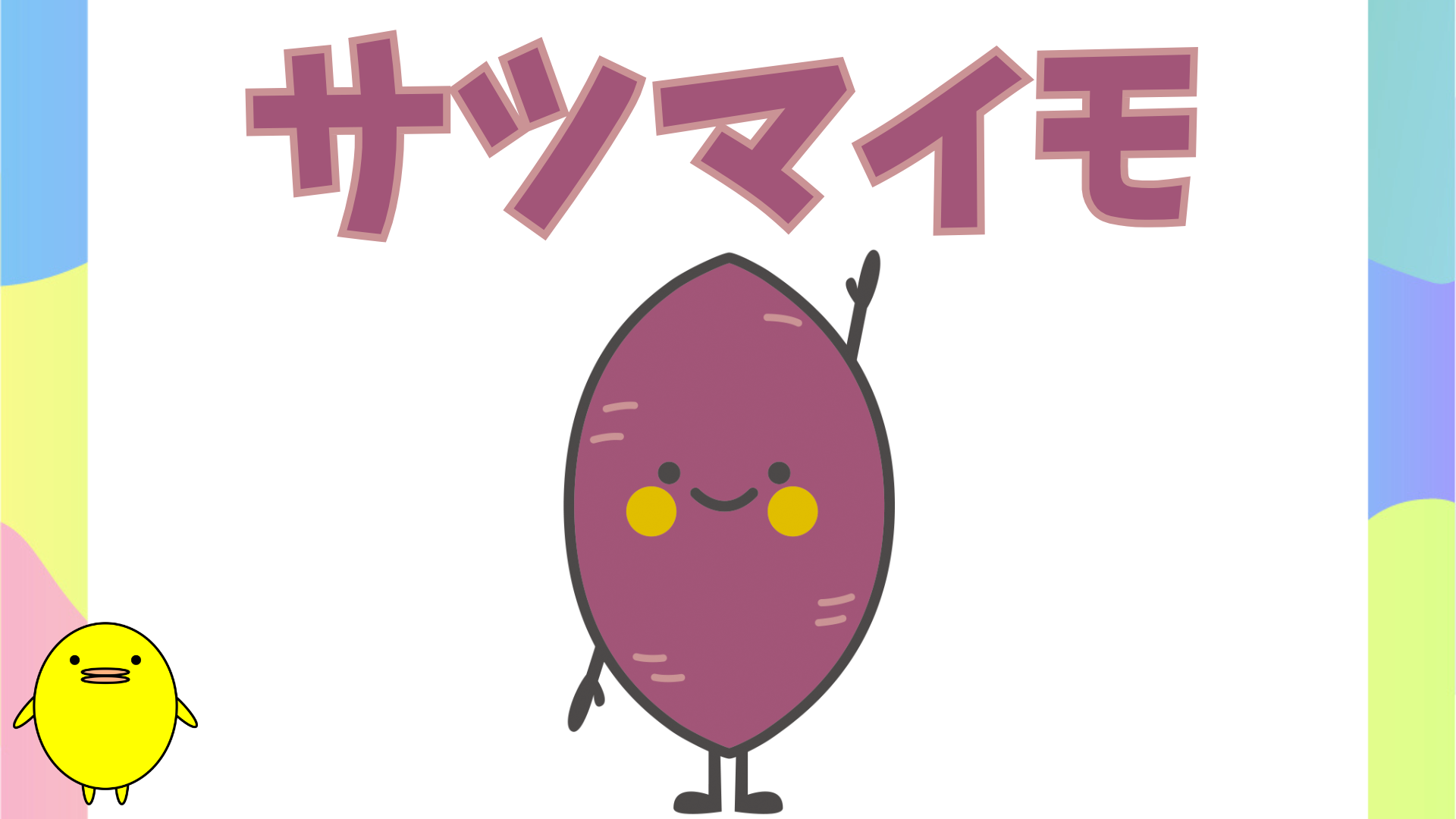皆さん、秋から冬にかけて食卓に登場する機会が増える「さつまいも」。その甘い香りと味わいは多くの人に愛されていますね。
さつまいもは中央アメリカが原産とされています。15世紀末頃、スペインやポルトガルを経由して東南アジアや中国、琉球(現在の沖縄)へ伝わりました。日本には約400年前に琉球から薩摩(現在の鹿児島県)を経て伝わり、その後全国に広がったことから「薩摩芋」と呼ばれるようになりました。
実は、この身近な食材には驚くほど多くの栄養素と健康効果が詰まっています。薬膳の観点からも注目される「薩摩芋」の魅力を、今回は徹底的に掘り下げていきましょう。
さつまいもは日常の食事に取り入れやすく、様々な調理法で楽しめる優れた食材です。その歴史や効能、日々の生活での活用法まで、Q&A形式でわかりやすくご紹介します。
さつまいもとは?その基本情報を教えてください
さつまいも(薩摩芋)は、ヒルガオ科の多年草で、甘味のある根茎(塊根)を食用とする作物です。
性味と帰経
- 性味:平、甘
- 帰経:肺、脾、腎、肝
さつまいもは「平」の性質を持つため、体を冷やしたり温めたりする偏った作用がなく、多くの体質の方に合う食材です。また甘味は、補う働きがあり、全身の気を補います。
主な栄養成分
- 食物繊維:豊富に含まれ、便秘改善に効果的
- ビタミンC:美肌づくりや風邪予防に効果あり
- カリウム:ナトリウムの代謝を促進し、高血圧対策に有効
- ビタミンB群:エネルギー代謝を助ける
- カロテン:抗酸化作用がある(特に紫芋や赤芋に多い)
さつまいもにはどんな健康効果がありますか?
さつまいもには様々な健康効果があります。東洋医学と現代栄養学の両面から見た効能を紹介します。
漢方的効能
- 益気健脾(えっきけんぴ)
- 脾胃の虚弱
- 無気力や疲労感
- 食欲不振の改善
- 和胃調中(わいちょうちゅう)
- 吐き気やげっぷの緩和
- 消渇(のどの渇きが強い状態)の緩和
- 潤腸通便(じゅんちょうつうべん)
- 便秘の改善
- 腸内環境の整備
- 通乳(つうにゅう)
- 母乳分泌促進
現代栄養学から見た効能
- 腸内環境の改善:食物繊維が腸内細菌のバランスを整えます
- 免疫力向上:ビタミンCや食物繊維が免疫機能をサポート
- 血糖値の急上昇を抑える:食物繊維の働きで糖の吸収がゆるやかに
- 美肌効果:抗酸化作用のあるビタミンCが肌の老化を防ぎます
- 心血管保護:カリウムがナトリウムのバランスを整え、血圧管理に役立ちます
さつまいもを食べる際の注意点は何ですか?
さつまいもは多くの方に適した食材ですが、いくつかの注意点もあります。
禁忌・使用上の注意
- 消化性潰瘍や腹部膨満感のある方には不向き
- 消化管に負担をかける可能性があります
- ガスが出やすいので注意が必要
- 対策:陳皮(みかんの皮を乾燥させたもの)や漬け物と一緒に食べると緩和されます
- 空腹時の摂取は胸やけの原因に
- さつまいもの糖分が胃酸分泌を促進し、胸やけを起こすことがあります
- 空腹時を避け、適量を食べるようにしましょう
- 柿との同時摂取は避ける
- 柿に含まれる鞣酸(タンニン)とさつまいもの成分が胃内で反応し、胃石(柿結石)を形成するリスクがあります
- 食べる場合は5時間以上間隔をあけましょう
- 黒斑のあるさつまいもは食べない
- 黒斑菌に感染したさつまいもは食べるのを控えましょう
食べ方の注意点
- 主食と考えて食べすぎない
- さつまいもはカロリーが高く、大量摂取は肥満の原因になります
- 主食の1/3程度を目安に摂取しましょう
- バランスの良い食事の一部として取り入れるのがおすすめです
まとめ:さつまいもを毎日の食事に取り入れよう
さつまいも(薩摩芋)は、東洋医学で「平、甘」の性質を持ち、肺・脾・腎・肝に作用する優れた食材です。益気健脾、和胃調中、潤腸通便、通乳などの効能があり、現代栄養学の観点からも食物繊維、ビタミン、ミネラルが豊富で健康維持に役立ちます。
日常の食事に取り入れる際は、消化性潰瘍がある方や腹部膨満感のある方は控えめに、また柿との同時摂取を避けるなどの注意点を守りましょう。ガスが出やすい性質は陳皮や漬け物と組み合わせることで緩和できます。
さつまいもは焼く、蒸す、煮る、揚げるなど様々な調理法で楽しめ、スイーツ作りにも最適です。その栄養価と多様な食べ方を活かして、ぜひ季節を問わず食卓に取り入れてみてください。健康増進と美味しさを両立できる素晴らしい食材ですよ。
参考文献

ご自分の体質にあった
漢方薬を試してみたい方は
ピヨの漢方の漢方相談を
ご利用ください。