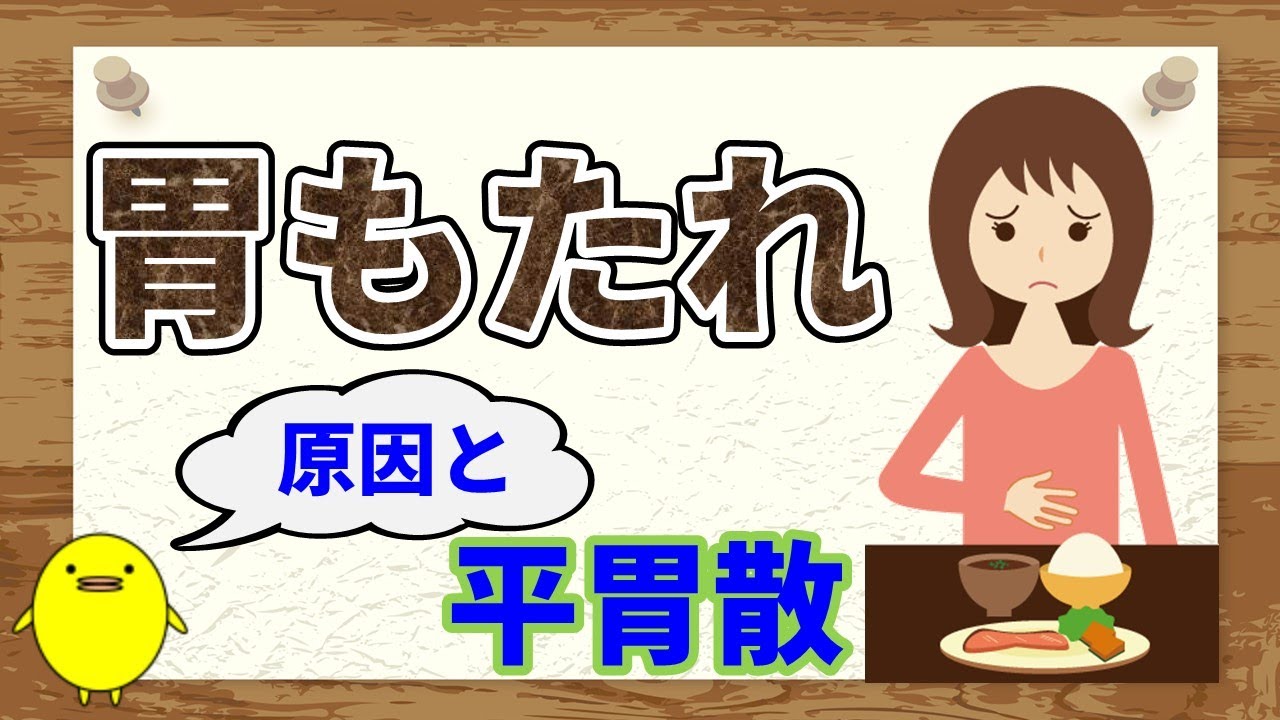こんにちは
どうなさいましたか?

胃もたれにお悩みの方から
質問をいただきましたよ
お腹に違和感があって胃もたれが続いているのに、お腹は空くので食べてしまう。でも食べるとまた具合が悪くなり、胃薬を飲んでも一向に改善しない。そんなお悩みを抱えていませんか?
胃もたれは、単に消化の問題だけではありません。お腹の冷えやストレスが原因で、消化機能そのものが低下している可能性があるのです。
今回は、**胃もたれを改善する漢方薬「平胃散(へいいさん)」**について、中医学の視点から詳しく解説します。なぜ胃もたれが起きるのか、そして平胃散がどのように働いて改善していくのかを知ることで、あなたの不調改善のヒントが見つかるはずです。
どうして胃もたれになってしまうのですか?
食べた物は、腸管の働きによって消化・吸収される場所へと運ばれていきます。そこで体に必要な栄養が吸収され、吸収された栄養は体の上の方へと運び上げられます。必要のなくなった食べ物のカスは、体の外へと排出されていきます。
お腹の働きが正常であれば、この一連の消化・吸収機能がスムーズに行われます。
食べ過ぎによる負担
しかし、お腹の消化・吸収能力を超えて食べ物が一気に入ってくると、処理しきれなくなります。処理しきれない食べ物がお腹に負担をかけ続けると、お腹の働きは低下していきます。
その結果、食べた物を運ぶための蠕動運動(ぜんどううんどう)が悪くなって、胃もたれを感じるようになるのです。
冷やす食べ物による影響
食べた物の性質によっては、お腹にさらに負担をかけてしまうこともあります。
例えば、以下のような食べ物には注意が必要です:
- 緑茶やジュース類
- 生野菜のサラダ
- スムージー
これらの体を冷やす性質のある食べ物を食べ続けていると、腸管を直接冷やしてしまうため、蠕動運動が停滞しやすくなります。
これは、冷たい水の中に手を突っ込んだ状態と同じです。手が温まっていれば力強くモノを掴み運べても、冷たい水で冷やされると手がかじかんで掴めなくなってしまいますね。
では、温度を温かくした緑茶なら大丈夫なのでしょうか?
確かに冷たい状態より直接冷やされることは少ないですが、食べ物の持つ性質そのものが体を冷やすため、体の状態を無視して飲み続けると、段々とお腹は冷やされていきます。
例え緑茶を沸騰させて飲んだとしても、続けて飲んでいると段々と冷やされることになるのです。
ストレスによる影響
別の原因として、ストレスによって腸管の動きが悪くなっている場合もあります。
腸管の蠕動運動は、平滑筋の緊張と緩みの連携によって行われています。東洋医学では、その平滑筋を胃気(いき)や肝気(かんき)が調整していると考えています。
しかし、ストレスを感じる状態が長く続くと、それらの気の働きが不具合を起こして滞ってしまいます。気によって動きを調整されていた腸管も、動きが停滞するようになるのです。
これは、交感神経の働きが過剰になった状態と同様です。交感神経が過剰に働いているときは、体が戦っている状態と同じです。
そのため、以下のような変化が起こります:
- 唾液や胃液の分泌が減る
- 腸管の蠕動運動が鈍くなる
- 膀胱や直腸の括約筋が閉じる
消化機能全体の働きが低下してしまうのです。
唾液や胃液が減れば食べ物の消化はできません。腸管の蠕動運動が鈍くなれば食べた物を運べません。括約筋が閉まっていれば、通行禁止の状態で排出もできません。
この状態が長期間続いているところへ、無理やり食べ物を押し込むとどうなるでしょうか。ただでさえ働きの悪いところへ、無理やり押し込まれた食べ物はいつまでも居座り続けます。これが胃もたれを引き起こすのです。
ストレスと冷えの複合
さらに、ストレスを感じている状態では、体の役に立たない熱が生じることがあります。
そこへ、のど越しの気持ち良い冷やす性質のある飲食物が入ってくると、今度はストレスだけでなく冷やす性質による動きの悪さも加わります。ますますお腹の働きは低下して、胃もたれの状態が悪化することになるのです。
平胃散はどんな漢方薬ですか?
平胃散は、5種類の生薬で構成されている漢方薬です。体を温めながら、停滞している余分な水分を排除して、お腹の働きを助けてくれます。
平胃散に使われている生薬は以下の通りです:
- 蒼朮(そうじゅつ): 体を温めて余分な水分を発散
- 生姜(しょうきょう): 体を温めて気や水分を巡らす
- 厚朴(こうぼく): 気を下向きに降ろして水分を排除
- 陳皮(ちんぴ): 気を降ろして余分な水分を排除
- 大棗(たいそう): 気の材料を補い働きを助ける
- 甘草(かんぞう): 潤いを補いお腹の働きを高める
どうして胃もたれが良くなるのですか?
平胃散の働きを、順を追って見ていきましょう。
ステップ1:停滞を上向きに発散する
まずは、蒼朮と生姜で、お腹の中に停滞している気や水分の巡りを上向きに動かします。
蒼朮は、体を温めながらお腹の中に停滞している余分な水分を、上向きに発散させて排除します。これによって、お腹の働きを応援してくれるのです。
蒼朮の働きによって、停滞している冷えや水分が強力に発散されます。停滞していた気も動き出しますので、痛みの解消にも効果的です。
また、生姜によっても、お腹の中に停滞している気や水分が温められながら上向きに発散されます。生姜には、胃液の分泌を高めて腸管の蠕動運動を促進する働きもあります。これにより、食欲が増進して消化機能が高まります。
ステップ2:停滞を下向きに引き降ろす
今度は、厚朴と陳皮によって、停滞している気や水を下向きに引き降ろしてきて、動きを応援します。
厚朴は、お腹の動きが悪くなったり冷えているような場合に、気の滞りを下向きに引き降ろしながら余分な水分を排除してくれます。
この働きによって、暴飲暴食などでお腹の中に余分なモノが停滞した場合や、ガスが発生したことによるお腹が張ったような状態が解消されます。
また、陳皮によっても、お腹の気を下向きに引き降ろしながら、停滞してドロドロになりかかっている水分も含めて、余分な水分を排除してくれます。
ステップ3:お腹の働きを支える
これら4つの生薬によって、冷えを伴いながらお腹の中に停滞していた気や水分が、上に下にと動きを回復させられて解消していきます。
そして、大棗と甘草によって、綺麗な潤いと気の材料を提供するとともに、お腹の働きを高めることで、これらの働きを支えてくれます。
平胃散の働きのまとめ
もう一度繰り返しますと、以下のような流れです:
- 生姜・蒼朮で、停滞している気や水分を上向きに発散して巡らせる
- 厚朴・陳皮で、下向きに引き降ろしてきて停滞していたものを動かす
- 大棗・甘草で、綺麗な潤いや気の材料を補充してお腹の働きを助ける
これらの働きによって、冷えを伴いながらお腹の中に停滞していた余分な気や水分が動かされていきます。
道路の状態が悪いことが原因で起きていた車の渋滞が、道路状態が回復したことで解消されるように、胃もたれの解消につながっていくのです。
どんなタイプの人に向いている?体質別おすすめコメント
平胃散は、以下のようなタイプの方に特におすすめです。
冷たい食べ物を好む方:冷たい飲み物や生野菜を好んで食べている方で、食後にお腹が張る方に向いています。平胃散が体を温めながら消化機能を助けてくれます。
食後の胃もたれが続く方:食べた後にお腹が張って重苦しい感じが続く方、げっぷが出やすい方におすすめです。停滞している気や水分を動かして、お腹の張りを解消してくれます。
ストレスでお腹の調子が悪くなる方:ストレスを感じると食欲がなくなる、お腹の動きが悪くなると感じる方に適しています。気の巡りを改善して、お腹の働きを回復させます。
余分な水分が停滞しやすい方:舌に白い苔がたくさんついている、口の中がネバネバする、体が重だるい感じがする方に向いています。余分な水分を排除して、体の巡りを良くしてくれます。
ただし、症状が複雑な場合には、平胃散単独では十分な効果が得られないこともあります。体質や症状に合わせた漢方薬の選択が大切ですので、当店でも漢方相談を承っております。お気軽にご相談ください。
まとめ
今回は、胃もたれの原因と平胃散についてお話ししました。
胃もたれを起こす原因にはいくつかありますが、今回は以下をご紹介しました:
- お腹の働き以上に食べてしまう
- お腹の働きを低下させる冷やすものを食べ続けてしまう
- ストレスでお腹の働きが悪くなっているところへ無理やり押し込んでしまう
胃もたれを解決するためには、やはり空腹感を感じるようになってから食べる、喉の渇きを感じてから水分を摂取することなどが大切です。
食欲の弱っている方の中には、栄養のある食べ物を沢山食べないと食欲が回復しないと考えてしまう方もいらっしゃいます。
ですが、体の準備ができていないところへ、無理やり処理に手間のかかる食べ物を押し込まれてしまうと、お腹はさらに弱ってしまいます。
イメージとしては、1週間睡眠もとらずに仕事をした人が、また次の日も会社に出勤して残業をしているような感じです。そんなことをしていたら、体は確実に壊れますよね。
腹も身の内という言葉通り、お腹も体の一部です。無理やり働かせるのは謹んで、お腹からやってくる体の声を聴くようにしてみましょう。
よく噛むことを実践しながら楽しい気持ちで食生活を送るようにしてみると、少しずつ胃もたれも回復してくると思いますのでお試しください。
YouTubeでも解説しています。

ご自分の体質にあった
漢方薬を試してみたい方は
ピヨの漢方の漢方相談を
ご利用ください。