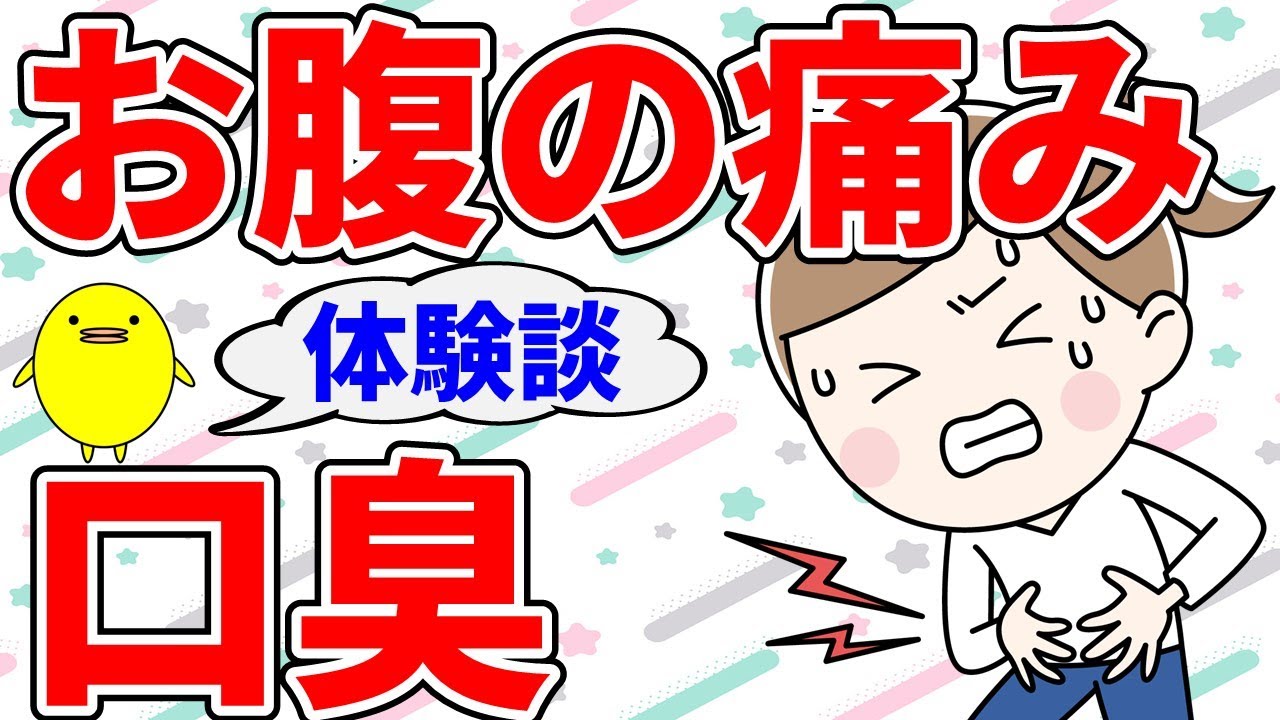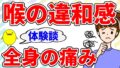こんにちは
どうなさいましたか?

胃腸の痛みにお悩みの方から
質問をいただきましたよ
誰にも理解してもらえない痛みや不快感で悩んでいませんか?検査では「異常なし」と言われても、実際に体験している苦痛は紛れもなく実在するものです。特に胃腸の痛みや口臭の問題は、日常生活の質を大きく下げてしまいます。
今回は、月に1回程度「気が遠くなるほどの胃腸痛」と「口臭」に苦しむ方の症例をもとに、東洋医学的な視点から体質改善のヒントをお伝えします。西洋医学的な検査では原因が見つからないケースでも、東洋医学的な視点から見ると、体のバランスの乱れが見えてくることがあります。
それでは、実際の症例を見ていきましょう。
この方の外見的な特徴とお悩みの症状
外見的な特徴
- 32歳女性
- 身長:151cm
- 体重:32kg
- BMI:14.03(かなりの低体重)
主な症状:
- 月1回程度、気が遠くなるほどの胃腸痛がある
- 胃カメラとMRIでは異常なし
- 芍薬甘草湯を飲んだが効果なし
- 口臭がひどい(歯科では口腔内以外の原因と診断)
- 痩せ型で1日3食食べても太らない(遺伝的要因あり)
- 足のむくみがひどい
- 全身がカチカチに凝っている
- 血圧は上下とも低い
特に胃腸痛については、食事と食事の間隔が長くなってお腹がすいた状態で食事をとると、約1時間後から6時間ほど続く激痛が起こります。痛みのあまり立てないほどで、寝ることができれば翌朝には治まるとのことです。
口臭については食事内容との関連は特に感じられないようです。
それでは、この症状がなぜ起こるのか、東洋医学的な視点から考えてみましょう。
東洋医学から見た胃腸痛の原因とは?
食べ物は口に入って噛み砕かれ、食道を通って胃に入り、細かく分解されてから腸へと送られていきます。そして、腸で必要な栄養素が吸収され、体内で利用できる形に変換されてから全身へと運ばれていきます。
東洋医学では、この一連の消化プロセスを次のように捉えています:
- 胃気 – 食べ物を受け入れ、分解し、下向きに運ぶ働き
- 肝気 – 胃気と協力して腸管の蠕動(ぜんどう)運動を調整する働き
- 脾気 – 必要な栄養を吸収して栄養に変え、上向きに運び上げる働き
これら3つの働きが調和して初めて、食べ物は適切に消化・吸収され、栄養は全身に行き渡り、不要なものは排出されます。しかし、どこかに不具合が生じると、胃腸の不快感や痛みを引き起こすことになります。
では、お腹の機能の不具合について、主な原因を見ていきましょう。
脾気(ひき)の機能低下による問題
脾気の機能が低下すると、食べ物をうまく吸収できなくなります。その結果:
- 食べ物が腸管内に長く留まり、食後の重だるさを感じる
- 血管の弾力性が維持できず、栄養を体の上部へ運べなくなる
- 胃下垂を伴うこともあり、食後の胃もたれを感じる
- 栄養吸収ができないため、痩せて疲れやすくなる
- 無理に食べると下痢になることも
胃気の問題による原因
胃気の問題は主に次のような場合に生じます:
- 辛い物や脂っこい物の過剰摂取
- 過労や寝不足などの生活習慣の乱れ
- ストレスの多い環境
これらにより胃に熱が生じると、胃の潤いが失われ、粘膜分泌が低下して知覚過敏になることがあります。胃の潤いが不足すると腸管の動きも停滞し、以下のような症状が現れます:
- 食欲不振
- 空腹感があっても食べたくない
- 吐き気やしゃっくり
また、過食や飲み過ぎもお腹に負担をかけ、胃気・脾気の機能低下を招きます。脂っこい食べ物や甘いものを長期間摂取すると、お腹の中に「湿熱(しつねつ)」というドロドロしたものが生じ、これが様々な症状の原因となります。
冷たい飲食物の過剰摂取も問題です。胃が冷やされると、まるで冷水に手を入れたときのように「かじかんで」しまい、腸管の動きが悪くなります。重度の冷えでは、お腹が引き絞られるような痛みを感じることもあります。
肝気(かんき)の流れの異常
肝気は脾気によって吸収された栄養を受け取り、全身に巡らせる役割を担っています。この肝気がうまく巡らなくなると:
- 腸管の筋肉が過度に緊張し、滑らかな蠕動運動ができなくなる
- 本来下向きの流れが逆流し、ゲップや吐き気、嘔吐を引き起こす
- お腹の張りや便秘の原因となる
特に強いストレスがあると、肝気の働きが過剰になり、脾気の吸収機能を妨げることで食欲不振や腹痛を生じさせることがあります。
この方の体質の特徴は?
この方の症状から体質を分析すると、以下のような特徴が見えてきます:
- 脾気の弱さ
- 食欲はあるものの、消化吸収力に余裕がない
- 立ちくらみしやすい
- あざができやすい、皮下出血しやすい
- 全身の倦怠感や無力感
- 血圧が低い
- 血の不足
- 髪が細く薄く乾燥している
- 口唇が乾燥しやすい
- 舌の色が白っぽい
- 脾気の持ち上げる力の不足により、月経血が過多になりやすい
- 気血の滞り
- 排便は2~3日に1回と停滞気味
- 月経前に胸が張る
- 生理不順
- 全身がカチカチに凝っている
- イライラしやすく怒りっぽい
- 肩こりがある(上方に向けて気が突き上がる)
- 上下のバランスの乱れ
- 上部:栄養不足で熱だけが上昇し、不安感や口の乾燥
- 下部:水分が充満して下半身のむくみ、帯下が多い
- 尿は少ない(気の滞りにより水分の循環が妨げられる)
- お腹の中の水分停滞と熱の存在
- 胃の中でチャポチャポ音がする
- のどが渇いても飲みたくない
- 口臭(お腹にこもった熱の存在を示す)
この方の場合、食事と食事の間隔が長くなると、腸管を動かす肝気は潤いの不足によってさらに滞りが強まります。そこに食べ物が入ってくると、気の滞りが脾気を妨げて痛みを引き起こし、さらに吸収した栄養物の運搬にも不具合が生じて停滞するため、痛みとなっていると考えられます。
また、お腹に停滞している水分も脾気の働きを妨げ、運搬の妨げとなって痛みを強めていると思われます。
ではこの方に、おススメの自然療法を教えて下さい
この方の体質とお悩みを考慮すると、以下の自然療法がおすすめです:
1. 気の滞りを改善する
運動量の多いお仕事をされているようですが、全身が「カチカチに凝っている」状態は、強い緊張がある証拠です。この緊張がお腹にも強い緊張を生じさせ、熱を生み、腹痛や口臭の原因となる胃熱を引き起こしている可能性があります。
リラックスを心がけた軽いストレッチで緊張をほぐすことをおすすめします。特に就寝前のリラックスタイムに取り入れると効果的です。
2. 食事方法の改善
食事をする際には、ゆっくりと良く噛んで腹八分目を心がけましょう。よく噛むことで体の受け入れ準備が整い、内臓機能も高まって栄養が必要な場所へ送られるようになります。
反対に、よく噛まずに一気に食べると、準備の整っていない体では食べ物が停滞して腹痛を引き起こします。1口につき50回は噛むつもりで、ゆっくり食事を楽しむようにしましょう。
3. お腹のセルフマッサージ
睡眠前のリラックスできる時間帯に(食事の直後は避けて)、みぞおちや臍の周囲を中心に、気持ちいいと感じる程度の強さでお腹のマッサージをするのも効果的です。
このとき、深くゆったりとした呼吸を行いながら、じっくりと手の温かさでお腹のしこりをほぐすようなイメージで行ってみてください。
4. 経絡マッサージ
胃と関係の深い経絡(けいらく)は大腿部の前面や下肢の前面にも通っています。これらの部位もじっくりとマッサージしたり、ストレッチで緩めるようにすると効果的です。
これらの方法を継続して行うことで、お腹の働きが正常に機能しやすくなり、症状の改善が期待できます。
この体質改善に効果が期待できる漢方薬
この体質改善には、以下のような漢方薬が効果を発揮する可能性があります。ただし、これらは特定の体質の改善に効果が期待できる一般的な漢方薬であり、個人の症状や体質によって合う合わないがあります。
- 六君子湯(りっくんしとう) – 脾胃の働きを高め、消化吸収を助ける漢方薬。胃もたれや食欲不振、疲れやすさなどの改善に期待できます。
- 柴胡加竜骨牡蛎湯(さいこかりゅうこつぼれいとう) – 肝気の巡りを改善し、精神的な緊張やストレスから来る症状に対して効果が期待できます。
- 半夏瀉心湯(はんげしゃしんとう) – 胃腸の熱を取り、水分の停滞を改善する働きがあります。胃痛や口臭などの症状に効果が期待できます。
なお、症状が複雑な場合には、これらの漢方薬を単独で使用しても効果が現れないことがあります。当店ではお一人おひとりの体質や症状に合わせた漢方相談も行っておりますので、お気軽にご相談ください。
まとめ:体質改善で胃腸痛と口臭を解消しよう
今回ご紹介した症例のような、検査では異常が見つからないけれど苦しい胃腸痛や口臭でお悩みの方は少なくありません。東洋医学的な視点では、こうした症状は体質の偏りから生じると考えます。
特に、気の滞りと脾気の弱さが根本にある場合、食生活やストレス、生活習慣の乱れなどによって症状が悪化していきます。
自然療法としては:
- リラックスを心がけたストレッチで緊張をほぐす
- 食事はよく噛んでゆっくり食べる
- お腹のセルフマッサージを取り入れる
- 胃と関連する経絡のマッサージを行う
これらを継続することで、体質の改善とともに症状の軽減が期待できます。
YouTubeでも解説しています。

ご自分の体質にあった
漢方薬を試してみたい方は
ピヨの漢方の漢方相談を
ご利用ください。