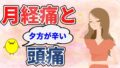水田や小川の泥底でひっそりと暮らすどじょう。日本の食文化に古くから親しまれてきたこの小さな魚は、実は薬膳の世界では貴重な薬膳食材として重宝されてきました。
どじょうは日本全国の平野部の水田や湿地、農業用水路、泥底の流れの緩やかな小川などに広く生息している淡水魚です。
見た目は地味ですが、その効能は驚くほど多彩。今回は、漢方的視点から見たどじょうの魅力と活用法について詳しくご紹介します。健康維持や体調管理にお役立てください。
泥鰌(どじょう)の漢方的な基本情報は?
性味/帰経:
- 性味:平、甘
- 帰経:脾、肺
「性味」とは食材の性質と味わいを表し、「帰経」はどの臓腑に作用するかを示します。どじょうは「平」という穏やかな性質を持ち、「甘」という味わいを持つとされています。また、主に「脾」と「肺」の働きを調整する効果があるとされています。
泥鰌(どじょう)には、どんな漢方的効能があるの?
どじょうには、主に3つの重要な薬膳的効能があります:
1. 補中益気(ほちゅうえっき)
「中気」とは体の中心部のエネルギーのことで、これが不足すると様々な不調が現れます。どじょうはこの中気を補い、活力を高める効果があるとされています。
以下のような症状に効果的です:
- めまい
- 疲れやすさ
- 食欲不振
2. 利水除湿(りすいじょしつ)
体内の余分な水分を排出し、湿気を取り除く作用です。
効果が期待できる症状:
- むくみ
- 黄疸
- 小便不利(排尿障害)
3. 解毒(げどく)
体内の毒素を排出する働きがあります。
効果的な症状:
- 二日酔い
- 皮膚トラブル
- 虚弱体質の改善
中医学では、どじょうには脾と腎の機能を補い、消化不良や食欲不振、腰膝の痛みなどの症状を緩和する効果があるとされています。また、免疫力の向上や創傷の治癒促進にも役立つとされています。
どじょうはどんな料理に活用できるの?
どじょうは様々な料理に活用できる万能食材です。特に漢方的効能を生かした応用例をご紹介します。
日本の伝統的などじょう料理
- 柳川鍋:どじょうとごぼうを甘辛く煮込み、卵でとじた料理。江戸時代から親しまれており、東京・浅草の「駒形どぜう」などが有名です。
- どじょう汁:東日本では醤油や塩で煮る「どじょう汁」が、西日本では味噌汁や卵とじなどが多く見られます。
- 蒲焼き:金沢などでは、どじょうを蒲焼きにして食べる文化があります。
どじょうは身近な魚で生かしたまま維持しやすく、川魚にありがちな臭みもほとんどないため、古くから各地で食用として親しまれてきました。
まとめ:泥鰌(どじょう)を健康維持に活かそう
泥鰌(どじょう)は、日本の水辺に古くから生息する身近な生き物でありながら、優れた漢方的効能を持つ食材です。補中益気(疲労回復・元気増進)、利水除湿(むくみ改善・水分代謝促進)、解毒という3つの主要な効能があり、様々な体調不良の改善に役立ちます。
特に、肝や腎、泌尿器系の健康維持に効果的とされており、日本の伝統的な食文化の中で育まれてきた知恵を現代の健康維持にも活かすことができます。
料理方法も柳川鍋やどじょう汁など多彩で、家庭でも比較的取り入れやすい食材です。ただし、カリウムの多い食材との併用には注意し、持病のある方は専門家に相談した上で取り入れるようにしましょう。
伝統的な知恵と現代の健康観を融合させ、どじょうの持つ自然の力を日々の食生活に取り入れてみてはいかがでしょうか。
参考文献

ご自分の体質にあった
漢方薬を試してみたい方は
ピヨの漢方の漢方相談を
ご利用ください。