日本の春から初夏にかけて黄色い実をつける枇杷(びわ)。
その甘酸っぱい風味は多くの人に親しまれていますが、実は果実だけでなく葉にも優れた薬効があることをご存知でしょうか?
古くから東洋医学では重要な生薬として用いられてきた枇杷には、咳を鎮める効果や胃腸を整える働きなど、様々な健康効果が期待できます。
今回は漢方の視点から見た枇杷の効能や使い方について、わかりやすく解説していきましょう。
枇杷(びわ)とは何ですか?
枇杷(びわ)はバラ科の常緑小高木で、中国東南部が原産とされています。名前の由来は果実が琵琶の形に似ていることに由来します。
性味・帰経
薬膳における枇杷の基本的な性質は以下の通りです:
- 性味:涼、甘、酸
- 帰経:脾、肺、肝
これは枇杷が体を冷やす性質を持ち、甘みと酸味があり、主に脾、肺、肝の経絡に作用することを示しています。
微熱がある方やほてりやすい体質の方に特に適した食材と言えるでしょう。
枇杷にはどのような薬効がありますか?
枇杷には主に4つの重要な薬効があります。それぞれ詳しく見ていきましょう。
1. 潤肺止咳(じゅんぱいしがい)
肺を潤し、咳を鎮める効果があります。特に以下の症状に効果的です:
- 肺の乾燥による咳
- 肺の熱による咳
肺を潤し咳を止め、痰を取り除く効果があります。
2. 生津止渇(せいしんしかつ)
体液を生成し、のどの渇きを癒す効果があります。
- 口の渇き
- 喉の乾燥感
枇杷に含まれるりんご酸やクエン酸などの有機酸が、のどの渇きを癒し、食欲増進にも役立ちます。
3. 降逆止嘔(こうぎゃくしおう)
胃の気を下げ、嘔吐やしゃっくりを止める効果があります。
- 胃気上逆(いきじょうぎゃく)による嘔吐やしゃっくり
- 胃熱による嘔吐
- げっぷ
枇杷はどのように使いますか?応用例を教えてください
枇杷は様々な症状に応じて、異なる方法で使用されます。以下にいくつかの応用例をご紹介します。
肺熱による咳
材料:
- 枇杷 60g
- 水砂糖 30g
- 水 適量
これらを煎じて飲むことで、肺の熱による咳を和らげることができます。
乾燥による肺の咳
材料:
- 枇杷 30g
- 百合の根 30g
- レンコン 30g
- 水と砂糖 適量
これらの材料を蒸して食べることで、乾燥が原因の咳を鎮める効果があります。
枇杷を使用する際の注意点は?
枇杷は優れた薬効を持ちますが、いくつかの注意点があります。
- 過剰摂取すると湿気を助長し、痰を生じさせることがあります
- お腹の機能が弱っている状態で下痢気味の方は控えましょう
- 未熟な枇杷は食べないでください
枇杷は涼性(体を冷やす性質)のため、体が冷えやすい方や胃腸が弱い方は摂取量に注意が必要です。
枇杷の栄養価値と保存方法は?
栄養成分
枇杷は以下の栄養素を豊富に含んでいます:
- 果糖・ブドウ糖
- カリウム
- リン
- 鉄
- カルシウム
- ビタミンA、B、C
特にカロテノイド(プロビタミンA)の含有量が多く、視力維持や免疫力向上に役立ちます。
保存方法
新鮮な枇杷は冷蔵庫で保存し、できるだけ早く消費することをお勧めします。鮮度が落ちると風味や効能も低下してしまいます。
まとめ:枇杷の効能と活用法
枇杷は古くから親しまれてきた果実であり、東洋医学では重要な生薬としても位置づけられています。
主な効能としては:
- 肺を潤し咳を鎮める(潤肺止咳)
- のどの渇きを癒す(生津止渇)
- 胃の気を下げ嘔吐やしゃっくりを止める(降気止嘔)
これらの効果を活かし、症状に合わせた使い方をすることで、健康維持に役立てることができます。
ただし、体質や体調によっては控えるべき場合もありますので、自己判断での過剰摂取は避け、気になる症状がある場合は医師に相談することをお勧めします。
自然の恵みである枇杷の力を上手に取り入れて、健やかな毎日を過ごしましょう。
参考文献
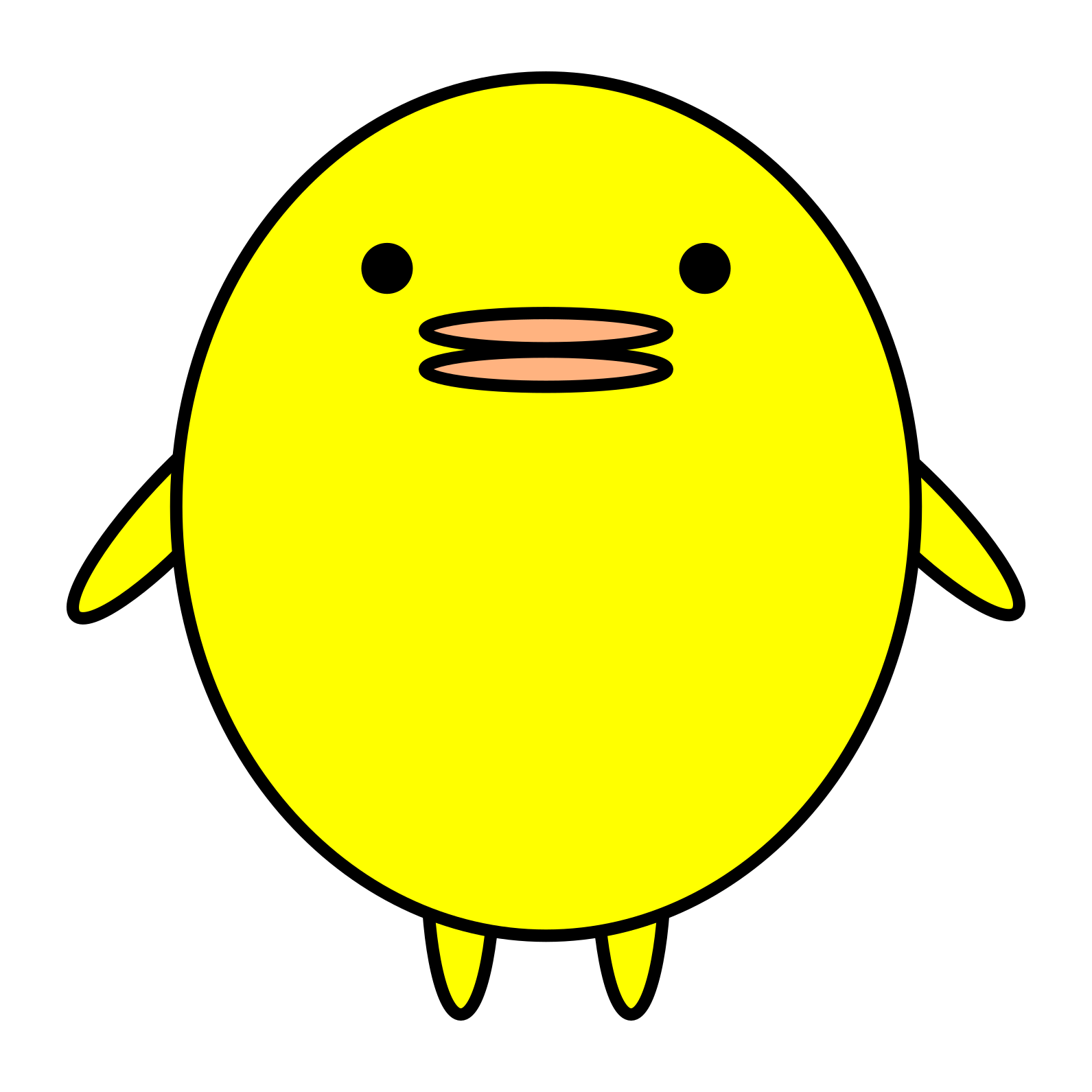
ご自分の体質にあった
漢方薬を試してみたい方は
ピヨの漢方の漢方相談を
ご利用ください。








