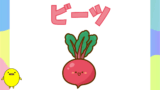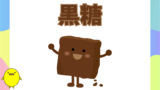こんにちは
どうなさいましたか?

むくみにお悩みの方から
質問をいただきましたよ
日本は四方を海に囲まれた島国のため、年間を通して湿度が高い環境にあります。この高い湿度の影響で、私たちの体は水分代謝が滞りやすくなり、むくみやすい体質になってしまうのです。
特に梅雨時期や夏場、エアコンで冷えた室内にいることが多い現代女性は、体内に余分な水分が溜まりがちですね。そんな時におすすめしたいのが、小豆を使った薬膳料理です。
古くから日本人に親しまれてきた小豆は、実は優れた薬膳食材。今回は時間のある時にゆっくりと小豆を煮て、体に優しい手作りあんこを作ってみませんか?
小豆の薬膳パワーとは?
小豆(あずき)
性味・帰経:
- 性味:甘・酸・平
- 帰経:心・小腸
薬膳効果:
- 利尿除湿:水分代謝を促しむくみを解消する
- 解毒排膿:毒素を取り除き膿を排出させる効果
甜菜(てんさい)
性味・帰経:
- 性味:涼・平・甘
- 帰経:肺・脾・胃・肝・腎
薬膳効果:
- 活血行瘀:血流を促進し血の滞りを改善する
- 清熱解毒:体内の熱と毒素を取り除く効果
- 寛胸下気:胸の詰まりを取り気の流れを良くする
黒糖
性味・帰経:
- 性味:甘・温
- 帰経:脾・胃・肝
薬膳効果:
- 温中補虚:体を温め体力を補う滋養強壮効果
- 緩急止痛:痛みを和らげ筋肉の緊張を緩める
- 活血化瘀:血流を良くし血の滞りを改善する
手作りあんこ&お赤飯レシピ
材料
- 小豆 200g
- 水 600ml
- てんさい糖 80g
- 黒糖 20g
- 塩 少々
つぶあんの作り方
- 小豆を洗います
- 水を入れて煮ます(40分-1時間くらい) ※小豆が水から出ないように、水を足します
- 小豆が指でつぶれるくらい煮ます
- 小豆と煮汁を分けます
- 甘味を3回に分けて入れます
- 1回目:てんさい糖40g
- 2回目:てんさい糖40g
- 3回目:黒糖20g
- 塩を入れます
フードプロセッサーを使ったこしあんの作り方
- 小豆を洗います
- 水を入れて煮ます(40分-1時間くらい) ※小豆が水から出ないように、水を足します
- 小豆が指でつぶれるくらい煮ます
- 小豆と煮汁を分けます(水分が少ないと、早く出来上がります)
- フードプロセッサーで小豆をつぶします ※上手くつぶれないときは煮汁を足します
- 甘味を3回に分けて入れます
- 1回目:てんさい糖40g
- 2回目:てんさい糖40g
- 3回目:黒糖20g
- 塩を入れます
煮汁を使ったお赤飯
- お米をとぎます(今回は3合)
- 小豆の煮汁を入れます
- 3合の線まで水を入れます
- 炊飯します
- ごま塩をふって、出来上がり
どんなタイプの人に向いている?体質別おすすめコメント
この小豆レシピは、特に以下のような体質の方におすすめです:
むくみやすい体質の方 朝起きた時に顔がパンパンになったり、夕方に足がむくんでしまう方に最適です。小豆の利水作用が余分な水分を排出してくれます。
疲れやすい体質の方 慢性的な疲労感を感じている方にもおすすめ。黒糖に含まれるミネラルが疲労回復をサポートします。
冷え性の方 黒糖の温める作用により、体の内側から温まることができます。
消化不良気味の方 小豆は消化に優しく、胃腸の働きを整える効果も期待できます。
気をつけたい点と注意事項
摂取量について
小豆は食物繊維が豊富なため、一度に大量に摂取するとお腹が張る場合があります。最初は少量から始めて、体の様子を見ながら量を調整しましょう。
糖分の摂り過ぎに注意
手作りあんこは市販品より糖分を調整できますが、それでも糖分が含まれていることに変わりはありません。糖尿病の方や血糖値が気になる方は、甘味を控えめにするか、医師に相談してから摂取してください。
アレルギーについて
小豆は豆類のため、豆アレルギーをお持ちの方は摂取を避けてください。
体質による個人差
体質によっては小豆が合わない場合もあります。摂取後に体調不良を感じた場合は、使用を中止して専門家にご相談ください。
まとめ
小豆は日本人にとって身近でありながら、優れた薬膳効果を持つ食材です。特に湿度の高い日本の環境で生活する私たちにとって、むくみ解消の強い味方となってくれます。
手作りあんこなら甘さも調整でき、添加物の心配もありません。小豆の煮汁を使ったお赤飯も一緒に作れば、無駄なく小豆の薬膳パワーを活用できますね。
時間のある休日に、ゆっくりと小豆を煮る時間を作ってみてください。きっとあなたの体も心も、優しく癒されることでしょう。
むくみにお悩みの方、疲れやすい方、冷え性の方に特におすすめしたいレシピです。毎日の食事に取り入れて、内側から美しく健康な体を目指しましょう。
このレシピの動画はこちらから(YouTube)
参考文献

ご自分の体質にあった
漢方薬を試してみたい方は
ピヨの漢方の漢方相談を
ご利用ください。