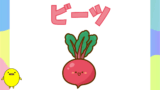こんにちは
どうなさいましたか?

喉の不調にお悩みの方から
質問をいただきましたよ
梅雨から夏にかけて、あんずの美しいオレンジ色が店頭に並ぶ季節がやってきましたね。
この時期は湿度が高く、お肌の調子が気になったり、のどの不調を感じやすい方も多いのではないでしょうか。そんな今の季節にぴったりなのが、旬のあんずを使った薬膳ジャムです。
あんずは中医学では「杏(キョウ)」と呼ばれ、古くから美肌作りと呼吸器系のケアに重宝されてきた食材なんです。甘酸っぱい味わいが特徴的で、お子様からご年配の方まで親しみやすいのも魅力的ですね。
今回は、そんなあんずの薬膳パワーを最大限に活かした、シンプルで美味しいジャムの作り方をご紹介します。美肌が気になる方、季節の変わり目にのどの調子を崩しやすい方には特におすすめのレシピです。
あんずジャムの食材が持つ薬膳パワーとは?
杏(杏子)
性味・帰経:
- 性味:温・甘・酸(微毒)
- 帰経:肺・心・腎
薬膳効果:
- 潤肺止咳:肺を潤し咳や喘息症状を緩和する
- 潤腸通便:腸の乾燥を改善し便通を促進する
- 生津止渴:体内の水分を補い口の渇きを癒す
てんさい糖
性味・帰経:
- 性味:甘、温
- 帰経:脾・胃
薬膳効果:
- 活血行瘀:血の巡りを良くし滞りを取り除く
- 清熱解毒:体の熱を冷まし毒素を排出する
- 寛胸下気:胸のつかえを和らげ気を降ろす
旬のあんずで作る薬膳ジャムのレシピ
材料(作りやすい分量)
- あんず:500g
- てんさい糖:300g(あんずの60%)
作り方
- あんずのへたを取り除く 丁寧にへたの部分を取り除きます
- 洗って水分を拭き取る 流水でよく洗い、清潔なタオルで水分をしっかり拭き取ります
- 種を取り除く あんずを半分に割り、種を取り出します
- 重さを量る 種を取り除いたあんずの正確な重さを量ります
- てんさい糖と混ぜ合わせる あんずの60%の重さのてんさい糖を加え、全体によく混ぜ合わせます
- 煮詰める 中火で20〜30分、木べらでかき混ぜながら煮詰めます 少しとろみがついたら火を止めます ※冷えるとさらに固くなるので、煮すぎないよう注意しましょう
- 保存・活用 清潔な瓶に詰めて保存します パン、ヨーグルト、スコーンなどにお使いください
どんなタイプの人に向いている?体質別おすすめコメント
このあんずジャムは、以下のような体質の方に特におすすめです:
肺燥タイプ(肺が乾燥しやすい方)
空咳が出やすい、のどが渇きやすい、肌が乾燥しがちな方にぴったりです。あんずの潤肺作用が、乾燥した肺に潤いを与えてくれます。
脾胃虚弱タイプ(消化機能が弱い方)
食欲不振、消化不良を起こしやすい方も、てんさい糖の優しい甘さが脾胃の働きを助けてくれます。
気をつけたい点と注意事項
あんずジャムを楽しむ際の注意点をお伝えします:
糖分の摂りすぎに注意
ジャムは糖分が多いため、1日大さじ1〜2杯程度を目安にしましょう。特に血糖値が気になる方は量を調整してくださいね。
湿熱体質の方は控えめに
体に熱がこもりやすく、ベタつく汗をかきやすい方は、甘いものの摂りすぎで症状が悪化する場合があります。少量から試してみましょう。
アレルギーのある方
あんずにアレルギーのある方はもちろん、初めて食べるお子様には少量から様子を見ながら与えてください。
保存期間
手作りジャムは冷蔵庫で約2週間が目安です。清潔なスプーンで取り分け、カビの発生に注意しましょう。
まとめ
今回ご紹介したあんずジャムは、旬の美味しさと薬膳効果を同時に楽しめる一品です。
特に季節の変わり目にのどの調子を崩しやすい方や、お肌の乾燥が気になる方にはぜひ試していただきたいレシピですね。シンプルな材料で作れるので、薬膳初心者の方でも気軽に挑戦できます。
あんずの旬は短いので、見つけたらぜひ早めに購入して、この自然の恵みを存分に味わってくださいね。毎日の食卓に薬膳の知恵を取り入れて、内側から美しく健やかな毎日を過ごしましょう。
このレシピの動画はこちらから(YouTube)
参考文献

ご自分の体質にあった
漢方薬を試してみたい方は
ピヨの漢方の漢方相談を
ご利用ください。