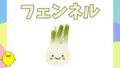こんにちは、ピヨの漢方のブログをご覧いただきありがとうございます。今回は、不整脈やパニック症状、高血圧でお悩みの方の体験談をもとに、東洋医学的な視点からこれらの症状の原因と対策についてご紹介します。
現代社会では、ストレスや生活習慣の乱れなどから、心臓や自律神経系のトラブルを抱える方が増えています。特に不整脈は、突然の動悸や息切れを引き起こし、日常生活に大きな不安をもたらすことがあります。
今回ご紹介するのは、これらの症状に悩む34歳女性の事例です。東洋医学の観点から見た体質の特徴と、自然療法によるアプローチ方法をお伝えしていきます。
この方はどのような症状でお悩みなのでしょうか?
まずは、この方の外見的な特徴とお悩みの症状についてご紹介します。
外見的な特徴とお悩みの症状
- 34歳の女性
- 身長:165cm
- 体重:51kg
- BMI:18.73
主な症状:
- 不整脈(上室性期外収縮と診断)があり、元々心室中隔欠損があるが手術はしていない
- パニック症状があり、買い物中のレジに並んでいると倒れそうになる
- 高血圧気味で、少し動くだけでも上が145になる
- 慢性的な貧血があり、鉄剤を服用中
この方は、赤ら顔で、舌が厚ぼったく赤い色をしており、手や足にむくみがあるといった特徴があります。また、5年前にインフルエンザにかかってから不整脈が気になり始め、出産後から高血圧気味になったとのことです。
不整脈の原因とは?東洋医学的な視点から
不整脈は、心臓の拍動リズムが崩れてしまう症状です。その原因には、心臓自体に物理的な異常がある場合と、心臓に物理的な異常はないものの働きに異常が起きる場合があります。
東洋医学では、心臓をコントロールしているのは「心気」と考えます。心気の異常には大きく分けて:
- 心気のパワー不足
- 心気の働きの過剰
- 中枢からの命令を伝える働きの不具合
などが考えられます。
心気が不足すると、心臓のポンプ機能が低下し、十分な血液を送り出せなくなるため動悸などが現れます。逆に、心を穏やかにする「冷却水」としての潤いが足りなくなると、オーバーヒートした車のように心の熱を制御できなくなり、過剰に働いて不整脈となります。
また、心臓という筋肉をコントロールしているのは、脳からの命令を伝える肝気です。肝気の巡りが不調を起こすと、中枢からの命令が心臓へ正しく届かず、不整脈になることがあります。
この方の体質の特徴は?
この方の症状から体質の特徴を探ってみましょう。
赤ら顔、舌の色も赤い、不眠になりやすい、夢をよく見る、寝つきが悪いなどから、心のある身体の上部で熱が過剰になっているようです。
しかし、手足が冷える、舌の苔が白く薄いことから、体全体が燃え盛るように熱くなっているわけではないようです。
体の中の潤いの状態を見ると、舌が厚い、脚や手にむくみがある、汗が出やすい、口がねばつく、頭が重く感じる、喉に何かが引っかかる感じがするなどから、動きの悪い水分が体のさまざまな部位に停滞している様子がうかがえます。
一方で、夜間の喉の渇き、熱っぽさ、筋肉の痙攣、目の疲れや乾燥、抜け毛、慢性的な貧血などは、体を冷却したり体を作るための潤いが不足していることを示唆しています。
気の様子を見ると、痞える感じ、体のあちこちの痛み、喉の違和感、イライラや怒りっぽさ、生理前後の症状悪化などから、気の巡りが順調ではないことがわかります。これが便秘の原因にもなっているようです。
この方の不整脈・パニック症状・高血圧の原因
ここまでの情報から、この方の症状は単なる心気の不足によるものとは考えにくいです。もし心気が著しく不足していれば、全身の倦怠感や無力感があり、顔色も舌の色も血の気がなくて白っぽくなっているはずだからです。
この方の場合、気の巡りの悪さや潤いの不足がベースにあり、それが原因となって体を少し動かしただけでも体内に熱がこもり、その邪熱が過剰に心臓の働きを煽っていると考えられます。
さらに、耳の聞こえにくさ、腰痛、夜間尿、インフルエンザ罹患後から症状が気になり始めたことなどから、腎気の不調も関係していると思われます。
腎気は体の芯部に存在し、身体全体の熱と潤いの基となるものです。心気と腎気はお互いに熱と潤いをやり取りする関係にあります。
心気から提供された熱が腎の陽気を温め、その熱によって腎陰が温められて上昇し、心の熱を冷ます潤いとなります。ところが、冷却水となる腎陰が不足していると、熱が蓄積していき、ある段階で腎陽が深部に留まれなくなり、急激に上昇します。
この熱の上昇が心臓の働きを乱すと不整脈や動悸となり、脳の働きを乱すとパニック障害となります。これを引き起こすきっかけの一つが気の巡りの悪さです。気が滞ると熱がこもり、その熱が腎陽を煽って急上昇させます。
ではこの方に、おススメの自然療法を教えて下さい
この方の場合、深い部分でのバランスの崩れがあるため、それを整える必要があります。
- 昼夜のバランスを整える
- 昼間は適度に活動し、心も体ものびのびとさせましょう
- 夜は早めに照明を暗くし、過剰な心の熱を穏やかにする
- 眠れなくても早めに布団に入り、心身を落ち着ける
- 呼吸法の実践
- 吐く息を長めにする
- 臍の下の丹田や足の裏に意識を向ける
- 特に足の裏の「湧泉」に意識を集中すると、頭に上がった熱を引き下ろし、血圧を下げる効果が期待できます
- 無理のない生活リズム
- 家事も含めて働き過ぎや頑張りすぎない
- 過度の活動は腎の潤いを消耗させる
- 夜はのんびり過ごし、体に無理をさせない生活を心がける
この体質改善に効果が期待できる漢方薬
以下は、こうした体質の改善に効果が期待できる漢方薬の例です。ただし、これはあくまで一般的な情報であり、この方個人に処方するものではありません。
- 柴胡加竜骨牡蛎湯(さいこかりゅうこつぼれいとう):精神不安や動悸、不眠などに効果があり、気の巡りを改善します
- 滋陰降火湯(じいんこうかとう):腎陰虚による熱症状を鎮め、上昇した熱を下げる効果があります
- 天王補心丹(てんのうほしんたん):心と腎のバランスを整え、不安や動悸、不眠に効果があります
症状が複雑な場合には、単独の漢方薬では効果が現れにくいこともあります。ピヨの漢方では個々の体質や症状に合わせた漢方相談を行っていますので、お気軽にご相談ください。
まとめ
今回ご紹介した事例は、不整脈・パニック症状・高血圧という一見別々の症状に見えるものが、東洋医学的には「気の巡りの悪さ」「腎陰の不足」「腎陽の上昇」という一連のメカニズムで説明できることを示しています。
特に注目すべきは、インフルエンザ罹患が体の深部である腎気のバランスを崩し、その後の症状発現のきっかけになったという点です。ウイルス感染後の体調不良が長引くケースでは、このような東洋医学的な視点も参考になるかもしれません。
日常生活では、無理をせず、昼夜のリズムを整え、適度な活動と十分な休息のバランスを取ることが大切です。特に、夜間は心身を落ち着かせる時間をしっかり確保しましょう。
YouTubeでも解説しています。

ご自分の体質にあった
漢方薬を試してみたい方は
ピヨの漢方の漢方相談を
ご利用ください。