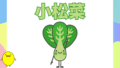こんにちは
どうなさいましたか?

過食と便秘にお悩みの方から
質問をいただきましたよ
便秘でお悩みの方は多いですが、特に「満腹感を感じにくい」「過食してしまう」という症状を伴う便秘は、単に食物繊維を増やすだけでは改善しにくいケースが少なくありません。
東洋医学では、便秘を「気血水」のバランスの乱れとして捉え、体質に合わせた対策を考えます。今回は、満腹感を感じにくく過食してしまう方の便秘について、東洋医学的な視点から詳しく解説していきます。
このブログでは、実際の相談事例をもとに、体質分析と自然療法のアプローチをご紹介します。ご自身の症状と照らし合わせながら読んでいただければ幸いです。
この方はどんな症状でお悩みですか?
まずは、今回ご相談いただいた方の症状をご紹介します。
外見的な特徴とお悩みの症状
- 45歳の女性
- 身長は151cm
- 体重は75kg
- BMIは32.89
主な症状:
- 満腹感をあまり感じず過食してしまう
- 断食3日で便が自力で出なくなり、浣腸に頼るようになった
- 顔色は黒ずみがち
- 髪の毛は乾燥している
- 舌は厚ぼったく、舌先に赤みが強い
- 舌の苔は水っぽく、バターを塗ったような状態
- 肩こりがある
- 静脈瘤がある
- 月経前に胸が張る
- 胸が張って苦しい時がある
- 不安感が強い
- 目が疲れやすく乾燥しやすい
- 口が粘る感じがある
- 足やふくらはぎに浮腫みがある
- 排尿の回数や量が少ない
便秘はどうして起こるのでしょうか?
便秘の仕組みを理解するために、まずは正常な排便の流れを確認してみましょう。
口から入った飲食物は胃で消化され、腸管の蠕動運動(ぜんどううんどう)によって運ばれていきます。体に必要な栄養素が吸収された後、残ったものは大腸で水分が吸収され、最終的に便として排泄されます。
この過程で重要なのが、東洋医学でいう「胃気」による腸管の蠕動運動です。便を体外へ排出するためには、腸管が正しく下向きに動く必要があります。
さらに、排便には以下の要素が関わっています:
- 肝気:筋肉の微妙な調整
- 腎陽:腸管の動きの原動力
- 肺気:呼吸の押し込め(いきみ)の調整
- 腎気:出口の開閉の調整
これらの共同作業がうまく機能しないと、腸管の蠕動運動が停滞して便秘になります。
現代生活と便秘の関係
現代の生活習慣は便秘を引き起こしやすい環境を作っています:
- デスクワークで座っている時間が長い
- 歩く機会が減っている
- ストレスが多い
- スマホやパソコンの長時間使用で気や熱が頭部に集中する
これらの要因により、本来下向きであるべき気の流れが上向きになり、腸管の蠕動運動が乱れやすくなっているのです。
この方の体質の特徴は?
この方の症状から体質を分析してみましょう。
まず気血の巡りに関しては、肩こり、静脈瘤、黒ずんだ顔色、月経前の胸の張りなどから、気血の巡りが滞っている状態がうかがえます。
興味深いのは、体の上部と下部で異なる症状が見られることです:
- 体の上部:髪の毛の乾燥、目の乾燥、不安感の強さなど、乾燥や熱の症状
- 体の下部:足の浮腫み、口の粘り気など、水分の停滞の症状
舌の状態(厚ぼったく、べたっとした苔、舌先の赤み)からも、体内の水分代謝が悪く、体の上部には熱が過剰になっていることがわかります。
さらに、BMIの値や月経血量の状態から、全身が乾燥しているわけではなく、水分の偏りがあることが推測されます。この方は寒がりで静脈瘤もあることから、体内の気の流れの悪さが関係しているようです。
また、排尿の回数や量も少ないことから、水分代謝にも問題がありそうです。
尿の生成と水分代謝の関係
水分代謝について簡単に説明しましょう。
体内に取り込まれた水分は、体の芯部の熱によって温められ、上部へと向かいます。その後、肺気の作用で下向きに流れを変え、体の各部を潤します。
余った水分のうち、再利用できるものは体内に残り、不要なものは膀胱へと向かって尿として排出されます。
水の巡りに勢いがないと、体内のあちこちで水分が滞留し、排尿がスムーズに行われなくなります。また、水分が体の上部で停滞しても同様の問題が生じます。
この方の体質分析
この方の症状から考えると、体の芯部の熱源が不足していると考えられます。これは、喉の渇きから来る過剰な水分摂取によって圧迫されている可能性があります。
これはお風呂に例えるとわかりやすいでしょう。お風呂の水が適量でも、火力が弱いと上部は熱くなっても下部は冷たいままになります。これは循環が弱くなっている状態と同じです。
この体質的な特徴によって、以下のような悪循環が生じています:
- 体の下部に水分が停滞し、足に浮腫みが出る
- 上部には水分が十分に届かず、髪や目の乾燥が起こる
- 脳の働きを調整する心気が不安定になり、不安感が強まる
- 気の滞りが生じ、胸の張りや腹部の不快感、生理不順などにつながる
- 気の滞りと冷えが合わさり、腸管の動きが悪化する
さらに、上部に起きている熱や乾きが喉の渇きを生み、水分摂取が増えます。また、満腹感をあまり感じないことから、胃熱の状態になっていると考えられます。
胃熱の状態とは?
胃熱とは、体に役立たない熱が胃に影響を与え、胃の消化機能が過剰になった状態です。
胃熱になると、異常な食欲が生じ、体が必要としない量の食物を摂取してしまいます。また、体内の熱を冷ますために冷たいものを欲しがるようになりますが、過剰な冷たい水分摂取は腸管をさらに冷やし、便秘を悪化させる原因になります。
さらに、胃腸に熱が溜まると腸管の潤いが失われ、胃気の下向きの働きが阻害されるため、便秘が起こりやすくなります。
この方の状態をまとめると
この方の状態を整理すると:
- 体の下部:動きの悪い水分が充満して浮腫みを生じている
- 背景には芯部の冷えや気の滞りがある
- 体の上部:必要な潤いや血が届かず、熱や乾きの症状が出ている
- これらの動きの悪さが腸管の蠕動運動にも影響している
- 上部の余分な熱が胃腸に影響し、喉の渇きや満腹感の欠如を引き起こしている
- 過剰な水分摂取や食事量が腸管の動きをさらに圧迫している
ではこの方に、おススメの自然療法を教えて下さい
満腹感をあまり感じずに過食してしまうという状態ですので、まずは食生活の改善から始めることをおすすめします。
水分摂取の見直し
体の芯部の熱に対して水分が多すぎると、水の巡りが悪くなり、腸管の動きも滞ります。
熱中症の心配がない季節では、喉の渇きを感じてから少量の水を飲み、様子を見るようにしましょう。しばらくしても喉が渇いていたら、また少し飲むという方法で、一気に大量の水を飲まず、少量ずつこまめに飲むことをおすすめします。
また、冷たい飲み物は控えるようにしましょう。冷たいものは体を冷やし、腸の動きを鈍らせます。
食事の取り方の改善
空腹感は体がエネルギーを必要としているサインですので、食べることは大切です。ただし、食べ方に工夫が必要です:
- 昔ながらの和食を中心に
- よく噛んで食べる
- 腹八分目を心がける
- 一気に食べず、ゆっくり食べる
早食いをすると満腹感を感じにくくなり、一気に体内に入った食べ物を体が処理しきれず、脂肪として蓄積されやすくなります。これにより満腹感を感じさせるホルモンも出にくくなり、悪循環に陥ります。
また、辛いものや味の濃い食べ物は胃に余分な熱を生じさせ、異常な空腹感を引き起こしたり、腸管の潤いを奪ったりする原因になりますので、控えめにしましょう。
適度な運動を取り入れる
無理のない範囲で体を動かすことで、全身の気血の巡りが良くなり、ストレス解消にもつながります。運動不足を感じている方は、軽い散歩やストレッチから始めてみましょう。
リラックスタイムの確保
腸管が活発に動くためには、副交感神経が優位になっていることが重要です。心と体をリラックスさせる時間を作りましょう。
具体的には:
- 軽いストレッチの後に仰向けになる
- お腹を軽くマッサージする
- 吐く息を長めにした呼吸法を意識する
このようなリラックスした時間を持つことが便秘解消には大切です。
おすすめの漢方薬
この体質の改善に効果が期待できる漢方薬をいくつかご紹介します。なお、これらは一般的な情報であり、個人の症状に最適な漢方薬ではない可能性があります。
- 麻子仁丸:腸の蠕動運動を促し、便通を改善する働きがあります。
- 桂枝加芍薬湯:腹部の張りや痛み、筋肉の緊張を和らげる効果があります。
- 半夏瀉心湯:胃熱を冷まし腸の働きを整え、消化機能を整える効果があります。
症状が複雑な場合には、これらの漢方薬を単独で使用しても十分な効果が得られないことがあります。ピヨの漢方では個人の体質や症状に合わせた漢方相談を行っていますので、お気軽にご相談ください。
まとめ
今回は満腹感を感じにくく過食してしまう方の便秘について、東洋医学的な視点から解説しました。
この方の場合、体の芯部の熱源不足による水分代謝の乱れが根本にあり、それが胃熱や気の滞りを引き起こし、便秘につながっていると考えられます。
自然療法としては:
- 水分摂取の方法を見直す
- 食事の取り方を工夫する
- 適度な運動を取り入れる
- リラックスタイムを確保する
これらの対策を日常生活に取り入れることで、症状の改善が期待できます。
YouTubeでも解説しています。

ご自分の体質にあった
漢方薬を試してみたい方は
ピヨの漢方の漢方相談を
ご利用ください。