みなさん、こんにちは。サラダの定番として食卓に並ぶレタスですが、実はその歴史は古く、4500年前の古代エジプトの壁画にも描かれているほど長い間人類と共にあった野菜なんです。
日常的に食べているレタスですが、中医学では「涼性」の食材として珍重され、様々な健康効果があるとされてきました。シャキシャキとした食感だけでなく、体の中から健康をサポートする力を持っているんですね。
今回は、そんな身近なレタスの秘密を中医学の視点から掘り下げ、Q&A形式でわかりやすくご紹介します。毎日の食卓に取り入れて、レタスの効能を最大限に活かしてみませんか?
YouTubeでも解説しています。
レタス(チシャ)とは何ですか?
レタスは、キク科アキノノゲシ属の一年草または二年草で、野菜として世界中で広く利用されています。原産地は地中海沿岸から西アジアにかけての地域とされています。
日本には奈良時代に中国を経由して伝わり、「チシャ(萵苣)」として栽培されていました。当時の品種は現在のリーフレタスに近い非結球性で、葉を下から順に摘み取る「掻きチシャ」として利用されていたんですよ。結球性のレタスが一般的になったのは明治時代以降で、西洋から導入されたものです。
レタスの基本情報と栄養価は?
性味/帰経
- 性味:涼、苦、甘
- 帰経:胃、腸
レタスは95%以上が水分で、ビタミンやミネラル、食物繊維などをバランスよく含んでいる低カロリーな食材です。特にビタミンAやビタミンK、葉酸を豊富に含んでいます。
サラダの定番として生食されるほか、サンドイッチや炒め物、スープの具材としても広く利用されています。低カロリーで食物繊維も豊富なため、ダイエット中の方にもおすすめの野菜ですね。
切り口から出る白い液体には「ラクツカリウム」と呼ばれる成分が含まれており、これが中医学的な効能にも関係しています。
中医学から見たレタスの薬効は?
中医学の古典によれば、レタスは「熱毒を解し、酒毒を消し、渇きを止め、大小腸を利する」と記されています。
具体的な薬効としては以下のようなものがあります:
- 体内の余分な熱を取り除く効果:レタスの涼性は体内の余分な熱を冷まし、炎症を抑える働きがあります
- 水分代謝の促進:むくみの改善や利尿作用に役立ちます
- 食欲増進効果:シャキシャキした食感は食欲を増進させます
- ストレス緩和:レタスに含まれる成分には鎮静作用があり、イライラを和らげます
- 鎮痛・催眠効果:レタスに含まれるラクツカリウムには、軽い鎮痛効果や催眠効果があります
- コレステロール低下:血中コレステロール値を下げる効果があるとされています
- 腸内毒素の除去:便秘予防や腸内環境の改善に役立ちます
レタスの効果的な活用レシピは?
レタスの効能を活かした食療法としてレシピをご紹介します:
1. 【ダイエット用】レタスとクルミの炒め物
材料:
- レタス 1個
- クルミ 100g
- オイスターソース 大さじ1.5
- 油 大さじ3
作り方:
- レタスを洗って水気を切ります
- クルミを弱火で乾煎りし、火が通ったら粗く砕きます
- 強火でレタスを約1分間素早く炒め、オイスターソースを加えます
- 弱火に変えて約3分間煮ます
- レタスを器に盛り、砕いたクルミをかけて完成です
このレシピは単なる料理としてだけでなく、レタスの持つ薬効を活かした食療法としても機能します。ぜひ試してみてくださいね。
レタスを食べる際の注意点は?
レタスは多くの人にとって安全な食材ですが、いくつか注意点もあります:
- 過剰摂取に注意:レタスには鎮静作用があるため、大量に摂取すると眠気を誘う可能性があります
- 体質に合わせた摂取:体質が「寒」の方(冷え性の方など)は、大量摂取を避けましょう
- 消化不良の方は注意:生で食べると消化不良を起こすことがあります。その場合は軽く炒めるなどの調理をしてから食べるとよいでしょう
- アレルギー反応:まれにレタスアレルギーがある方もいますので、症状が出た場合は摂取を中止してください
まとめ:日常に取り入れたいレタスの効能
レタスは単なるサラダの具材だけではなく、中医学的に見ても様々な効能を持つ優れた食材です。体の余分な熱を取り、水分代謝を促進し、ストレスを和らげる効果があります。
特に夏場の暑さ対策や、むくみが気になる方、ストレスでイライラしている方におすすめの野菜と言えるでしょう。
毎日の食事にレタスを取り入れる際は、単にサラダだけでなく、炒め物やスープなど様々な調理法を試してみることで、より効果的にレタスの恩恵を受けることができます。
シャキシャキとした爽やかな食感とともに、レタスの持つ中医学的な効能も味わってみてはいかがでしょうか?
参考文献
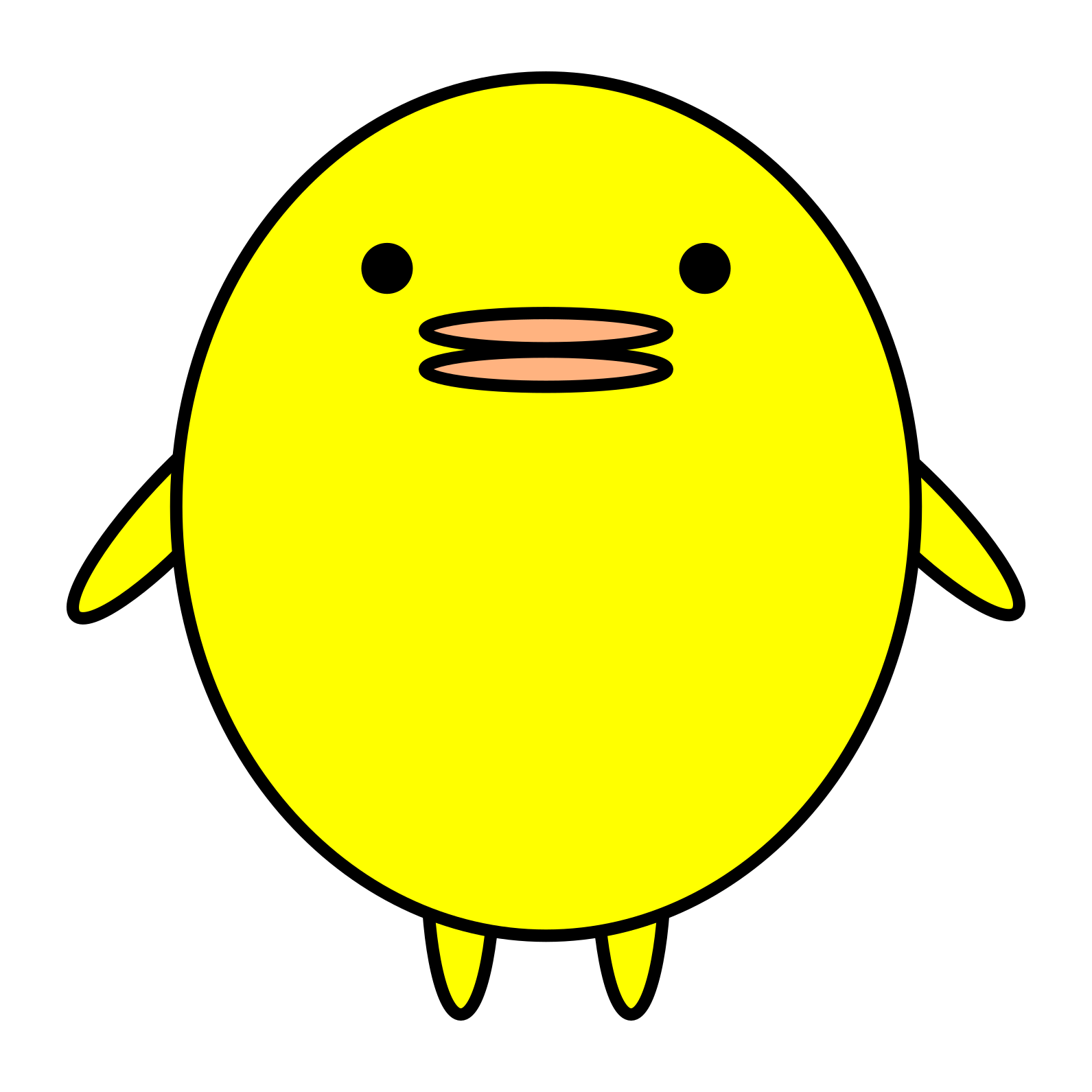
ご自分の体質にあった
漢方薬を試してみたい方は
ピヨの漢方の漢方相談を
ご利用ください。









