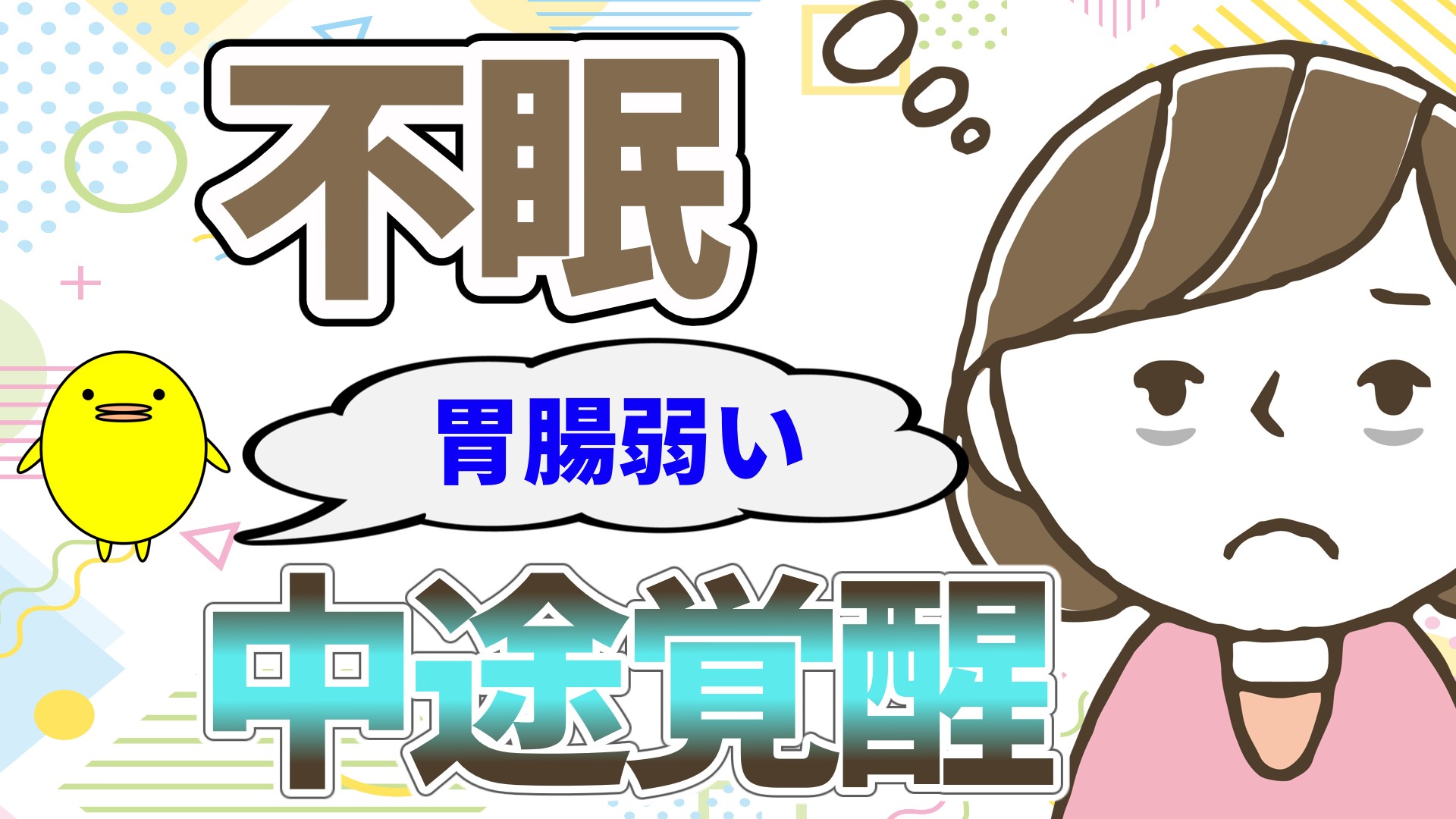こんにちは
どうなさいましたか?

不眠にお悩みの方から
質問をいただきましたよ。
睡眠は私たちの健康の基盤となる大切な活動です。しかし、現代社会では多くの方が不眠や中途覚醒といった睡眠の問題を抱えています。特に仕事を始めてから睡眠の質が低下したという方は少なくありません。
今回は、64歳女性の事例をもとに、東洋医学的な視点から不眠の原因と改善策についてご紹介します。この記事を読めば、単に眠れない原因だけでなく、体の中で何が起きているのかを理解し、自然な方法で睡眠の質を高める方法がわかるでしょう。
外見的な特徴とお悩みの症状
- 64歳・女性
- 身長:162.6cm
- 体重:62.6kg
- BMI:23.68
身体的特徴:
- 皮膚や髪の毛が乾燥している
- 舌の苔が厚い
主な症状:
- 不眠、中途覚醒、早朝覚醒があり、毎日4時間程度の睡眠
- 仕事や家事はきちんとこなしている
- 昼間に眠気がある
- 症状は半年ほど続いており、仕事を始めてから発症
- 食事に気を使っている
- 運動はテレビ体操程度
- たまに鍼灸に通っている
- 胃腸が弱く、冷え性で疲れやすい
- 仕事帰りの運転中に眠くなることがある
この方はなぜ不眠に悩まされているのでしょうか?
この方の症状を東洋医学的に分析すると、いくつかの特徴が見えてきます。
まず、胃腸が弱く冷え性であること、そして舌の苔が厚いことから、お腹の中に余分な水分が充満している状態(水滞)が考えられます。水滞がある場合、体内の水分の流れが滞り、様々な不調を引き起こします。
また、昼間に眠くなることから心血の不足(心臓が血液を十分に送り出せていない状態)の可能性があります。皮膚や髪の毛の乾燥からは、末端部での血の不足も示唆されますが、BMIや全体的な様子からは、体全体の血の不足ではないようです。
特に注目すべき点は、仕事を始めてから不眠になったということです。これは気の巡りに負担がかかり、気の伸びやかさが失われている状態と考えられます。
東洋医学では、心を落ち着かせるためには十分な「血」が必要だと考えます。しかし、この方の場合:
- 気の滞り(気滞)がある
- お腹に停滞している余分な水分(水滞)が血の流れを阻害している
この二つの要因によって、心に十分な血が届かず、眠りに入れなくなっています。さらに気の滞りがあるために、いったん眠りについても睡眠を維持できず、中途覚醒や早朝覚醒になっているのでしょう。
ではこの方に、おススメの自然療法を教えて下さい
この方の症状からみると、喉の渇きをあまり感じていないようです。これは、もしかすると体が必要とする以上に水分を摂り過ぎている可能性があります。その結果、のどの渇きを感じにくくなっているかもしれません。
お腹の中には動きの悪くなった水が充満しており、それが血の動きを阻んで不眠を引き起こしています。水分の摂り過ぎに心当たりがある場合は、熱中症の危険がない季節においては、喉の渇きを感じてから飲むように心がけると良いでしょう。
また、現在のテレビ体操に加えて、近所を軽く散歩するなど、体を動かす習慣を取り入れることもおすすめします。体をよく動かすことで胃腸の調子も良くなり、お腹の中の水分の流れも改善されます。気が向いたら、軽く汗ばむくらいの運動を取り入れてみるのも効果的です。
水滞・気滞体質の改善に効果が期待できる漢方薬
水滞と気滞の改善には、以下のような漢方薬が一般的に用いられます:
- 苓桂朮甘湯(りょうけいじゅつかんとう):水分代謝を改善し、不安感を和らげる効果があります
- 柴胡加竜骨牡蛎湯(さいこかりゅうこつぼれいとう):気の滞りを改善し、精神的な緊張を和らげる効果があります
- 半夏厚朴湯(はんげこうぼくとう):気の滞りを改善し、胃腸の水分代謝を促進する効果があります
※これらは一般的な水滞・気滞体質の改善に効果が期待できる漢方薬であり、この方に特化したものではありません。症状が複雑な場合には、単独では効果がない場合もあります。当店では専門の漢方相談も行っておりますので、お気軽にご相談ください。
まとめ:自然な睡眠のために
不眠症状の背景には、体の中の水分バランスの乱れや気の流れの滞りがあることがわかりました。特に仕事のストレスなどで気の巡りが悪くなると、さらに症状が悪化する可能性があります。
自然療法として、以下の点に気をつけてみましょう:
- 水分摂取は喉が渇いたタイミングで行う
- 軽い運動で体を動かし、水分代謝を促進する
- ストレスを軽減し、気の巡りを改善する習慣を取り入れる
これらの対策を継続することで、体内の水滞と気滞が改善され、自然な眠りを取り戻せる可能性が高まります。焦らずゆっくりと、体の声に耳を傾けながら改善していきましょう。
YouTubeでも解説しています。

ご自分の体質にあった
漢方薬を試してみたい方は
ピヨの漢方の漢方相談を
ご利用ください。